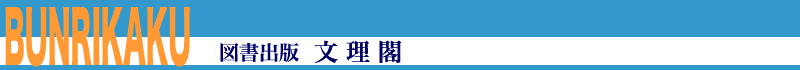
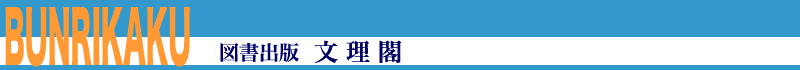 |
|
|||||||||||||||
手話を学ぶ人たちの学習室 |
|||||||||||||||
※全国手話通訳問題研究会(全通研)では、学習の機会を会員に提供し、手話に関する理論的学習を深めていくため、全通研学校を1998(平成10)年から毎年、開催しています。 全国手話通訳問題研究会(全通研) |
|||||||||||||||
 |
社会福祉と通訳論真田是・長尾ひろみ 〔真田是氏〕 右肩あがりで充実してきた日本の社会福祉は今大きな転換期をむかえている。きびしくなる現状のもとで、ヒューマンサービスに取り組む人々は「なにができるか」。福祉の歴史と動向をわかりやすく講演。 四六判 143ページ 本体895円+税 2005年2月刊 |
||||||||||||||
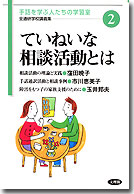 |
ていねいな相談活動とは (品切)窪田暁子・市川恵美子・玉井邦夫 あらゆる障害問題において、専門窓口での相談は本人や家族にとって大切な情報源である。全国手話通訳問題研究会は、聴覚障害をもつ人々の窓口相談だけでなく、通訳者が日々接するろう者の相談にどう対応できるかを検討するため、学習課題の一つとしてとりあげている。 本書では手話通訳現場でおこる具体的事例の検討とともに、専門学者の提案と助言から、相談による支援のあり方を考える。各種障害相談に通じる幅広い内容。 四六判 194ページ 本体905円+税 2006年4月刊 |
||||||||||||||
 |
福祉国家の姿とコミュニケーション労働
|
||||||||||||||
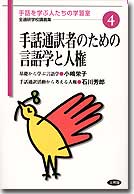 |
手話通訳者のための言語学と人権小嶋栄子・石川 芳郎 「音声言語の基本的な特性」「和語・漢語・外来語など単語の意味」ほか、日本語学の専門家がやさしく語る言語の本質と、全通研副委員長の体験的人権論。聴覚障害者とともに手話を学ぶ者の人権問題を見つめ直します。 四六判 155ページ 本体1,048円+税 2008年3月刊 |
||||||||||||||
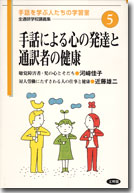 |
手話による心の発達と通訳者の健康河 聴覚障害者・児の心とそだち(河 四六判 124ページ 本体952円+税 2009年2月刊 →詳細はこちら |
||||||||||||||
 |
現代の地域福祉と障害者の発達保障宗澤忠雄・白石恵理子 地域活動とボランティア活動(宗澤忠雄) 四六判 129ページ 本体1,048円+税 2010年5月刊 →詳細はこちら |
||||||||||||||
 |
手話コミュニケーションと聴覚障害児教育本名信行・若狭妙子 手話とノンバーバル・コミュニケーション(本名信行) 四六判 117ページ 本体1,048円+税 2011年2月刊 →詳細はこちら |
||||||||||||||
 |
新しい福祉制度とコミュニティー通訳論藤井克徳 ・水野真木子 新しい福祉制度と障害者運動(藤井克徳) 四六判 136ページ 本体1,048円+税 2012年2月刊 →詳細はこちら |
||||||||||||||
 |
手話で伸びる子どもの力と障害者の福祉制度改革南村洋子 ・藤原精吾 聴覚障害児にとっての手話(南村洋子) 四六判 138ページ 本体1,048円+税 2013年2月刊 →詳細はこちら |
||||||||||||||
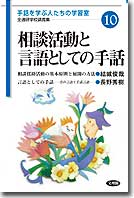 |
相談活動と言語としての手話結城俊哉・長野秀樹 相談援助活動の基本原則と展開の方法 (結城俊哉) 四六判 150ページ 本体1,100円+税 2014年3月刊 →詳細はこちら |
||||||||||||||
 |
私たちの障害者権利条約と聴覚障害者支援薗部英夫・近藤幸一 障害者権利条約批准後の情勢 (薗部英夫) 四六判 125ページ 本体1,050円+税 2015年3月刊 →詳細はこちら |
||||||||||||||