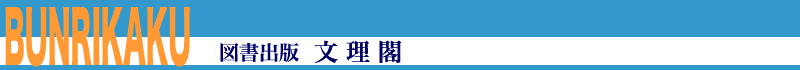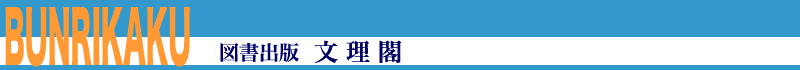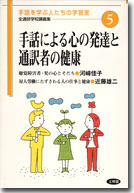手話を学ぶ人たちの学習室 全通研学校講義集 5
聴覚障害児・者の心とそだち
河 佳子(京都女子大学現代社会学部教授) 佳子(京都女子大学現代社会学部教授)
【もくじ】
はじめに
更生訓練にかかわった経緯
大切な二者関係
語られはじめた過去
聴覚障害と心理研究
「心理相談」のはじまり
健聴者モデルがアイデンティティ形成に与える影響
親子関係―庇護と依存、強制と服従の関係
空想に生きる時間の長さ
聴覚障害学生と手話との出会い
軽・中等度難聴者(児)の心理
聴覚障害者の心の風景―映像思考
手話がもたらす発達の質的変化
早期支援に求めること
おわりに
対人労にたずさわる人の仕事と健康
近藤雄二(天理大学体育学部教授)
【もくじ】
はじめに―自己紹介を兼ねて
知られていない職業、手話通訳
働くこと、その拘束性と疲労
三〇〇年前に書き残された心労
健康は手段、目的ではない
人間の権利を実現する手段としての人間工学
人権思想に裏付けられた人間工学が必要
対人労働は健康支援の職業
心の病、その対策
雇用、そこにある心的な負担
ヒヤッ・ハッ・ドキッ・グターの意味
仕事の移り変わり、休息の軽視とふえた精神的負担
精神作業とは
過重労働、負荷と負担の違いについて
大脳で判定するストレス
対人労働の負担の特性
対人労働の情動不安とストレス
仕事の特性・特徴
対策その一 法規則の活用
対策その二 不注意論・不摂生論の克服
疲労対策の意味 疲れは早期の休息でもとに戻る
現場を包括的に見て改善提案をする
良い工夫を探して展開する
最後に―いい仕事をするための健康づくりを目指して
|