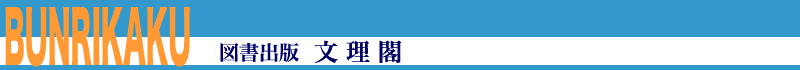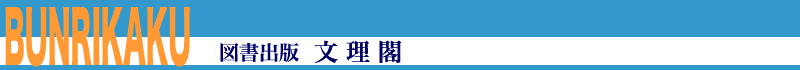| |
|
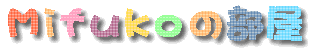
おんなと男上方流|現代のことば|MIFUKOのぷちシネマ|私の京都新聞評|Mifukoの筆箱 |
 |
MIFKOのぷちシネマ |
このページでは、映画好きの黒川が心に残った作品の映画評を掲載しています。 |
|
|
| ◆心の配達人「山の郵便配達」
制作:2001年中国 監督:フォ・ジェンチイ
 中国、湖南省の一角、深い山里を舞台に描かれた、真珠の一粒のように、清らかな物語『山の郵便配達』は、映画が終わっても立ち上がるのが惜しいほど、静かで深い感動を与えてくれた。物語も、背景の舞台も、登場する人々も、伝説の世界に彷徨いこんだように、美しかった。 中国、湖南省の一角、深い山里を舞台に描かれた、真珠の一粒のように、清らかな物語『山の郵便配達』は、映画が終わっても立ち上がるのが惜しいほど、静かで深い感動を与えてくれた。物語も、背景の舞台も、登場する人々も、伝説の世界に彷徨いこんだように、美しかった。
それは、長年、きびしい山道を2泊3日かけてたどってきた郵便配達の父が、次男坊と呼ぶ相棒の犬と、後を継ぐ息子のための最後の仕事行を描いたものである。
仕事で留守がちだった父に馴染めない息子は、寡黙な父と旅をしながら、「山の郵便配達」の何であるかを理解し、父への距離を縮め、村人との交流と人への労りを学ぶ。
盲目の苗族の老女は、糸紡ぎをしながら、ひっそり暮らしている。父はわざわざ寄り道して、一通の現金封筒を届け、いつものように孫からの便りを読んできかせる。続きを読めと息子に手渡された便箋は白紙だった。息子はすべてを悟る。
親子のたどる道は、険しく切り立った谷間の道であり、風の渡る尾根道であり、稲穂がゆれる里の道である。
それは、幼い頃の私の原風景とよく似ている。家の庭先から見下ろすと、かなり険しい坂道が白く光って見えていた。子どもだった私は、いつもその道を動く黒い人影に胸をときめかせていた。私が待っていたのは、遠く離れた町の病院で、長い療養生活をしている母からの便りだった。門口にたった郵便屋さんは、これ以上優しい顔はないといった表情で、私に手紙を渡してくれるのだった。郵便屋さんは現金書留を山の畑まで届けたり、封書と切手代を預かったりもしていた。
人々の心を届け続けてきた山の郵便配達は、どこも似ていた。
郵便配達と村人の温かい交流。その物語をこれほどの精神世界に昇華させたポン・ヂェンミンの文学、それを映像ならではの美しさに変えたフォ・ジェンチイ監督の見事さは、正に圧巻だった。
朝日シネマ「ニュース」掲載
|
 |
|
◆
ブルカに吹く風「カンダハール」
制作:2001年イラン・フランス 監督・脚本・編集:モフセン・マフマルバフ
 頭からすっぽり全身を覆う黒い女性の衣装、
チャドルやパランジャはイスラム教独特の風俗である。 頭からすっぽり全身を覆う黒い女性の衣装、
チャドルやパランジャはイスラム教独特の風俗である。
中国のシルクロードは美しいモスクの建つイスラム世界であるが、 現在、 ほとんどの女性は、 色鮮やかな洋服を着て、 まぶしいほど美しい容貌を太陽にさらして働いている。
しかし、 ときおり頭から肩までをすっぽり覆う、 目の荒いベール、 面紗を被ぶっている女性たちを見かける。 年齢や未婚か既婚かでベールの色が区別されているのだとも聞いた。
この衣服はイスラム世界の風物詩ともなって、 さまざまの映像で、 私たちの目になじんできたが、 多くの日本人はその名がチャドルやパランジャだとは知らない。
しかし今、 「ブルカ」 といえば誰もがうなずく。
新世紀の扉が開いたばかりの2001年、 ブルカはアフガニスタンの地図と一緒に、 私たちの識るところとなった。 しかも、 アフガンの人々の空前の不幸と、
私たちの新世紀への期待がもろくも崩れる報せとともに。
そんなアフガン世界を描いた映画 『カンダハール』 を観た。
この映画は、 アフガンへの世界の人々の関心を切望するメッセージで、 アメリカの同時テロ事件の前年に発表されていた。
物語は、 アフガンからカナダに亡命している女性ジャーナリストのナファスが、 地雷で片足を失った妹を探してカンダハールを目指し、 イランから国境を越える困難な道中を描いたものである。
イランのアフガン難民キャンプの学校で、 帰還を目前にした最後の授業、 女子生徒を前に先生は言う。
「明日はアフガンに帰ります。 アフガンに帰ったら家からは出られません。 でも希望は捨てないで。 たとえ塀が高くても、 空はもっと高い。 いつか世界の人々が助けてくれるでしょう。
もし、 助けてくれなかったら、 自分でなんとかするんです」
タリバーン政権下で女子教育は禁止され、 女性は男性の同伴なしには外出すること、 社会活動に参加したり働くことも禁止された。さらにブルカの着用なしに人前に姿を現すことも許されない。
ナファスはそれらを 「アフガン女性のいくつもの牢獄」 と呼ぶ。
よく見ると、 女性たちは唯一の外出着のために、 目のまわりに美しい刺繍をし、 裾をレースやフリルで飾ったり、 プリーツのあるものにしたり、
少しでもお洒落なものにと工夫している。 彼女たちは、 ブルカに隠されてしまう唇にルージュをひき、 砂と栄養失調で荒れた手にマニキュアをする。
それさえも実は禁止されているのだ。
監督は工夫をこらして映像にブルカを生かしている。
カメラに被せると、 ブルカの中のナファスの目になる。 その小さな網目の窓に広がる、 広大な砂漠。 砂丘の稜線を行く色とりどりの一団。 花嫁行列は、
それに紛れこんでカンダハールを目指す人々でふくれ上がっていく。
黄、 紫、 青、 緑、 とりどりのブルカが、 風にひるがえって赤茶けた砂漠に大輪の花々を咲かせる。 と、 突然彼女たちは、 ブルカの中に持っていた壷や荷物を頭上に載せて行進を始める。
それは、 閉じ込められた心の炎を見るようにエネルギッシュな光景だった。
アフガンの女性たちがブルカの下に抱いてきたのは、 荷物だけではなかった。
誰も抑圧することのできない自由への渇望と平和への願い、 女性の真の魂だ。
チャドルやブルカは、 イスラム世界の女性たちが、 自分の身を守るために、 長い歴史を着てきた衣装でもある。
(「高知新聞」掲載 『ひとはなにを着てきたか』所収)
|
 |
|
◆やさしさとはなにか「至福のとき」
制作: 2000年中国 監督:チャン・イーモー
 京都府綾部市にある、「いこいの村梅の木寮」に耳も聞こえず、目も見えなくなったというお年寄りがいた。施設長の大矢暹さんが、「目がみえませんから、あなたの顔に触らせてあげてもいいですか」と触手話で彼に私を紹介した。顔をやさしくなぞる手を感じながら、ああ、この方は手で私を見ているのだと思った。 京都府綾部市にある、「いこいの村梅の木寮」に耳も聞こえず、目も見えなくなったというお年寄りがいた。施設長の大矢暹さんが、「目がみえませんから、あなたの顔に触らせてあげてもいいですか」と触手話で彼に私を紹介した。顔をやさしくなぞる手を感じながら、ああ、この方は手で私を見ているのだと思った。
映画「至福のとき」の一場面で、ふとそのことを思いだした。
この映画は目の見えない少女インと失業中の中年男チャオの物語である。結婚話の進んでいるチャオの相手には、前夫が置き去りにした盲目の連れ子がいた。相手はこの子が邪魔でならない。チャオは婚約者を失わないために彼女の世話をするはめになったのだ。
マッサージができるという彼女のために、使われなくなった旧国営工場の一角に、一流ホテルを想定したマッサージ室をつくる。仲間の失業者たちを動員して、廃材で目をとじて触れると、さもそれらしきものが完成した。しかし、荒れ果てた工場跡に客がくるはずもない。客が来たとしても、その有り様が彼女に知れてはこまる。失業者仲間同士が、よれよれの服に半ズボン姿のまま大学教授や会社社長になりすまして、お客になる。
彼女ははじめてチップを手にする。チャオに手を引かれて宿舎に帰る途中、大連の町角で少女インは言う。
「仕事をくれてありがとう。一生懸命働いてお金を貯めて、目の手術を受けるの。一番見たいのは」
「お父さんか」
「社長(チャオ)さんもよ」。心を開いたインは初めて彼の顔にさわる。
夕暮れの大連の街角。家路を急ぐ人々、買い物を抱えた人々。その雑踏の中に立つよれよれの中年男と初々しい少女。少女が手さぐりで彼を見ている。人々に埋もれるるように存在する、貧しい二人の、小さな小さな至福のひとときであった。
マッサージ室は毎日続いた。しかし、問題は客をよそおう失業者仲間がチップを払い続けることができないことだった。そんな中、一人の女が紙幣大の白い紙切れを持ってくる。目をとじてさわったら、判らないだろう。ただの紙切れに彼女はすぐ気づく。彼女はやがて全てを理解していくが…。
失業者仲間が、目の見えないインを思いやって騙しを続ける。善良で純粋な騙しだ。インはそれが「至福の時」だったとテープに言葉を残して去る。
汚職、失業、過労死、暗いニュースの続く日本で、観客もまた監督に翻弄されて至福のひとときを味わう。
(全日本ろうあ連盟発行 季刊雑誌『MIMI』102 号) |
|
 |
|
◆愛のための勇気と冒険「ビッグ・フィッシュ」
制作:2004年 アメリカ映画 監督:ティム・バートン
 ドラマを紡いでいる。それが現実ばかりのリアルなものであるか、この映画の主人公のように少し脚色されたものであるかの違いかもしれない。 ドラマを紡いでいる。それが現実ばかりのリアルなものであるか、この映画の主人公のように少し脚色されたものであるかの違いかもしれない。
「小さな池の大きな魚にはなりたくない」 が、若き日の主人公エドワードの人生観だ。
池にはどんな餌でも絶対釣れない大きな魚がいた。
「俺はその魚を、結婚指輪で釣りあげたのさ」
エドワードは息子の結婚式にも、あったような、なかったような得意の話を披露して万座の注目に酔いしれていた。なにしろ最愛の息子が結婚するのだ。この上なく上機嫌で。
「父さんはいつも自分が主人公だ。だが、今日は僕の結婚式なのだ」
常々父親のほら話に辟易していた、ジャーナリストの息子は怒り心頭に達して、以来3年も口を利かない。
そんなある日、母から父親はすでにガンの末期で長くはないと電話がかかる。
身重の妻と父の元に帰った息子は、物置で「スペクター」と記された土地家屋登記簿を発見する。「スペクター」はしばしばほら話に登場した、まるで幻のような楽園だった。
「なに?」その土地がほんとうにあるのか……。
作り話だと思っていた息子は、ジャーナリストらしい探索を展開する。息子の調査とともに、明らかになる父の真実の姿。
観客もまた、ほら話なのか、真実なのか、物語に翻弄されながら、この映画のメッセージに魂を清められていく。
ファンタジーに彩りを添える人々。おとぎ話には、不思議をもった人々が登場しなくてはならない。
この物語には、覗いた人の未来を写すガラスの右目を持つ魔女、みんなが靴を脱ぎすて裸足で楽園を享受するスペクターの町の人々、いつもお腹が空いてたまらないエドワードの5倍もある巨人、夜になると狼に変身してしまうサーカスの団長、下半身が一つの双子の姉妹など、「異形」の人々が、それぞれ重要な役割を担って登場する。
そのわき役たちに、ある時はエドワードが助けの手を出すし、ある時は彼が助けられる。
人生で出会う友人たちは、共に苦境を乗り越える仲間であったり、伴走者であったりするわけだ。
エドワードが恋人、妻や息子、家族、隣人、町の人々、愛しい者のために捧げる命知らずの勇気や冒険は、私たちの人生の様々な場面で試されていることがらの象徴だろう。
人生の「ビッグ・フィッシュ」を釣るための餌はこぼれるほどの愛の宝石なのだ。
(全日本ろうあ連盟発行 季刊雑誌『MIMI』104号)
|
|
 |
|
◆心が浄化される透明な愛「オアシス」
制作:2002年 韓国映画(第59回ヴェネチア 国際映画祭「監督賞」「新人俳優賞」
監督:イ・チャンドン 主演:ソル・ギョング、ムン・ソリ DVD:バンダイビジュアル
 なにもなくても、いつか愛する人に出会える。人を思いやるやさしさがあれば、コミュニケーションが難しくても、二人はきっと素敵な恋人どうしになれる。そんなあたたかいメッセージが伝わってくる物語だ。 なにもなくても、いつか愛する人に出会える。人を思いやるやさしさがあれば、コミュニケーションが難しくても、二人はきっと素敵な恋人どうしになれる。そんなあたたかいメッセージが伝わってくる物語だ。
鏡の裏側みたいな人生を負った二人がいた。ジョンドウは兄のひき逃げの身代わりをかってでて刑務所から出たばかりだが、家族はまたやっかい者が帰ってきたと、うとましく思っている。
コンジュには、脳性マヒの障害がある。自分のための立派な障害者住宅の名義だけ兄にとられて、古ぼけたアパートに一人取り残されている。
ジョンドウはそんなコンジュに出会った時からなにか心を動かされた。「女としてなかなかの顔だ」ジョンドウの言葉でコンジュの女性が目覚める。不自由な手でルージュを引き、鏡に向かって服を合わせてみる。コンジュは少しずつ心を開いていく。
ジョンドウは彼女にきれいに身繕いさせて車椅子で外に連れ出す。しかし、外の世界はコンジュをすんなり受け入れない。レストランの客たちは明らかに不快な表情になるし、店員はていよく二人を追い出す。
「もしも私が……」時おりコンジュの顔からマヒが消えて、手はのびのびとジョンドウを抱きしめる。言葉を伝えきれない彼女の夢の世界や想像がファンタジックな映像で物語の間に散りばめられる。
『オアシス』はコンジュの部屋の壁に掛かったタペストリーのとおりに、椰子の木が繁る砂漠の中の泉だ。泉の水は旅人や動物の喉を潤し癒してくれる。ジョンドウとコンジュにはまさに愛の泉である。
しかし、監督はそこに深い意味を込めた。オアシスとは境界線だ。自分と他者、私たちと私たちが忌み嫌う相手、また健常者と障害者との境界線。愛というファンタジーと別の日常の境界でもある。
ジョンドウ役のソル・ギョングも、コンジュ役のムン・ソリ、二人があまりにも自然に役を演じきったので、最初は二人にとまどどいさえ覚えた。しかし、物語の展開と共に、この映画の美しい魂に吸い込まれ、心が浄化されるてゆくのを感じる。
二人を見て眉をひそめる町の人々や、二人の愛を理解できないジョドウやコンジュの家族、警察も韓国社会のあたり前の風景だろう。そして、観客の私はどっち側なのか、どきっとするほど深い映画だ。
最近韓国から目が離せない。
(全日本ろうあ連盟発行 季刊雑誌『MIMI』105 号 2004年8月) |
|
 |
|
◆「おばあちゃんの家」
制作:2002年 韓国映画 監督:イ・ジョンヒャン
 韓国の美しい山村を舞台に、都会暮らしの少年とおばあちゃんの物語がはじまる。 韓国の美しい山村を舞台に、都会暮らしの少年とおばあちゃんの物語がはじまる。
ソウルに住む7歳の少年サンウは、生まれてはじめておばあちゃんの家にいくことになった。離婚して一人で子育ていている母親が、新しい仕事を見つけるまで預けられることになったのだ。
サンウは列車の中でおかあさんに聞く。
「耳が聞こえないの?」
「そうよ」
「口は?」
「きけないわ」
おばあちゃんは、列車を降りて大型バスに乗り換え、つづら折れの坂道を、さらにマイクロバスに乗り換え、停留所から山道を登って、やっとたどり着く小さく粗末な草ぶきの家に住んでいた。
はじめての山の暮らし。古びたテレビは映らないし、おばあちゃんのおかずは食べたくない。サンウは母親が持たせてくれた缶詰やインスタント食品ばかり食べていたが…。
ここにはケンタッキーのフライドチキンもハンバーグもピザもない。
田舎の暮らしはことごとく不便だから、おばあちゃんにあたりちらす。耳が聞こえず、文字も知らないから馬鹿にして、悪態をつき、いたずら書きもする。
しかし、おばあちゃんはけっして叱らない。ひたむきにサンウを思って心をくだく。
ある日二人で、穫れたカボチャを町に売りにいく。ようやく売れたお金で食堂に入ったが、おばあちゃんはなんにも食べない。帰りもサンウだけをバスに載せて、節約のために何キロもの道を歩いて戻ってきた。
そんなおばあちゃんの心が、少しずつサンウに伝わり、しだいに信頼と愛情が芽生えるようになる。
真っ青だった山が紅葉し、冷気がしみるころ、お母さんが迎えにくることになった。
最後の夜、サンウは一人暮らしになるおばあちゃんのために考える。
停留所で、おばあちゃんが「さよなら」とバスの窓を叩いても知らんぷりしていたサンウだが…。
発車すると思わず最後尾の座席に走り寄り、胸をなでる手話をしてみせる。それはおばあちゃんがよくしてくれた手話だった。
私にもやさしいおばあちゃんがいた。腰は90度に曲がって、いつも2本の杖をついていた。畑仕事が大好きで沢庵漬けは絶品だった。雨の日はきまって藁ぞうりを編んでいたから家族の物はいつもたっぷり用意されていた。幼い私のだけには、鼻緒とヨコに赤い布をまいてくれた。
魅了される作品でDVDを繰り返し見た。物静かなおばあちゃんの手話が映画の心を一層深く伝えている。カメラワークもとてもいい。もう一つ、なにもかも便利になった現代の営み、これでいいのかと考えさせられる。
(全日本ろうあ連盟発行 季刊雑誌『MIMI』106 号 2004年12月)
|
|
 |
|
◆香川照之が中国のろう者を熱演「故郷の香り」
制作:2003年 中国 監督:霍建起(フォ・ジェンチィ)
 草むらを波うたせて渡る風。 草むらを波うたせて渡る風。
あの娘と通った道。
家々のたたずまい。
なにひとつ変わらないふるさとの風景。
ジンハーはこの村の出身だが、大学を出て北京の役所で働き、妻と生まれて間もない息子がいる。高校時代の恩師の相談にのるため、十年ぶりに帰省した。
用がすんでの帰り道、村の橋で大きな草束を背負った若い農婦とすれ違う。ちらっとジンハーを見る瞳、汗と泥に汚れて疲れきった顔つき。彼女は片足を引きずって歩く。
ヌアンだ。
ジンハーは忘れられない青春の日々に呼び戻された。
高校生の頃、ずっと彼女に憧れていた。一緒に大学に行こうと誘ったこともある。彼女は村に来た京劇の若手俳優に憧れ、「いつか劇団に入って彼と結ばれたい、それがだめだったらあなたにするわ」という。ヌアンの前途にもいっぱいの希望があった。
ジンハーは北京の大学に出発するとき、「必ずむかえに来る」と誓った。一緒に乗っていたブランコがちぎれて、彼女は足が不自由になっていた。最初は盛んに送った手紙も、いつしか途切れ、彼女のことを忘れてしまった。いや忘れようとしていた。
ジンハーは都会での、新しい世界に心を奪われた。
ヌアンに再会して「迎えに来なかった」痛みとともに、青春時代のままの心が、よみがえる。
忘れられた彼女は、故郷を背負って生きていた。昔となにもかわらないまま。
ヌアンは、かつて密かに彼女に憧れていた、ろうの青年ヤーバ(香川照之)と結婚し、可愛い一人娘もいた。ヤーバは最初ジンハーを歓迎しない。
「ほかに相応しい人はいなかったのか」
貧しい暮らし向きに、思わずジンハーは口ばしる。
香川のヤーバがすごい。妻と娘の、わずかな手話で暮らすヤーバの表情は、時に不安気で、時に激しい。
「香川さんは中国語ができないから耳も口も不自由なのと同じ状況にいます。私は本物の表情が欲しかった」。監督は言っている。
観客にはやがてわかる。なぜ彼女がヤーバと結婚したのか。
ヤーバはとても心が清らかで優しい。雨の中で、足の弱い彼女をかばって背負うシーンは、どんな抱擁よりもすてきだ。
ヌアンと娘は時にヤーバに手話通訳するが、ヤーバの手話には通訳も字幕もない。それでいて映画は進行する。
ラストシーンの香川の手話が圧巻だ。ヤーバは、ジンハーとヌアンが今も愛しあっていることを知っている。ヌアンを愛しているから、辛い一つの決断を、心の叫びのような手話で言う。ヤーバの愛がすごい。
物語も映像も美しすぎるほどだ。
(全日本ろうあ連盟発行 季刊雑誌『MIMI』 2005年8月)
|
|
 |
|
◆「ALWAYS
三丁目の夕日」
制作:2005年 日本 監督:山崎貴 原作: 西岸良平 『三丁目の夕日 映画化特別編』
 プロレスの力道山、インスタントのチキンラーメンやアーモンドチョコレートの誕生、そして、初めて人工衛星の打ち上げられた時代。 プロレスの力道山、インスタントのチキンラーメンやアーモンドチョコレートの誕生、そして、初めて人工衛星の打ち上げられた時代。
明日には、また新しい何かが出てきそうな、未来社会への予感と期待にみちた時代、昭和33年がこの物語の時代だった。
列車の中ではしゃぐ学生服やセーラー服の少年・少女たち。SL機関車に揺られて上野駅のホームに着いたのは、中学を卒業したばかりの集団就職の一行だった。
その中にほっぺの真っ赤な少女、六ちゃんがいた。迎えの社長さんの運転する、ポンコツでガタガタのミゼットに乗せられて到着したのは、夕日町三丁目にある鈴木オート、社長さんと家族だけの小さな町工場だった。
空には建設中の東京タワーがそそり立つ。その下には、泥んこの路地があって、煙草屋だの駄菓子屋だのが軒を連ねる、まだオンボロだった町があった。大通りにでるとチンチン電車が走っていた。
この横町で、原作の西岸良平のコミック『三丁目の夕日』の人々が、一人ひとりの小さなエピソードをくりひろげる。ちょっとコミカルで、どこか哀しく、なによりあたたかい。
一つひとつのエピソードが、21世紀の私たちは、まぎれもなくそこにいて、そこから来
たことを考えさせてくれる。
聴覚障害者も、この町のどこかにいただろう。似たような日本のどこかの町にも。
松山善三監督の『名もなく貧しく美しく』は、この映画の時代の3年後、昭和36年に撮られている。
同じ頃、ろう者のまわりにも、手話で耳の不自由な人とおしゃべりしたいと思った心やさしい人々がいた。京都で一人の看護婦さんが、「聞こえない患者さんと話したいから、手話を教えて」と提案したことから、手話サークル「みみずく」が誕生したのは、昭和38年のことで、全国最初だ。
夕日町三丁目の人々のぬくもりの延長線に、手話のひろがりもあった。
残念ながら、この映画に字幕はない。
しかし、それでもここに紹介したい名作である。山崎監督が「人々の記憶の中の昭和を創りだしたい」と願ったとおり、徹底した時代考証で再現された町とドラマが、手話のみちのりもまた、オーバーラップさせてくれる。原作を読んで映画を見ると、きっと、それぞれの物語が紡がれるだろう。
駄菓子屋の小説家茶川が恋人にプロポーズするシーンがある。指輪ケースにはどんな宝石が……。
私は、その箱に「字幕」の宝石を入れたい。日本人なのに日本映画やテレビが楽しめないのはおかしい。「昔は、字幕がなかったからね」と語れる日はいつだろう。
(全日本ろうあ連盟発行 季刊雑誌『MIMI』110号 2006年1月)
|
|
 |
|
◆「王の男」
制作:2005年 韓国映画 監督: イ・ジュンイク 原作: キム・テウン 2006年、韓国で4人に1人が見た大ヒット作
 16世紀の初頭、日本でいえば室町幕府の時代、韓国では史上最悪の暴君と言われたヨンサングンが王位にあった。「チャングムの誓い」の前の王である。 16世紀の初頭、日本でいえば室町幕府の時代、韓国では史上最悪の暴君と言われたヨンサングンが王位にあった。「チャングムの誓い」の前の王である。
地方のしがない旅芸人一座の花形チャンセンと女形のコンギルは、いつも迫力ある演技で喝采をあびていたが、食うや食わずの貧しい暮らしだった。妖しい美貌のコンギルが巡業先の有力者の夜伽までさせられても、懐が潤うのは座長だけだった。
チャンセンはコンギルが受ける侮辱が許せなかった。二人は都に出て一花咲かせようと一座を脱出した。
ようやくたどり着いた漢陽の都。二人は大道芸に割り込んでたちまち成功する。
王のヨンサングンが身分の低い芸者を妾に召しあげ、遊蕩にふけっている噂を聞くや、二人は王とその妾ノクスに扮して、その様を面白おかしく揶揄して大喝采をあびる。もう食べるものにも事欠くこともないし、その日の雨露をしのぐに不自由はなかった。
そんなおり、二人は宮廷に捕えられ、「王を侮辱した罪で死刑にする」と言い渡される「もし、王が笑えば侮辱じゃない」とチャンセンが反論したから、王の前で芝居することになった。人生に屈折している王は簡単には笑わない。すっかり緊張した一座の舞台はし
どろもどろだが、コンギルのあでやかな演技で、ついに王が笑った。
王もまたコンギルの美貌をみのがさなかった。一座は一番身分の低い賎民階級であるが、王は宮廷の反対を押し切って、召し抱え。
王ヨンサングンは、陰謀によって母を毒殺された翳りをもつ。重臣の誰も信用できない。母を追い詰めた宮廷や、官僚の賄賂をあばく芝居をさせて、おののく臣下を廃絶していく。
一方、夜な夜な、王はコンギルを召すから、妾のノクスは面白くない。彼女は謀略を図って、チャンセンとコンギルを窮地に追い詰める。
一方、暴君ヨンサングンもみずからの悪政によって、滅ぼされる運命にあった。
庶民の笑いをかっさらう、チョンセンとコンギルの機知に富んだ掛け合い。世を風刺、揶揄する仮面劇。緊張感あふれる空中宙返りの綱渡りの迫力も見どころ。
真っ直ぐに、ひたむきに生きる貧しい人々のけなげな姿。死がせまってもなお勇敢な二人の芝居も圧巻だ。日本の狂言や神楽に散りばめられる風刺や笑いに共通する娯楽の楽しみを充分に堪能させ、中世に生きた人々の、エネルギーと渇望、現実の哀しみを描いて奥深い。
映画の娯楽性とメッセージを見事に結実させた傑作だ。
(全日本ろうあ連盟発行 季刊雑誌『MIMI』春号掲載 2007年3月)
|
|
 |
|
◆「ブラック」
制作:2007年 オランダ・ドイツ・ベルギー合作映画 監督:ポール・バーホーベン 原案: ジェラルド・ソエトマン アカデミー賞外国語映画賞オランダ代表作品
 1944年のナチスの占領下のオランダ。美しい歌手のラヘルは、ユダヤ人狩りから逃れ、オランダ人一家にかくまわれていた。 1944年のナチスの占領下のオランダ。美しい歌手のラヘルは、ユダヤ人狩りから逃れ、オランダ人一家にかくまわれていた。
ある日、湖畔で音楽を楽しんでいると、突然のドイツ機が現れ爆撃で隠れ家を失った。湖畔で出会った青年ロブが彼女をかくまってくれた。そこに一人の男が現れ、身の危険が迫っていると教える。
ラヘルはレジスタンスの一員らしいその男に逃亡を頼む。彼女が、公証人から父親の財産を引き取り、約束の場所に案内されると、そこには両親も弟もいた。一家は久しぶりに再会し、安住の地へ旅だてる約束だった。
しかし、乗り込んだ船の前に、突然ドイツ軍が現れ、容赦なく銃弾を浴びせた。乗員のすべてが殺されるなか、彼女はいち早く水に飛び込み、九死に一生を得る。繁る水草の隙間から彼女が見たのは、ユダヤ人の持っていた金品を略奪するドイツ兵たちだった。それ
を指揮する一人の将校の顔を彼女は脳裏に焼き付けた。
ただ一人助かった彼女は農民に助けられ、チフスの死体を装って検問をくぐり、レジスタンスの隠れ家に救われる。やがて、彼女もレジスタンスの一員として、危険な活動に身をおいていく。連合軍の爆撃機から落とされる武器や物資を移送するのが任務だった。列車の中、危険な物資が摘発されそうな危機、彼女は機転をきかせてのがれ、空席のあるコンパートメントにたどりつく。
乗っていたのはドイツの将校ムンツェだった。ムンツェはこころよく彼女を招きいれた。紳士的な物腰の将軍と、美貌のラヘルの運命的な出会い。
そんなある日、レジスタンスに危機的事件がおこる。野菜を偽装して武器を運んでいたトラックが事故を起こし、ティムたち仲間が逮捕された。銃殺は必定だろう。仲間の命を救うため、ラヘルは身を呈してムンツェに近づくが……。
登場するのは、レジスタンスの指揮官で共産主義者のヘルベン、仲間の医師で射撃の名手ハンス、ユダヤ人を罠にかけるフランケン中尉、ドイツ軍にいるラヘルの女友達となるロニー、カウトナー将軍など。
物語はどんでん返しつぐ、どんでん返し。
ドイツが降伏しても、ラヘルは幸せになれなかった。新たな苦難と屈辱が待っていた。味方と思っていた者があざむく。彼女の家族を殺した人々は誰だったのか。
監督は言う。「あの時代の真実がどうだったのかを忠実にかつ、あっといわせるような手法で描きたかった。白でもないし、かといって黒でもない。グレーで…」
実際の出来事から作られた、恐怖と戦慄、官能の入り交じった画面、2時間24分、完全に釘づけさせる不朽の名作。
(全日本ろうあ連盟発行 季刊雑誌『MIMI』夏号掲載 2007年7月)
|
|
 |
|
◆「サンジャックへの道」
制作:2005年 フランス映画 監督:コリーヌ・セロー
 この映画は、聖地までの1500キロを徒歩で巡礼する、9人の同行者の物語。 この映画は、聖地までの1500キロを徒歩で巡礼する、9人の同行者の物語。
会社を経営する兄のピエール、妹で教師、夫はリストラされ失業中のクララ、アルコール中毒で家族にも見放され、福祉の世話で生きる弟のクロード。
ある日、この3人に、母親の遺産相続の連絡が届く。条件は3人が一緒にフランスのル・ピュイからスペインの西の果て、キリスト教の聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラまで、2ヶ月かけて歩いて巡礼をすることだった。
無信論者で歩くことなど大嫌い。兄弟仲のよくない三人。だが遺産は欲しい。
それぞれが不満ながら巡礼に参加する。
駅に集合した巡礼一行は9人。みなが3人と同様に、現代を代表する境遇にある。不治の病気や家族の崩壊、宗教や民族の問題を抱え、一番若いラムジィ少年はいまだに文字を覚えられない。
出発したものの、みんなは自分のことしか頭にない。互いに辛辣な言葉でいがみ会って
ガイドをなげかせる。
とにかく、みなが自分の荷物を背負って、その日の行程を歩くのに必死。背中の荷物がだんだん重くなる。ハイティーンの女の子はマニキュアやヘアドライヤーなど、兄のピエールはパソコンなど旅に不要な物を捨てる。
巡礼とは、人生の余分の物すべてをそぎ落とし、生きられるだけの最低の条件下で、ひたすら歩くこと。その中で、人は宗教や信仰とかかわりなくとも、もう一人の自分自身を発見する。
休憩時間に、みなが一斉に携帯電話を取り出し、外の誰かと連絡をとる姿はどこか滑稽だが、電池がきれたり、電波が届かない中で、同行の仲間に目を向け、力を合わせることに目覚める。巡礼宿や教会に寝泊まりし、不便や困難、同行者の宗教差別や民族差別にも遭遇する。
やがて、互いの苦しみや悩みに耳を傾け、いたわり、励まし会うようになる。
文字の覚えられない少年に、教師のクララはひそかに手をさしのべ、道しるべや看板が読めるようになる。
それにしても、フランスからスペインの最西端への巡礼路の景色の素晴らしさ。そこに展開する巡礼たちの感動的ドラマ。共に歩いているような錯覚を感じながら、物語は劇的なラストシーンへ。
科学文明が暮らしのすべてを満たす現代。歴史を越えて、なぜ巡礼は続くのか。本当の意味は、バスや列車ではなく歩き続ける体験で見えてくるのだ。
「赤ちゃんに乾杯」でも知られる女性監督のこの作品は、ひずんだ現代社会と、人のもつ本来のやさしさを熱くメッセージする。
母親の遺言は、遺産そのものよりずっと大きかった。
(全日本ろうあ連盟発行 季刊雑誌『MIMI』 2007年秋号)
|
|
 |
|
◆「バベル」
制作:2007年 メキシコ映画 監督:アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ 出演:役所広司、菊地凜子
 アフリカのモロッコ。山岳部で山羊を放牧して暮らす一家は、ある日、1丁のライフル銃を手にいれる。山羊を狙うジャッカルを撃つためだった。少年兄弟は、ただ、その性能を確かめたくて、遠くを走るバスを目がけてライフルの引き金を弾(ひ)いた。 アフリカのモロッコ。山岳部で山羊を放牧して暮らす一家は、ある日、1丁のライフル銃を手にいれる。山羊を狙うジャッカルを撃つためだった。少年兄弟は、ただ、その性能を確かめたくて、遠くを走るバスを目がけてライフルの引き金を弾(ひ)いた。
一方、アメリカの中流家庭では、2人の子どもが走りまわり、メキシコ人の乳母がが世話をしている。そこに、妻の容態が思わしくない。けれども、彼女が息子の結婚式には出られるように、代わりの人を頼むからと電話が入る。
もう一つ、ここは東京。ヤスジロウ(役所広司)と娘のチエコ(菊地凜子)が暮らしている。チエコは、多感なろうの高校生。母を自殺で失ってまだ間もない。
さて、一発の銃弾は、バスの窓側でまどろんでいた、アメリカ人夫婦の妻に当たり、瀕死の重傷を負う。夫婦は3番目に生まれた赤ちゃんを失ったばかりで、ギクシャャクし、その絆を取り戻すべくモロッコの旅にあった。荒涼とした砂漠。見知らぬ国の観光バスでの突然のできごと。救急車もすぐ間に合わない。しかたなく、近くの村の民家に運ばれるが現地の言葉もわからず、あせるばかり。
アメリカでは、乳母の代わりが見つからなかった。彼女は子ども二人を連れて、メキシ
コの息子の結婚式に出掛けるが…。
モロッコの少年の一発の銃弾がアメリカ、メキシコ、日本を結びながら、それぞれの人々の切ないほどの現実と哀しみを描いていく。3つの大陸のシーンが、一枚のピース画になっていく、絶妙の演出。
菊地凜子のチエコは、映画の中で最も現代を象徴するする存在。ろう者であるため青春の複雑な思いを伝えあい、共有する異性に恵まれない。そのもどかしさ。
タイトルの「バベル」は、旧約聖書にでてくる「バベルの塔」を意味している。
人々は「天まで届く高い塔の町を建て、有名になろう」と、建設をはじめる。この傲慢(ごうまん)に怒った神は、互いの言葉を聞きわけられないようにしてしまった。
一発の銃弾が世界を一つに結んでしまうほど連鎖しているこの世紀、人々は数千年の永遠の課題を背負って生きている。
ほんとうは、言葉がわからないのではない。互いの心がわからない。
互いを理解したいと願い、抱きしめあい、涙し、愛しようと葛藤する。その姿が痛々しいほど胸に迫ってくるのが、チエコの存在だ。クライマックス、チエコはそれを行為で表現する。
チエコの、アメリカ人夫婦の、山羊飼いの少年や父親の、メキシコ人乳母の、それぞれの置かれたきびしさと苦難。その中で、人々の本来の気高い魂が、香気を放つ。
(全日本ろうあ連盟発行 季刊雑誌「MIMI」2007年12月)
|
|
 |
|
◆「アース」
制作:2007年 ドイツ映画 監督:アラステア・フォザーギル/マーク・リンフィールド
 宇宙に浮かぶ、生命の星、地球。 宇宙に浮かぶ、生命の星、地球。
50億年ほど前、この地球に巨大な小惑星が激突した。そのはかりしれない衝撃の力は、地球を23・5 度も傾けてしまうものだった。
しかし、この傾きのために、この星は、驚くほど多様な地形と四季の彩りに恵まれることになった。
生命が誕生し生存できる完ぺきな条件が揃ったのだ。
誕生したさまざまの生命は、少しずつ進化をとげながら、今日まで、長い命のリレーを続けてきた。
北極の大地から、カナダのツンドラ地帯、針葉樹林のタイガ、ヒマラヤ山脈、赤道下のジャングル、アフリカの砂漠やサバンナ、海を渡って南極にいたるまでの、命の大ドキュメンタリーがこの『アース』である。
キャストはすべて動物・植物たちで、世界200 カ所以上で、のべ4500日かけて撮影された。
NHKで放映された「プラネットアース」、海洋ドキュメンタリー「ディープ・ブルー」のスタッフたちが、同時進行で撮影した映像は、最先端の撮影機器と技術が駆使され、
息をのむ迫力。
私たちはまるで、鳥になったかのように、はてし無い砂丘を、ヒマラヤの尾根を、大漠布の上空を、複雑で奇怪な岩壁の間を通りぬける。海では、鯨になって、6000キロの大航海をともにする。
樹林のなかのアムールヒョウやオオヤマネコは、こんなに近づいてもいいのかと思うほどの至近距離で、美しい瞳の輝きを放っている。
チータがガゼルの子どもを狩る、数秒間が、数分の映像に解析される。スローモーションで、獲物のノド元に正確に牙を入れる瞬間を目のあたりにする。
森の大木。その巣穴で育ったオシドリのヒナたちは、まだ羽もなく飛べないのに、数メートルをとび下りる。地面にはフカフカに降りつもった落ち葉が待っている。
水と緑を求めて、飢えながら砂漠を移動する像の群。ようやくたどりついた湖、水中で、像はかくも、のびのび泳ぐのか。
四季とりどりに変化する森の美しさ。山々は、春から夏へ、秋へ、そして冬へ…。
まるで、染料がしみ込むように変化をとげる。そこには私達の馴染深い、日本の風景も登場する。
私たちが住んでいる地球は、どれほど美しい星だろう。
みずみずしい命の躍動。しかし、この光景が危機にある。
人類の地球規模の環境破壊が、後戻りできない深刻でせまっている。
温暖化で北極海の氷は年々早く溶けだし、ホッキョクグマは海にはまり、狩りもできずに死んでいく。
地球の酸素の大半を生みだしてきた、熱帯ジャングルの伐採が、砂漠化を深刻にしている。
動物たちの姿は「いまなら間に合う」、そんなメッセージを送っている。
(全日本ろうあ連盟発行 季刊雑誌「MIMI」 2008年3月)
|
|
 |
|
◆「潜水服は蝶の夢を見る」
2007年 フランス=アメリカ 監督:ジュリアン・シュナベール
 モワモワしたぼんやりした画像、いろんな声が聞こえてくる。 モワモワしたぼんやりした画像、いろんな声が聞こえてくる。
「名前は?」
「子どもの名前は?」
質問に応えているのに、相手には聞こえないようだ。まるで、もどかしい夢をみているように。
おぼろな画像が…、ゆがんだ画像が…、鮮明になる。取り囲む医療スタッフたち。
ときおり、暗くなったりぼやけたりする映像と声は、彼自身に残された能力、左目から見える世界と、耳からの声なのだ。
主人公ジャンは目覚め、死の淵からよみがえったことを告げられる。
どうしたことだ。首から下が全く感じない。潜水服をきているように、動かせないばかりか、顔にハエがとまっても、頭をふることもできない。耳は聞こえ、言葉の思考力はあるのに声がだせない。
悩血管発作の後遺症による「ロックト・イン・シンドローム」、つまり「閉じ込め症候群」になったのだ。
ようやく動くのは、左目だけ。記憶や知力は問題ない。
そんな彼のために言語療法士が考えたコミュニケーション手段はまばたき。「はい」はまばたき1回、「いいえ」は2回。ジャン自身の言葉を伝えるのは、どうやって?。それは文字だった。
「ESRIND…」アルファベット順ではなく、頻度順に並べた文字を療法士が読み上げる。必要な文字の所で一回まばたきする。それをメモしてもらい、目的の単語が終わると、まばたきを2回。
美しい療法士にうながされて、はじめて綴らせた言葉は…。「死にたい」。
しかし、マリーは辛抱強く「ESRI…」を続ける。やがてジャンは「もう自分を憐れむのはやめた」と決意し、彼女に綴らせる。「MERCI=ありがとう」。
ジャンはファッション雑誌「ELLE(エル)」の編集長だった。妻もいて子どももいる。颯爽と仕事をこなし、情事の相手も数人いる華やかな人生での突然の発症。
文字によるコミュニケーションに慣れると、彼の心は潜水服の肉体から、解き放される。心は蝶になり、過去へ自由に飛び立つ。子どもたちに会い、老いた父親に文字通訳を通して電話もする。
手厚い介護も見逃せない。彼は介護しやすい服でなく、毎朝、お洒落なセーターに着替えさせてもら。細やかな介護で、人は人たりうるのだ。
やがて、一冊の自伝が綴られた。20万回のまばたきで。(訳書:講談社刊)
身動きできなくても、人は立ち上がれる。そして、香り高い文学が生まれた。
その映像化もまた見事。映像も脚色も心の鼓動を聴くほどに素晴らしい。
(全日本ろうあ連盟発行 季刊雑誌「MIMI」 2008年秋号)
◆「愛を読むひと」
2008年 アメリカ・ドイツ 監督:スティーヴン・ダルドリー
2009年アカデミー主演女優賞 原作:『朗読者』新潮文庫
 15歳の少年マイケルは、学校の帰り体調がおかしくなり、一人の美しい女性に助けられる。猩紅熱だった。3ケ月後、退院できたマイケルは、お礼の花束をもって、彼女ハンナを訪ねた。石炭運びを頼まれて、煤に汚れたマイケルのために、バスルームを用意してくれるハンナ。 15歳の少年マイケルは、学校の帰り体調がおかしくなり、一人の美しい女性に助けられる。猩紅熱だった。3ケ月後、退院できたマイケルは、お礼の花束をもって、彼女ハンナを訪ねた。石炭運びを頼まれて、煤に汚れたマイケルのために、バスルームを用意してくれるハンナ。
そして…、浴槽を上がるとき、その背中を大きなタオルでやさしくくるんでくれた、彼女自身も裸だった。ハンナは36歳。マイケルより21も年上で、電車の車掌をしている。
マイケルは放課後を待ちわびて、ハンナのもとに駆けつけるようになった。やがて、ハンナは「本を読んで聞かせて」と求めた。『オデュッセイア』や『チャタレー夫人の恋人』などを持ち込んで、朗読するマイケル。聞き入るハンナ。
しかし、ある日、アパートには書き置きもなく、彼女の姿はなかった。
ときはたって、8年後。大学の法学部に学ぶマイケルは、ゼミの法廷見学で、ハンナと衝撃の再会をした。
「ハンナ・シュミッツ」、呼ばれた名前は、数人とともに被告席にあった。
戦争中に、彼女はユダヤ人収容所の看守として働いていた。輸送中のユダヤ人を閉じ込めた教会が火災になり、みな犠牲になった。なぜ、鍵をあけて解放しなかったかという、裁判官のきびしい審問に「あなたならどうしましたか」と答えながらも、ハンナはみずからの罪はきっぱり認めた。
明らかに不利なのに、なぜだ。はっと、その理由に思いあたったマイケル。それは、少年の日の彼には気づくべくもなかった、だれにも知られたくない、彼女のある秘密のためだった。罪を一身に背負い、誰より重い無期懲役に服した。
収監されたハンナを一度は訪ねようとしたマイケルだったが…。マイケルは獄中のハンナのために、再び朗読をはじめ、数々の名作テープをおくり続けた。
ようやく出獄する彼女に、快適なマンションと、仕事も探した。少年の日の慕情は、時をへても消えることのない、マイケルの心の灯火だったのだ。
しかし、出獄にあたってハンナはある決意をしていた…。
生活のために、大勢のユダヤ人を死に送る仕事についたことを、時代や体制のせいにせず、自分自身に問いつづけた決意。それは、数々の朗読作品の魂からみちびきだした結論かもしれない。
「あなたならどうしましたか」、法廷のハンナのことばは、今をいきる私たち自身に対する、人生の問いでもある。
ケイト・ウインスレットは、ハンナの心模様をみごとに表現した。原作『朗読者』とともに、映像と文学の深さを味わってほしい名作。
(季刊『MIMI』125 号 2009年秋号掲載)
|
|
 |
|
◆「ものすごくうるさくてありえないほど近い」
制作:2011年 アメリカ映画 監督:スチーブン・ダルドリー

「なぜ、空っぽの棺おけを墓地に埋めるのだろう」。11歳のオスカーは大好きだったパパ(トム・ハンクス)の死を受け入れることはできない。
2001年の「9・11同時多発テロ事件」の日、宝石店を営むパパは、ちょうどツインタワーに出掛けて仕事の打ち合わせをしていた。もう、パパが帰って来ないことはわかっていた。けれど……。
オスカーは、人と話すのが苦手で、あらゆることにちょっと怖がりだった。そんな息子にパパはいろんなことをしてくれた。「調査探検ゲーム」もその一つ。かつてニューヨークには6つ目の区があったが今はない。それを証明する物を探すという冒険だった。
パパの死から、ふさぎ込んでばかりのママとはしっくりいかない。そんな時、向かいのマンションに住むおばあちゃんと無線で話をする。
ようやく1年がすぎようとしたある日、パパの部屋で思い出さがしをしていて、過って割ってしまった青い壺。中から古びた封筒に入った金色の鍵が見つかった。black (ブラック)とメモがある。オスカーはパパのメッセージだと確信して、ニューヨーク中のブラックさん472人を電話帳で調べて、鍵穴の持ち主を探す綿密な行動計画をたてる。
いろんなブラックさんがいた。出会いと交流があった。だが、鍵穴の持ち主は見つからない。
そんな深夜、懐中電灯でおばあちゃんの窓にモールス信号を送った。真っ暗な部屋から返事があった。訪ねてみるとおばあちゃんは留守。しばらく前から滞在している不思議な間借り人のオジイサン(マックス・フォン・ジドー)が現れた。オジイサンは耳は聞こえるけれども、声で話すことができない。右手にはyes (イエス)、左手にはno(ノー)と入れ墨している。それでも用の足りないとき、大きな文字でメモを見せる。
このオジイサンがオスカーのブラックさん探索を手伝ってくれることになる。オジイサンはオスカーみたいに早くも、遠距離も歩けない。オスカーは地下鉄が怖い。そんな二人の鍵穴探し…。オジイサンが話せないわけにも大きな秘密が…。
子どもは学校に行く、パパやママは仕事に出掛ける。昨日に続くあたりまえの今日や明日を疑わない日々が、誰も想像しない巨大なできごとで一瞬に奪われる。ツインタワーのテロ崩壊も、阪神大震災も、3・11東日本大地震も。
無数の哀しみと絶望。それぞれは、やがて、立ち上がり鍵穴探しをはじめる。失ったものを探す途方もないかの旅。それは、私たちのすべてが、いつか、人生で出会う耐えがたい喪失と向き合う旅にも重なる。
(2012年6月15日 季刊『MIMI』136号)
本作品は、ワーナー・ホーム・ビデオで発売されました。写真提供も同社によります。 |
|
 |
|
 |
|
|