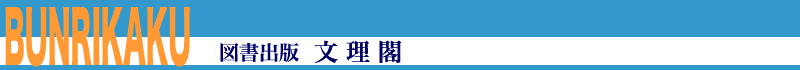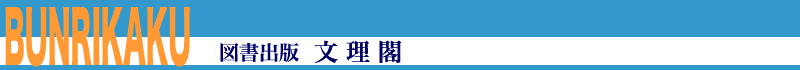| |
|
|
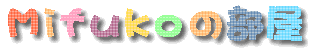
おんなと男上方流|現代のことば|MIFUKOのぷちシネマ|私の京都新聞評|Mifukoの筆箱 |
|
| |
|
おんなと男上方流
|
|
読売新聞に連載した(2004年1月〜3月)「おんなと男上方流」コラムです。 |
|
 |
|
|
| 大原女の姿におしゃれ心 (2004/1/7 夕刊
)
 京都に来て、街角でしば漬けを売っている大原女(おはらめ)をはじめて見たとき、その清楚な美しさにはっとした。 京都に来て、街角でしば漬けを売っている大原女(おはらめ)をはじめて見たとき、その清楚な美しさにはっとした。
無地の藍(あい)木綿の着物をひざ丈までに着て、糊のきいた日本手拭いを被(かぶ)っている。模様ひとつない地味な野良着だ。
そこに彼女たちはちょっと彩りを添えていた。たすきには赤、かすり生地の前掛けには赤や黄色模様のついた幅の広い紐(ひも)を付け、帯のように結んでいる。心ばかりのおしゃれだ。
たすきでたくし上げた肘から下の藍色の手甲(てっこう)、ひざ下の白い脚絆(きゃはん)がいかにもかいがいしい。
これが、頭に柴をのせて売り歩いた大原女や花を商う白川女(め)の姿である。
彼女たちは、ほのかな女の香りを漂わせた。頭の手拭いを結ばず吹き流しに垂らしている。所作で、顔がちょっと見えかくれするのがいい。
こうした姿も今ではほとんど見ることができない。大原女も白川女もどこへ消えたのか。
しかし、洛北雲ケ畑の料理屋さんに行くと、今も、着物の上に大原女と似た前掛けをしてもてなしてくれる。反物の巾三枚を胴に巻き付けるように仕立てた三巾(みはば)前掛けである。女将さんは「ここは昔、宮廷のご猟場だったんで、どんな高貴なお方の前にも、こんで出られる衣装やったんです」と語る。
誇りに満ちた衣装でもあったのだ。
大原女のたたずまいを見ていると、洛中へ商いに出掛けた女たちの、せいいっぱいのおしゃれ心が見える。
写真提供:土村清二氏
|
|
| |
|
|
着物の襟にみる「粋」と「はんなり」 (2004/1/14 夕刊)
友人の結婚式が東京のホテルであった。せっかく京都から馳せ参じるので着物にした。
晴れの席だからホテルで着付けしてもらった。プロにしてもらうとどこか華やかさがちがう。どうも襟ぐ りや襟合わせにポイントがあるように思う。襟足を後ろに引くと、アップに結った髪から襟足へ、女の項(うなじ)が強調されて色気が漂う。着物独特の後姿の魅力だ。
身を任せて着付けてもらい、鏡を見て驚いた。粋な江戸の女になっていた。京都とは明らかに着付け具合が違うのだ。
江戸風は襟合わせがずっと下の方にあって、帯の少し上というか、帯ぎりぎりのときもある。それがいかにも粋なのだ。京都はやや上にするので、東京よりも襟を詰めた感じになる。
着物を着るとき、襟元はポイントになる。洋服でいうとまる首かY字形かのような違いだ。
京都祇園のお姐さんたちと、東京の赤坂や神楽坂のお姐さんたちの着物姿の違いもここにある。
京女たちは、襟をあまり後に抜かないし、襟合わせもゆったりする。体にふわっと添うたような、いかにも「はんなり」した着こなしだ。
東京は、襟が帯びに向かって凛と走った感じで、かつ襟の合わせ目が帯のすぐ上なので、優れて「粋」である。
武士の都市だった江戸と、公家の都市だった京都では、街の人々もまた、異なった美意識をつくりあげた。 |
|
|
不平不満次々と 男を責めたてる (2004/1/21 夕刊)
女の眼は心へ走る稲妻だ。
京都木屋町のとあるカウンターバーで大学時代の友人たちと飲んでいた。
ママが
「へぇ、今日は『れんこん屋』さんにお行きやしたんどすか」
と言った。びっくりしたのは男友だちだった。
「なんで、そんなんわかるん」。
私はすでに気づいていた、彼が使っているのは、れんこん屋のマッチだと。
ああ、だから男はどじなのだ。凄腕仕事師の男にもそういう間抜けなところがある。こんな他愛もない話なら「そうか、そんで気いついたんや」と納得してお終いである。
しかし、これが家事分担や育児、はては浮気の匂いだったりするとただではすまない。妻の言葉は連射砲のような襲撃となる。そんな時、男が居直ったとするとさらに手痛い爆襲をうける。
女の日頃の思いは箱に詰まったティシュシュペーパーのようなものだ。男が一枚目を引っ張りださせたとたんに、それまでため込んでいた不平不満、鬱積まで、過去の夫の非を次々繰り出して責めたてる。
さらに女はこれを、再び元通りにたたみ直して、胸ににしまっておく。
はたまた、いざというとき同じ攻撃を受けても、男は初めて聞かされるような顔になる。要するに、居直った男は真面目に聞いてはいなかったからだ。
だから、このテッシュペーパーだけは使い捨てにならない。
京の右大将道綱の母も、鎌倉の北条政子も同じだったかもしれない。 |
|
|
京ことば40年で自分のことばに (2004/1/29 夕刊)
田舎者だからことばを捨てながら生きてきた。
故郷のことばを使って「それ、なんのこと?」と聞かれるのがうっとうしかった。
聞く方には珍しいが、聞かれる方はなんだか田舎を卑しめられているような気がした。早くその土地のことばに馴染もうとした。
出版社に入ったばかりのころ、京生まれ京育ちの同僚がいた。本願寺のお供物を扱っていた旧家育ちのお嬢さんで、それはきれいな京ことばだった。
「なあ、今夜家においないなー」
などと誘ってくれた。
彼女は全国どこから電話があっても、どこに行っても標準語は使わなかった。いや、京ことばしか話せなかった。
進学や就職でやむなく、住処を変える者は、故郷のことばを捨てる。逆に、よそに出た経験のない者は、常なる自分のことばでしか話せない。
編集者として、東京に出張し、著者回りをするようになった時も標準語を使っていた。と、関西での大学経験の長い教授から
「東京に来ても、京都のことばでおやんなさい。その方があなたの企画が成功します」
とアドバイスされた。
しかし、まだ二十代のかけだし編集者にはそれができなかった。いや、京都の経験がたった五、六年だった。京ぐらしも四十年ともなる今では、やはりそれらしいものになってきた。
しかし、上方のことばがこんなに気楽に使えるようになったのは、なんと言っても吉本興行のおかげだと思う。 |
|
|
舞子育てる祇園 少女が世界の華 (2004/2/4 夕刊)
「失礼します」、ふすまが開いて料理屋の大将が顔をだした。そのうしろに花かんざしが頭を下げている。
出版や新聞に携わる仲間が祇園の料理屋で鍋を囲んでいた。
「えっ、舞妓はん? どうしたん?」
「はあ、まあええやないですか。お店からのプレゼントです。次のお座敷にちょっと間があるんで、ここに…」
舞妓さんが入ると座敷がひときわ華ぐ。彼女の口紅は下だけ、花びら一枚の可憐さだ。
「お座敷に出ても、一年未満は上には紅ひかへんてほんまなんやね」
「そうどす。よろしゅうお頼申します」。
かんざしは二月を表す梅。帯留めは時代を感じさせる赤珊瑚に翡翠。遠くは江戸期から、代々舞妓の帯を飾ってきた置屋秘蔵の品だろう。予想もしないプレゼントに
「こっちおいで」
「こっちにも早よ」
舞妓さんと並んでツーショト。フラッシュがそこここで光る。
髪形は割れしのぶ、履物はおこぼ、肩上げの付いた衣装、振り袖にも上げがしてある。すべて少女のシンボルだ。
ここ祇園では、大金をつぎこんで、少女に芸事や作法を仕込み、舞妓を育てる。彼女たちは英国女王やアメリカ大統領など、国賓をもてなすにも臆せぬ、度胸とマナーを身につけている。
花街によっては、少女は半玉と呼ばれて、花代が半分しかない。それを祇園は舞妓という世界の華に育てた。
知恵をしぼった、奥深い女の世界だ。 |
|
|
北山杉思わす すごい写真家 (2004/2/18 夕刊)
「とにかくすごい男がいる」といえば、回りが一瞬注目する。
ほんとうだ。居間には、もう十年近くその人の写真が掛かっている。
朝もやの杉林の写真だ。ほの暗い植林に、おぼろな朝の光が届いた瞬間にシャッターは押されている。
そうだ、その人は写真家である。一幅の墨絵のようなそれを、新刊写真集で見た瞬間、「欲しい!」と思った。
早朝の杉木立の間から、生涯を林業に生きた父の姿が浮かんでくるようだった。
その、出版を記念した個展の最終日を狙って「あれが欲しい」と頼んだ。
「よっしゃ。今、持って帰り」
と、持たせてくれた。
「京都の雪は立っとる時に撮らなあかん。まだ真っ暗な刻に、ねらっているポイントへ行って、じぃーと待つんや。そして、陽がさした瞬間にシャッターを切る。京都の雪は北陸の雪と違ごうて、柔わらかい。陽が昇ったら、じきにベターと寝よる」
その人は、そう言うのだ。
「あちこち遠出する。ええ温泉もあるが、撮影したら泊まらん。その日に戻んて、現像にだす。フィルムは生き物やから鮮度がいのちや」
「シルクロードや中国へ行ったらわしは確実にはまる。わかっとるさかい行かへん」
京都北山には、雪の重さで枝が下にしなったまま、天に伸びる杉の巨木がある。形から台状杉と呼ぶ。
その杉のように根深く関西を撮り続けるひと。すごい男は山本建三さんだ。 |
|
|
使いやすく美しく 京都で出会った箸 (2004/2/25 夕刊)
「ああ、やっぱり京都の豆腐だね」そうもらしたのは、『平家物語』など日本の中世文学研究で著名な永積安明さんだった。神戸大学教授を退かれて、東京の女子大学におられた。
関西の暮らしも長かったので、京都の豆腐は格別で懐かしいと喜ばれた。
そんな豆腐料理店で、今、一軒だけ特別な箸を出す店がある。
囲炉裏の天井で燻された、古い煤竹で作られていて、割り箸より一回り細く、さらに先がより細い。
太刀魚やカレイの縁のぎざぎざの、一番美味しい米粒ほどの身をつつくのに最適という感じだ。
使い勝手がよかった。惚れた。
同じ箸に再び出会ったのは、左京区一乗寺にある曼殊院の売店だった。結構な値段だったが買った。枯淡の風情で、模様のついた塗り箸と違って、食卓で威張らない。なにより具合がいい。
もう一つ、最近いい箸を手にした。
嵐山大河内山荘に、上品な竹製品ばかり並べた土産コーナーがある。そこで、やはり煤竹を削った、ちょうど割り箸ほどの大きさの箸を求めた。色、形、太さ、先端の完成度も完璧だ。
「お箸の国の人だもの」という三田佳子さんのコマーシャルが流れたことがあった。日本、朝鮮半島、中国、ベトナム…、お米を食べる国は箸の文化をもつ。錫や銀、象牙の箸もある。
しかし、日本の割り箸を安くするために、東南アジアの樹林が消えた話など聞くとなんとも切ない。 |
|
|
「お終い」 も粋に 祇園のバーにて (2004/3/3 夕刊)
「遊びなれた男のひとは、 お店で女の右側座らはるんよ。 なんでや知ってる」
「?」
「親しくなったら、 着物の胸に手が入れやすい」
そんなことを教えてくれたのは、 祇園の小さなバーのママだった。 女の子もカラオケも置かない。 上品なお客さんばかりが通う店だった。
元はお茶屋さんにいたから、 その世界のことも詳しくて、 客一人というときなど、 面白い話を聞かせてくれた。
地味に結い上げた髪に、 着物がよく似合って、 うしろを向いてボトルを探している襟足から帯へ、 女ですら魅せられ、 癒された。
そのママから 「お店をたたみます」 と手紙が届いたので、 飛んで行った。
「もう充分やったし、 暮らしてもいける」 と語り、 後の話はしなかった。 不況のせいもあったかもしれない。
「あんた、 着物好きやったなあ。 一枚貰うてくれる?」
「ええのん」
「ほら、 あんたがいつも褒めてくれてた京小紋と椿模様の塩瀬。 あれでどう?」
すでに用意してあった。 帰りぎわに持たせてくれた。 家に戻って畳紙を広げると洗い張りした日付の符丁もそのままだった。
店終いの最後のお別れ会というのもなくて、 その日たまたま来たお客さんでお終いというたたみ方だった。
「お家の住所、 教えておいて」 と言ったら、
「また手紙でだすし」。
それっきりだった。
そっと消える、 そんな別れもある。 |
|
|
切れ水菜と鯨 絶品の旬の味 (2004/3/10 夕刊)
満願寺ししとう、 堀川ゴボウ、 聖護院大根など京野菜は種類も多い。
中でも、 葉っぱにぎざぎざのついた切れ水菜は人気がある。
もともと冬野菜であるが、 栽培技術が工夫されたのか、 年中市場に出る。
しかし、 旬のものと違って株も小さく、 姿ばかりで味は今ひとつである。
この野菜はなんといっても、 霜が降るころから二月下旬、 まあ三月上旬までが美味しい。
株が白菜の親分のように太って、 根元でつぼみの支度が始まる二月末ころのは独特の甘味がでて、 極上だ。
その水菜と脂ののった鯨の鹿子は正に旬の出会いだった。
脂のとけた出汁に、 大ぶりに切った水菜を入れ、 さっとあげてシャキシャキしたのを食べる。 ハリハリ鍋だ。
関東はマグロの中落ちとネギを鍋にしてネギマと呼ぶ。 対するのが関西のこれで、 双方とも庶民の味だ。
捕鯨禁止になって久しい。
鯨のかわりに、 ちょっとはりこんで合鴨を使ってハリハリ鍋をする。
ちょうど水菜の旬に、 東京の出版屋仲間が来たので、 我が家でこれを御馳走した。 絶品だと好評だった。
魅せられた連中は、 東京には水菜がないと八百屋で段ボール一箱買った。
鯨が減ったのは日本人やイヌイットたちが食料として捕りすぎたためではない。 産業用燃料として鯨油を取るため大量捕獲した国が、 いま世界を支配している。 |
|
|
戦乱と子供の目 終わらない悲劇 (2004/3/17 夕刊)
このコラムを、 前に担当されたのは講談師の旭堂南海さんだった。
終章を 「おきく物語」 で閉められた。 世の 「端っこ」 の物語も高座にと。
そのおきくよりも十二、 三歳年上で、 同じ戦国の世を生きた、 もう一人の女性がいた。
「おあん物語」 である。
おきくは大坂城の落城を体験するが、 おあんは関が原の石田三成の城にいた。
天守には、 取ってきた敵兵の生首が次々と持ちこまれた。 十七歳だったおあんら女たちは、 その首にお歯黒を塗る。 高貴にみせて恩賞にあずかろうと、
彼女たちに頼んでくるのだ。
しまいには 「首もこわい物ではない。 その首どもの血くさい中にねた事でおじゃった」 と語っている。
いよいよ落城というとき、 鉄砲の玉が十四歳の弟にあたった。
「そのままぴりぴりとして死んでおじゃる」。
のち土佐に移り住んだ彼女は、 晩年 「おあんさま昔物語なされませ」 と子どもたちにせがまれて回想する。
「むごい事を見ておじゃったよのう」。
今、 京都在住の 「中国残留孤児の証言集」 を編集している。
幼くして、 死体を、 殺戮を見、 一人ぼっちで大地に取り残された人々。
貧しいながら、 学校に通わせ、 大切に育てた養父母もいる。 凍てつく東北地方で、 年中裸足、 牛馬のようにこき使われ、 売買された孤児もいる。
彼らは、 「残留ではない、 国に棄てられたのだ」 と語る。 むごい事はまだ、 世界のあちこちで続いている。 |
|
|
やさしさあふれる 手塚さんの申し出 (2004/3/24 夕刊)
「手塚さんと約束はとれたけど、 24時間遅れるのはあたり前やから、 どうなるか…」
京都精華大学のヨシトミヤスオさんから電話をいただいた。 30年ほど前の話。 中沢啓治さんの 『はだしのゲン』 を出した出版社にいた。
ヨシトミさんに、 マンガでなにか面白い企画ができないかと相談した。
昔イギリスで 『パンチ』 という風刺漫画雑誌があった。 当時の日本でそんなものは出来ないかと、 手塚さんを京都に招いてくださったのだ。
心配をよそに、 時間は遅れたもののほんとうに手塚さんが現れた。
長岡京市の 「錦水亭」。 三人で、 いや、 ほとんど二人がマンガや文化を語って夜がふけ、 川の字になって寝た。
翌日曜日、 仕事があって一人事務所にいると、 ふらりと手塚さんが訪ねて来られた。
「僕の作品に 『フライング・ベン』 があるんだけど、 残念なことに原稿も本もないんです。 あれをあなたにあげるから探してください」
会えただけでも光栄で、 作品を預れるほどの会社ではなかったのに。 そこが手塚さんのやさしさだった。
それは実現しなかった。 語りあった夢も、 その出版社が傾いてついえた。
「医学部時代から貸本屋マンガを描いてたんだよ。 たからぼくの出発点は大阪なんだ」 そう語っておられた。
昨年がアトム誕生の年だった。 今、 私たちはアトムの現実を生きている。 |
|
|
障害児に捧げる500部のバイブル (2004/3/31 夕刊)
小さい出版社をやっている。
一点あたりの初版部数も多くない。
昨年は、極小の一冊を出した。
訪問教育の写真集だ。重い障害や病気で学校に通えない子どもを、先生が家庭や施設に訪ねて教える。
制度が始まったのは25年前、世界初の試みで、韓国が後に続く。
学齢期に達しても、1歳あるいはそれ以下の発達しかできない重い障害児もいる。どう教育するか。辞令を受けた先生たちはとまどった。
たいてい任期の3年で転任した。
しかし、ただ1人、以来この教育にたずさわり続けた先生がいた。
奈良に住む西村圭也先生である。
先生は寝たきりの子どもたちに、それぞれ、その子だけの手作りの椅子をプレゼントした。
天井ばかり見てきた子が、生まれて初めてお母さんの姿を横から見た。
抱っこしてその子だけのために作詞作曲した歌を聞かせて揺すった。呼吸すら苦しい子が初めて笑った。
日光浴やお風呂、音楽を聞いたり、ものを握ったり、それが教育なのだ。
先生がCDロムと分厚いプリント原稿を持って来られたのは退職してのちのことだった。
「オールカラーの本にして下さい」
「カラーは高いし、それに…」
「わかっています。いいんです。僕が責任をもちます」
退職金からお金を出して、たった500冊の本が出た。
全国でこの仕事につく先生の数だ。訪問教育のバイブルはこうして世に出た。 |
|
|
|
|
|
|
|