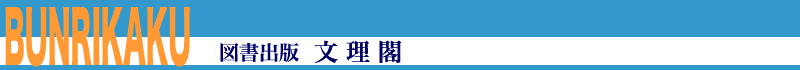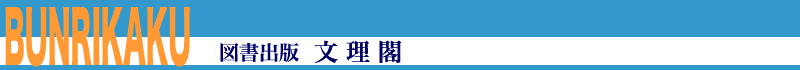| |
|
|
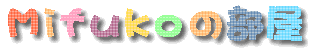
おんなと男上方流|現代のことば|MIFUKOのぷちシネマ|私の京都新聞評|Mifukoの筆箱 |
|
| |
|
Mifukoの筆箱 エッセー集 |
|
| ●日々のエッセー
|
●出版の現場から
|
|
| ◆子安大師とお地蔵さん(2016年12月26日付 高知新聞「所感雑感」)

今年も喪中葉書が届いた。数年前から、それにお悔やみ状をだしている。逝く命を惜しみ一輪、野山の花の写真を添える。
祖父が興した私の生家には、長い間、位牌のない幸せがあった。仏壇には、右手に錫杖、左手に赤ん坊を抱いた、弘法大師像が、小さな桐の小箱で祀られていた。子安大師である。
やがて、祖父母が、父母が逝き…、兄から電話があった。
「お大師様の箱をよう見たら、昭和20年の50銭玉があった。あんたのときのお供えやねえ」。
お腹の私に気づき、無事な誕生を祈って供えてくれたのは、敗戦から日も経たない、秋冷の頃のことであろうか。親亡きのちに知る、50銭玉に託された子への思い。
その後、このお大師様は兄の孫たちがお腹に宿るたび、娘たちの家を持ち回りして、安産を祈ってきたと聞いた。
我が家のお大師様は、祖父から数えて5世代目までを、見守ってくださったことになる。
そんな信仰の、もう一つが、地蔵尊であろう。子どもの守り神として中世以来、庶民のなかに根づき、野辺や街道で日本の風景を彩ってきた。
京都の町内には「地蔵盆」という行事がある。8月末の夕暮れ、あちこちのお祭り会場に、たくさんの提灯がともって賑わう。
私の住む町内でも、その日は早朝から、役員たちで路地の一角にテントを張り、床几を並べる。町内のお地蔵さんを軽トラックで迎えてきて、赤いよだれかけを、新調に替える。
子どもの多い頃は何枚も、よだれかけが掛かっていた。祈願する親の名前が記されている。
「あっ、誰々ちゃんのときのや」「誰々ちゃんのは…」と、まだ新しいのは残す。安産を祈られた子が、そのへんをトチトチと走り回っていたりもする。
ヨーヨー釣り、金魚すくい、スイカ割り、縁日が引っ越してきたような賑わいで、お坊さんを呼んでのお勤めもある。鴨川堤での花火が終わると、ビールで乾杯の大人の時間になる。
この数年、子どもが減って行事は簡素になったが、町内懇親の一夜は続いている。
最近の子どもをめぐる痛ましい事件に「地域力」を考える。
むごい虐待で摘み取られる幼い命。
震災の原発事故をいじめにする事件。それでも「しんさいでいっぱい死んだからつらいけどぼくは生きるときめた」少年。
虐待やいじめに、私たち大人は、はがゆいほどなにもできていない。
そんななか、地域が子どもを見守る伝統を、せめてもの防堤の一つにと願う。
◆弔いの風景(2013年5月27日付 高知新聞「所感雑感」)

五木の子守唄には「おどんがうっ死んだば 道端いけろ」とある。俳人正岡子規も道端か原の真中に葬り、白い石を3つか4つころがすばかりに、と書いている。
高齢社会の今日、新聞には葬儀や墓地の宣伝が競い合う。宣伝は家族葬主流で数10万から100 万円余り。一方「火葬・直葬」は5万から10万円ほど。こちらは病院や老人ホームから直接火葬場に運んで荼毘に付すもので、近年このケースが増加し、しかもお骨を連れて帰れない件数も急増していると聞く。
そんなある日、朝刊の京都地方版に見たのは「『葬儀費用ない』母親の遺体放置」の小さな見出しだった。46歳の息子が、老衰で亡くなった86歳の母親の遺体と一ヵ月以上も暮らしていた。息子は死体遺棄で逮捕された。
とても気になるニュースだった。なぜ一言、町内や行政に相談できなかったかと残念に思う。毎日お母さんの姿を見るのは辛かっただろうに。
かつて葬儀は、集落や町内の共同の助けあいに支えられてきた。訃報を聞けば「すわっ」と親戚やご近所が駆けつけ、あたたかい見送りを受けて自宅から旅立った。
今日、セレモニーホール利用が圧倒的で、加えて京都や大阪では香典辞退が一般化してきた。家族葬も増加し、周りにお手伝いを頼まない分、サービスを葬儀社からお金で買う時代になってしまった。
こうした葬儀事情から、香典の負担や手伝いで、周りに迷惑をかけられないという、肩身の狭さや遠慮から起こった事件だったら…。
実は、そんな社会問題を予期し、数年前にわたしの出版社で「宗教のないお葬式」という本を出した。
著者の柿田睦夫さんは、長年、宗教や、社会と葬儀の問題を追ってきたジャーナリスト。もう一人の北添眞和さんは仲間たちと「大阪・やすらぎ支援の会」を立ち上げた実践者。誠実な地域の葬儀店や花屋を選び、安心葬儀を実現し、福祉・医療・年金や成年後見支援、遺言書まで相談できる会。名前に「大阪」と入れたのは、ボランティア活動の一つとして全国各地にできてほしい願いからだった。
会が利用するのは、公民館など公営施設だが、自治体によっては葬儀に使用させない所もあるのがネックになる。
高齢、格差社会の現代、行政が少し窓口を広げたり公営の葬祭ホールが開設されると、シニアのボランティア活動につながり、交流と相互扶助が取り戻される。
公営の納骨堂があれば、遺族に抱いて帰って貰えるお骨も増えるだろう。
京都市は1958年に市営納骨施設、深草墓園を開設し、すでに半世紀になる。昨年の京都新聞はこの墓園の利用者が5年で7割も増加したと報じたから、時代は確実に需要を伸ばしている。
共同納骨だから墓石も不要、費用は永代で1人6千円のみ。場所が絶好の位置で、江戸期に活躍した画家伊藤若冲による五百羅漢で有名な石峰寺の境内に隣接している。境内の山肌に添って、愛らしい羅漢様たちが微笑む。
この墓園には、京都大学教授の憲法学者、川口是先生も眠っておられる。いつ訪ねても幾組かの参拝者と出会い、会釈を交わす。共同の大祭壇には花や線香がたえない。
誰もがいつか大地に還る。
次は高知の子供の詩の一節。
新聞を読むとき
おばあちゃんにたのまれた薬を探すとき
おじいちゃんは、いつもメガネをかけていた
泣きながら、骨といっしょに
メガネも拾った
(潮江東小5年 田中希枝)(「やまもも」第24集所集)
お骨を拾う家族が温かい社会は、死者にもやさしい。
◆『立命館 大学紛争の五ヵ月 1969』と写真家ー小原輝三さん(燎原 2013年5月15日第206号掲載)

永遠の友 小原さん
あなたと同じ青春をすごしました。
三冊目の写真集もようやく終盤だというのに、あなたは力尽きました。
ほんとうに悔しいです。
あなたのシャッターの音を一枚一枚に刻んで、歴史の証言としての「立命館大学紛争」の写真集を仕上げ墓前に捧げます(後略)。
この弔電を打ったのは、三月二日の通夜の日だった。
色校正が出るに日に訃報が……
去年の秋も暮れ近く、「そろそろ、大学紛争の写真集にかかりたいねん。鈴木元さんに文章をお願いして、有田知行さんに編集責任者になってもらうけど、引き受けてくれる?」と電話があった。ガンの進行を十分知っての依頼だった。
年末、小原さんと関係者で編集会議をし、新年早々には有田さんから版下プリントも届いて、大急ぎで作業をすすめたが、写真集はレイアウトやキャプションなど手間がかかる。ようやく最初の色校正が出るという二月二十八日、訃報が届いてしまった。私たちが、小原さんにできたことは、カバーデザインと写真の初校の折本を抱いて、旅だってもらうことまでだった。
二十日に事務所で写真製版直前の編集会議をしていると、小原さんが和子夫人に、後から押し上げてもらうようにして三階まで上がってきた。スタジアムにビリでたどりついたフラフラのマラソンランナーが崩れるように、椅子へ…。しかし、編集会議の内容には確認するように耳を傾けていた。しかも、帰りには「今から、パソコンを見にいこうかな」と、いつもの悪戯っぽい笑顔になっていた。その言葉に、驚異的ともいうべき、めげない闘病姿勢をかいま見る思いだった。夫人とともに、いや夫人に支えられて「細く、長く、しぶとく生きる」の合言葉での闘病がブログに書かれている。
全学集会での末川総長の写真も
四月二〇日、ようやく和子夫人の手元に『立命館 大学紛争の五カ月 1969』の完成本を届けることができた。
印刷の日、写真家の有田さんと東山幸弘さんが立ち会いくださった。印刷所への並木に、遅い八重咲きの桜が手鞠のような花房を揺らせていた。写真集は製版技術はもちろん、最後の印刷で出来ばえが決まる。二人が、細かな要望を出して、何度も刷本を確認した。そこには、「桜、今年も見られるかな」と言っていた、小原さんもいるはずだったのに。 刷本一台目には、一九六九年一月二十日の「全学集会」で演題に立った末川博立命館総長の一枚もある。
「わが立命館大学では、二万有余の学生諸君のうちの数百人の寮生諸君との話し合が封鎖された会場でなされねばならない理由は、どこにもない」、末川総長の言葉に、以後、半年余り続く大学紛争の何であるかが象徴されていた。
四四年前の光景を鮮明に
写真集発行への小原さんの思いは、「あとがき」にくわしいが、「学園封鎖が一日も早く解除され、正常な授業が再開されることを願いながらカメラで記録し続けた」と記している。小原さんは、撮影した四〇本に余るネガを除湿器に入れて、長年大切に保存していた。いつか、出版したい思いで。そのフィルムから選びつくした三二枚のカットには、四四年前に私たちが体験した、キャンパスのその日その日が焼き付けられていた。今、私が思い出そうとしても、まるでおぼろでしかないが、写真は鮮明にその光景を捉えている。 写真は封鎖された日の中川会館に始まり、わだつみ像の破壊で止まっている。
小原さんは、この撮影をとおして、常に全共闘にマークされていた。ついに、わだつみ像破壊の翌日に、拉致監禁されて、凄惨なリンチを受け、左腎臓破裂で一月半も入院する瀕死の重傷を負わされたからである。
この写真集は、正に小原さんが勇気を奮って撮影した一枚一枚である。キャプションを書くために、プリントをみていた鈴木元さんが、「これは、存心館封鎖解除のときだけど、よく見るとベニア板一枚で…」、ヘルメットも被らず立ち向かう学生たちの表情…。
小原さんは一部で、私は二部(夜間)生だったが、学生時代からの友人であった。しかし、リンチ事件の詳細を一度も聞くことはなかった。そういうことをあまり語らない人であった。この度、何度か「あとがき」をやりとりをする中で、一度だけ踏み込んで書いてきたが、結局は、その部分は鈴木さんの原稿に託する方を選んだ。
貴重なフィルムを大事に保存してくれていたことを、学友として、一出版人として、ただ感謝している。私たちは、あの大学紛争の渦中にいた。しかし、四四年後に、その写真集を出すことも、手掛けることも、互いに想像もしない青春だった。
歴史学徒の眼差しそのもの
この本で、小原さんの写真集は三冊目となる。
一冊目は、一九八七年の写真集『お日さまのまばたき−僕の子どもの保育園−』である。長男の入園から三人目の長女の卒園までの一一年間、さまざまな園の行事や日常を撮影した。写真のこちら側に、カメラを向ける子育て真っ盛りの小原さんがいる。
子どもたちのはしゃぎ声が聞こえ、送迎シーンには赤ちゃんを背負ったパパの姿もある。団塊の世代の、夫婦しての子育ての姿にもカメラは及んでいる。
二冊目は、立命館大学を退職してから出した、中国を撮った『向銭看(シャンチェンカン)−中国1988〜1997年 豊かになれる人から豊かに−』である。学生たちの短期留学を引率する機会で始まった、小原さんの中国熱はその後も続き、一冊に収まらないほどの枚数だったはずである。
「向銭看」とは、拝金主義という意味で、そこには、驀進する改革開放政策下、豊かさの一方にある、農村の出稼ぎや貧困、小皇帝とも呼ばれた象徴的な一人っ子、路地や街頭の風景まで、高度経済成長の表裏が記録されている。偶然居合わせた天安門事件の時、アスファルトにくっきり残る戦車のキャタピラの痕跡も、目敏く捉えている。
本書には、恩師の岩井忠熊先生が序文を寄せてくださった。「この写真集を見ると、今でも心があつくなる。文章の表現しえない歴史の姿がそこには生きているからだ」と書かれている。
小原さんは、ゼミでは不出来な弟子だったと「あとがき」に書いているが、三冊の写真集に収録された一枚一枚は、まぎれもなく歴史学徒の眼ざしだと思う。どのカットも、時代の情報性に満ちたものばかり。
そんな意味で、この原稿のタイトルに「写真家−小原輝三さん」と書いた。今ごろ、きっと、あのはにかみを浮かべているにちがいない。彼は「含羞の人」でもあった。
◆いのちを食べる (高知新聞 2008/3/14日掲載)
中国貴州省の山奥に、肇興(けいこう)というひなびた町がある。
たどり着くのがたいへんで、早朝、漓江(りこう)下りで有名な桂林を出発し、山また山のガタガタ道を車にゆられて、夜の十時ごろやっと到着する。
遅い夕食は、山菜や野菜が主で、唯一、玉子がご馳走だった。
その玉子がすごいっ。口にするや、何十年も眠っていた味覚がよみがえった。それは、子どものころの味そのもの。それこそ、ほんとうの玉子の味だった
翌朝、バスの窓から畑に行く農民姿が見えた。決まって、天秤の前と後に大きな籠。中に数羽ずつ鶏が入っている。
少し走ると、日は高く昇り、すでに畑を耕している農夫たち。その後を、横一列に並んだ鶏たちが、土を引っかきながら付いていく。堀り起こされたミミズや昆虫をついばんでいるのだろう。あの玉子は、幸せな鶏たちが産んでいたのだ。
ベトナムのメコンデルタには、浮島のように小さな島がたくさんある。家が一軒建ち、その周囲が農家の庭ほどの広さ、それが一つの島のすべて。川の流れに金網の囲いをして、二十羽ばかりのアヒルを飼っていた。珍客へのご馳走というので、お母さんは一羽のアヒルを捕まえた。羽がい締めにして、膝の下におさえ、クチバシを持ち上げて、頸動脈を切る。そばで、四歳ばかりの坊やが、ながめていた。
血も肉も食べる。私たちが、その内蔵を餌にもらって釣りを楽しんでいる間に、美味し
いアヒルのお粥が仕上がっていた。
地球のすみずみには、まだ、そんな暮らしがある。
私たちの食卓はそうはいかない。
店頭には、くだものや野菜が山積みされ、肉類は部位ごとに処理され調理するばかりにスライスして並べてある。どこでどのように育て、加工されたのか見る機会はない。
そんな現代の、食品生産現場を見たのは、映画「いのちの食べかた」だった。オーストリア発信のこのドキュメンタリー映画は、音楽も解説もいっさいなく、トマトやパプリカ、牛肉や豚肉、玉子などが、どんな所で育てられ、屠殺されて食卓に届くのかを、淡々と
見せる。
夜になっても煌々と明かりの灯る巨大なハウスでは、トマトの収穫。ワゴンを移動させながら、摘み取る労働者の作業は、全く無駄なく設計されたシステム。トマトは各種栄養素を詰めたブロック状のビニール袋に植えてある。収穫がおわると、袋を片付け、新たな苗セットが置かれる仕組。もはや農場とは呼べない。水と光、熱を与えてトマトを作る工場だ。
鶏舎には窓がない。電灯の光で管理され、自動給餌で鶏を飼う。一羽分のスペースに入れられた鶏は、まるで玉子製造機。口から材料を入れ、お尻から玉子を出す。
丸いドームに入れられた牛は、眉間に電極を当てられて気絶する。片足が吊るされ、機会移動し、心臓にナイフが、そして、着物を脱がせるように皮をはぎ、チェーンソウで真っ二つになって、お肉に変わる。豚も鶏も魚も…。
私たちは、そうした命を毎日食べる。
大漁だ
大羽鰯の大漁だ
浜は祭りのやうだけど
海の中では何万の
鰯の葬式(とむらい)するだろう
丸いちゃぶ台の前で金子みすずはお皿の鰯に同情した。
いま大量生産、大量消費の時代、私たちの食卓は複雑になるばかり。
ときに、はるかな命の深淵を思いやりたい。
|
|
| |
|
|
◆
幼なじみ (「高知新聞」2006/7/5 所感雑感欄)
 もう四十年以上も前、仁淀川上流の寒村で、毎日毎日、郵便配達を待つ青年がいた。しかし、一年近く、彼の待つ手紙は届かなかった。 もう四十年以上も前、仁淀川上流の寒村で、毎日毎日、郵便配達を待つ青年がいた。しかし、一年近く、彼の待つ手紙は届かなかった。
その年、同じ郵便を待つ青年たちが全国にかなりの数いた。国鉄の採用通知を受けながら、自宅待機させられていた人々だった。
そして、1965年、待機組の一人の青年が自殺した。
この事件で、国鉄はようやく待機者たちを呼び出し、職場に配置した。
村で郵便を待っていたのは、私の生家の隣に住む幼なじみだった。
ようやく、京都駅に配属された彼は、「人ごとじゃない。僕が自殺していたかもしれない」と呟いた。戦後のベービーブームに生まれた団塊の世代が、高校を卒業し就職した時代、彼のポッポ屋(鉄道マン)人生は始まった。
ちょうど、そのころ私も京都の大学に学んでいた。一足先に社会人になった彼は、ときおり、私に食事を奢ってくれた。学生運動の盛んな時代、政治を論じ、労働組合の話を聞いた。その団塊の世代が今年は還暦となり、多くは定年を迎える。彼もだいぶ前からUターンを語っていた。
6月のカレンダーをめくったばかりの日、信じがたい知らせが届いた。7月には満六十歳を迎えるはずの、彼の訃報だった。
葬儀には、彼の職場の仲間が大勢参列し、心のこもった見送りとなった。奥さんの心づかいだろう、柩のお別れも友人たちを先にして、それを遺族が見守る。花を手向けた男たちは、それぞれに眼鏡をずらして涙をぬぐった。
青い空にぬけるような悲しみ…。
「ああ、これがポッポ屋の男たちの別れなんだ。いい仲間たちの中にいたんだ」。胸を熱くした。その仲間たちが「あなたのことを聞かされてたよ。家が隣で、幼なじみだってね」声をかけてくれた。
私たちは誕生も2ヵ月しか違わなかったから、まるで双子のように遊んだ。
選挙ごっこでは、新聞紙を丸めて「吉田茂をお願いします」と村中を駆け回った。
ときにに大喧嘩もした。私が引っかいて、彼の顔に雨だれみたいなカサブタが何本もできて、見るたびにすまない思いをした。
まだ唐傘を使っていた時代。買いたての唐傘は、開くとき油の匂いとともにパリパリと小気味のいい音がする。そんな新品の彼の傘に、開いた私の傘をたたきつけて、あっちこっち穴を開けてしまった。「お父さんが町に行って直してきた」というそれには、切手ほどの同じ油紙が張ってあった。これも見るたびに反省した。
しかし、そんな時、誰からも叱られた記憶がない。子どもどうしの事だからという、大人たちのあたたかさがあったのだろう。
私がやっつけてばかりではない。家に帰って、ランドセルを見てびっくりした。背中に白い粘土が思いっきり塗りたくってあった。「やったなっ」、前を歩いていた私はまったく気がつかなかった。
泣かされたり泣かしたりしながら、私たちはそれぞれ、少年に、少女に成長した。
このごろ、秋田で亡くなった二人の子どものニュースがしきりに報じられている。原因がわからないいまま逝った彩香ちゃん。その母親に殺されたという豪憲君。二軒隣で育っていたから、私たちと同じように遊んだり喧嘩していただろう。
なぜ、あんなことが…。
戦後の貧しい時代を、慎ましく暮らした私たち。子どもをめぐる事件が起きるたびに、私たちは、ずいぶん遠くに来てしまったと、複雑な思いだ。
今日も空はただ青いのに。
|
|
|
◆牡丹と芍薬 (『M・O・H通信』12号 2006/4)
 風ありとうなづきあふや寒牡丹 (阿波野青畝あわのせいほ) 風ありとうなづきあふや寒牡丹 (阿波野青畝あわのせいほ)
寒牡丹で知られる奈良の石光寺(せっこうじ)には、初詣を兼ねて数回、花を見に行った。境内には牡丹を囲う藁づとが、唐傘をすぼめたような恰好でいっぱい立っている。霜や雪、寒風から牡丹を守るためだ。その一つひとつをのぞいてみると、ふくらんだつぼみや、花を二、三輪咲かせたのもある。桜のころに一斉に咲き誇る華麗な花と違って、冬のはひとまわり小さい。清楚で可憐、なにより冷気の中で凛としている。花二、三輪がゆれる様を青畝は「うなづきあふや」と詠んだのだ。藁づとに守られて風もそれほど強くあた
らないのだろう。
牡丹は、古来、野性の根を漢方の生薬(しょうやく)に利用していた。中国でも、鑑賞 用として栽培されたのは唐の時代(七世紀から八世紀)からで、その気品は百花の王「花
王」と称された。
西安郊外の長安市に玄奘三蔵の眠る興教寺を訪ねたことがある。ちょうど牡丹の盛りで、境内のあちこちに咲き乱れていた。ふと見ると、散った花びらを、庭の石畳に集めて干
してある。まるで赤紫の絨毯だ。通りかかったお坊さんに聞くと「花茶」として楽しむの だという。開花のときの、あの芳香がするのだろうか。
牡丹は奈良から平安時代に渡来した。鑑賞用として栽培されるのは平安期からだ。最初は貴族の庭園で、鎌倉、室町期には大寺院でも作られた。江戸期に武士や庶民まで広がることで、品種も急速に増えた。一七世紀末の園芸書『花壇地錦抄(かだんちきんしょう)』には325品種が記録されているという。寒牡丹もまたこの時期、日本で作られた品種である。
牡丹とよく比較される芍薬は少し遅れて咲く。牡丹の魅力が華麗さにあるなら、芍薬はそれに劣らない美しさ、控えめな気品が魅力で、花ことばも「恥じらい」である。
生薬としての効能は紀元前から中国だけでなく、ヨーロッパでも認められていた。その分布も日本、中国、朝鮮半島、シベリア、ヨーロッパと広い。ギリシャ神話では、医薬の神パイオンが用いて、神々の傷を癒したことから、その名もパイオニーアと呼ばれた。古代・中世のヨーロッパでは、昼間に根を採集しているのをキツツキに見つかると目をつぶされるなど、災いがあるとされた。夜間、紐に結んで犬に引っ張り抜かせたというから面白い。
鑑賞用として栽培されるのは、中国では晋の時代(三世紀〜五世紀)、欧米では中国や日本から渡ったものが盛んに交配された。18〜19世紀のことである。
春から初夏にかけて咲き乱れる牡丹や芍薬。色もとりどり、花びらもさまざま。お洒落した花々が風に揺れる。それぞれに思いのこもった品種名がある。
現在三千種以上あるという芍薬の園芸品種がどのようにして誕生したのか。それは枝分かれや実生(みしょう)(実ばえ)からだという。数万、数十万もの種を蒔く。芽生えた苗から貴重な価値をもつものだけが選ばれる。成長を見守り結果を待つ。種蒔きと選抜のたゆまぬ努力の繰り返し。品種改良にかける情熱とロマンに支えられて、誕生してきた花々だ。
私の庭では、牡丹と芍薬が仲良く一つの株から花を咲かせている。元々は割り箸ほどの一本の牡丹であった。ようやく一輪の花をつけたのは三年後だった。かれこれ十五年もたったとき、ふと根元を見ると芍薬の芽が出ている。びっくりして京都府立植物園に電話してみた。「当然です。牡丹は生命力の強い芍薬に接ぎ木してあるのです。芍薬は原種なので、たいした花じゃありませんから、摘み取るのが牡丹のためです」。そんな返事だった。
芍薬は十五年近くも、人知れず地下で牡丹に栄養を送り続けてきた。やっと自分の芽を出したのだ。そう思うと、とてもむごくて摘み取れなかった。
やがて一輪の花が咲いた。一重で、白にほのかなピンクを添えた、山芍薬のような素朴な花だった。寂しげな花もまた風情がある。今では、活き活きと繁殖してきた。今年の秋には、牡丹から株分けして芍薬の長年の労に報いたい。 |
|
|
◆2月の切れ水菜 (『M・O・H通信』11号 2006/2)
 ほんのりといそいで廻る水菜売り ほんのりといそいで廻る水菜売り
辞典の紹介には「雑俳、手引草」とあるのだが、作者を調べあたれない。
正月二日、江戸、京都、大阪の三都では、初売りとして丑から寅の刻(午前1時から5時)のころ、ロウソクを灯して蔬菜類の初売りをした。ほんのり空も明けそめたので、あわてて水菜を売り廻っている情景だろう。
今、水菜は「京のブランド産品」のロゴマークつきで、年中出回る京野菜の代表格である。
農家に聞くと、年中出回っているのはハウス栽培で、種蒔きから収穫までが、夏期で二十五日、冬季で六十日から八十日という。根元が親指ほどに育ったら出荷される。
元京都府農業指導所長の林義雄さんによると、そのルーツはナタネ油をとるアブラナ菜だという。どこで誕生したかは不明だが、江戸初期の京都、東寺や九条のあたりで、畦の間に水を引きいれて作ったことから「水いれ菜」と呼び、やがて「水菜」になったと推理されている。
関東では「京菜」と呼ぶ。別名もいろいろあって、千筋菜、千本菜、糸菜、柊(ひいらぎ)菜。私の故郷高知県では糸菜だった。白く長い茎(葉軸)を糸に見立てた呼び名だ。千筋や千本にも、葉軸の数が多いことが象徴されている。柊菜は、葉っぱの姿がギザギザなところから呼んだのだろう。京都では葉先の丸い壬生菜と区別するため「切れ水菜」と呼ぶ。
その地、かの地で人々が親しんだ、冬の菜っ葉なのだ。
水菜のほんとうの旬は霜の降りる晩秋から、蕾をつける3月半ばまでである。
「今日のおばんざいは、お揚げさんと水菜の炊いたんよ」とか会話されて、京の庶民の食卓にのってきた。きばった料理ではなく、日常のお菜(おかず)である。
ちょっと張り込むときには、揚ではなく、鯨の鹿子、いわゆるベーコンにする部分や、黒い皮のついた脂のコロだった。あつあつをふうふうしながら、水菜に熱がとおり過ぎず、まだシャキッとした所でたべる。ハリハリ鍋である。
今、鯨のハリハリ鍋はめったなことでは食べられない。IWC(国際捕鯨委員会)の決定を受けて1985年、日本が捕鯨禁止を受け入れたからだ。
それでも、旬の水菜を見つけると、どうにかして、ハリハリ鍋が食べたい。そこで考えたのが脂身の多い牛肉のコマ切れや切り落とし、豚のバラ肉を使う。来客のときは合鴨を奮発するから、薬味に柚子が欠かせない。
ところが、このハリハリ鍋が今危機にある。
主役の切れ水菜の露地栽培が減っているうえに、冬場でも旬まで待たないで市場にでるからだ。若い株は鮮やかな緑は確かに美しいが、味は太った旬の露地栽培の、葉先がちょっと霜やけしたような株にはかなわない。白菜の大玉ほどになった株が早春の気配を感じて、つぼみをつける身支度の頃こそ旬の旬だ。噛めば茎から甘い汁が口中に広がる。本来、風花や霜や雪、寒風に育てられ、春を待つ野菜である。
残念ながら、今では旬の大株にはなかなか出会えない。私の手近では、京都のプラッツ近鉄の矢尾吉さんだけが農家の名前入りのを出す。旬を食べさせてくれるために、天候とにらめっこしながら、畑をやってくれたのは、このお百姓さんなんだ。熱い思いで、大株を抱えてかえる。今夜は合鴨を奮発するしかない。
|
|
|
◆悲劇を生んだコロモジラミ (『からたち』第49号 下京社会保険委員会誌 2005/8)
 焼け跡の町に建つバラック。買い出し列車の人の群。ごった返す闇市。誰もの脳裏に浮かぶ戦後の映像だ。 焼け跡の町に建つバラック。買い出し列車の人の群。ごった返す闇市。誰もの脳裏に浮かぶ戦後の映像だ。
もう一つ、必ず浮かぶ光景がある。頭から、襟足から、背中に浴びせられる白い粉。シラミ退治のために、アメリカ進駐軍がたずさえてきたDDTの洗礼だ。ノミやシラミ、蚊など人類はさまざまの害虫に悩まされてきた。伝染病を媒介し、甚大な被害がでるからだ。
ネズミに運ばれたペストはヨーロッパで、古くは6世紀ビザンチン帝国の時代から、中世から近世に至るまで、しばしば歴史を動かすほどの流行をみた。先に死んだものを弔っても後で死ぬ自分を弔うものはいない。高貴な身分でも死体埋葬の余裕がなく、倉庫の荷物のように山積みされたといわれる。ヨーロッパの歴史は、ペストや黒死病を語らないではすまないほどだ。
一方、日本の戦後風景の点景ともなったDDT散布の光景は、シラミ退治のためだった。発疹チフスを媒介するからだ。
この病気は、16世紀のヨーロッパでは「牢獄病」「従軍病」「不潔病」と呼ばれ、しばしば、軍隊で蔓延し、戦争の勝敗を決定づけるほど深刻なものであった。
最も有名なのが、19世紀、ナポレオンのロシア遠征における罹患である。当時発疹チフスはポーランドとロシアの地方病といわれていた。ナポレオン軍はポーランドの農家に宿営中シラミを拾い、発疹チフスに罹患した。シラミは瞬く間に軍隊内に拡がった。70万人という世界最大規模でフランスを出発した軍隊が、モスクワ進撃時にはわずか16万に、二週間後には13万に減った。すべてがシラミによる被害ではないとしても、おびただしい犠牲者がでた。世界史を左右するのは、戦術や軍隊の優劣だけではなかったのだ。
発疹チフスは血液中にいる微生物、リケッチァという病原体をシラミが吸って、人に媒介する。潜伏期間は12〜14日、発病すると突然、悪寒を覚える。2〜3日後階段状に熱が上がり40度の高熱が10日ほど続く。発疹は3〜4日後、上半身の肩甲骨あたりから全身にひろがり、手のひらや足の裏に及ぶこともあるが、顔には少ない。発疹が出始めて数日後に出血斑がおこることもある。高熱のため頭痛、意識混濁とうわ言、不眠、不整脈などが患者を苦しめる。通常の場合死亡率は10〜40パーセント。
ペストや発疹チフス、コレラ、天然痘などといった伝染病は、まだ衛生状態が未発達の段階に、点在していた世界が交通や商業の発達で、交流し結ばれていくことによって伝染し、多くの被害をだした。いわば、文明の発達が媒介者でもある。
なかでも、発疹チフスの媒介者のコロモジラミは、じつは人類最初の文明から誕生した昆虫という点で、たいへん興味深い。
人類がいつの頃から「コロモジラミ」に悩まされたかは、長いあいだ研究者の注目する所だった。コロモジラミは人類が衣類を身にまとうようになるとともに、頭髪に住む頭ジラミが進化して誕生したといわれる。なぜならこのシラミは人体を離れると24時間以内に死んでしまう。体毛の短い裸の人間では生息できないし、原始的な生活をしている人々には見当たらないのが普通である。
では、人はいつから衣類を着たか。衣類の繊維は腐敗しやすい。これまで、獣の皮をなめす石器や糸つむぎの紡錘などから遡るしかなかった。
ところが2003年8月、この捜査に一つの結論がもたらされた。謎を解いたのは歴史家でも考古学者でもない。シラミと遺伝子研究者たちだった。
ドイツ・マックスプランク進化人類学研究所の研究グループである。彼らはコロモジラミの細胞にある、ミトコンドリアからDNAを取り出して、他のシラミなどと比較した。その結果コロモジラミの誕生を約7万年前だと断定した。それは、森を出て地上生活を始めた人類の祖先が、北アフリカからヨーロッパに漕ぎだした時代のことだ。
21世紀初頭の今日、「コロモジラミ」は、私たちに新たな科学の情報をもたらすメッセンジャーとして登場した。
人体に寄生するシラミは三種類だ。頭ジラミ、その他の毛に住みつく毛ジラミ、そして衣ジラミである。コロモジラミの蔓延で、現代日本人の記憶に残るのが、戦中戦後の一時期である。
空襲ですべてを焼かれ、着替えもなく入浴もできない環境こそが、シラミの天国だった。米粒の半分くらいの白い虫は、繁殖力がつよくどんどん増えた。
ともかく一日5個以上を一ヵ月に渡り毎日産卵し続ける。無数のシラミがそれを繰り返すから、おそろしいことになった。
当時の体験者は「噛まれるとがまんできない痒さだった」「夜も痒くて安眠できなかった」「衣類の縫い目にびっしり産みつけたタマゴはなかなかとれなかった」と口をそろえる。
17世紀のヨーロッパ淑女の教育でも、人前でみだりに体を掻いてはならないと教えたというから、貴婦人ですらシラミから身をまもるのは難しかった。
ノミやシラミといった害虫も、さまざまな病原体による疫病も、総体的な環境衛生が整備されないと、特権階級といえども、その汚染から逃れることはできない。人や物を介して豪華な宮殿にも被害は及ぶ。
上下水道やゴミの除去、都市の環境整備や公衆衛生の発展、清潔な暮らしが確立しなければ解決されない問題である。
焼け跡にはびこったシラミはとどまるところがないかの勢いだった。DDT散布にもかかわらず、終戦の翌年には全国で3万2366人が発疹チフスに感染し、3351名が死亡した。さらに天然痘で3039人、コレラで560人が死亡している。戦後の貧困と不衛生のためだ。
ちなみに近代日本における発疹チフスの発症は大正3年2月、東京で発生し各地に流行し、年末までに1176人の死者をだした。この年の4月やはり東京でペストも発生している。昭和17年と19年にも発疹チフスの記録がある。疫病の流行は「社会の病気」なのだ。
体験者は「ところが、シラミはある日突然、ふっつりと姿を消しました。毎日やっていたシラミツブシが今日いらないみたいな消え方だった」と語る。
戦後荒廃から人々は少しずつ普通の暮らしをとりもどしていた。昭和26年には、東大医学部が発疹チフス研究のために、東京駅、上野駅の路上生活者からシラミ一匹を10円で買い取っている。このころすでに、一般的に入手しがたくなるほど淘汰されていたことを示している。
そのころ、私の故郷高知県の山間の小学校では、まだネズミのシッポが売れていた。学校に持っていくといくらかのお小遣いがもらえたから、私の兄など、ネコからネズミの尻尾をもらっていた。衛生のためのネズミ駆除に多少の予算が組まれていたのだ。
今日の私たちは潤沢な衣類の中で「明日はどれを着ようか」と迷っている。「抗菌」をかざしたさまざまの製品は神経質なほどだ。
すっかりシラミのことを忘れていた。
ところが、最近この名前を聞いて、改めて時をひきもどされた。
「コロモシラミが湧いてね。たいへんでした」
と語ったのは、「京都・平安郷開拓団調査会」で旧満州に同行した、当時の体験者村田省一さんだった。終戦後、村田さんは開拓地から何カ月もかかって、ようやく瀋陽(旧奉天)にたどりついた。無蓋の貨車で食事もなく、わずかの水だけで、何日も立ったままの旅だった。避難を始めたのは八月だったがすでに冬になっていた。途中、ソ連兵や中国人の略奪にあい、着の身着のままの夏服姿だった。避難開始以来数カ月、入浴も着替えもできなかった。
衛生事情の悪い収容所ではたちまちシラミが蔓延した。ノミの活動は夏期だけだが、人間にとりついたシラミは冬期も元気だ。
たまたま発疹チフスの患者が出た。シラミの媒介で、またたく間に多くの犠牲者を出した。開拓団からの引揚者はお金もなく、自由に食べ物を買うことができなかった。収容所で出される臭くてまずいコウリャン粥が一日二杯、それが全てだった。栄養失調の上に長旅で体力を消耗し尽くして抵抗力がなかった。狭い空間に大勢が押し込まれた過密状態で、病原体を運ぶシラミの移動を容易にした。そして氷点下の人々に着替えも燃料もなく、煮沸消毒によるシラミ退治ができなかった。条件はそろいすぎていた。
その状況をそばから三木建一さんが語る。
「毎日、何人も何人も亡くなりました。ある夜、耳がザワザワ鳴るんです。『ああ、僕はとうとう耳鳴りにもなった』と思って頭をあげたら、真っ白なシラミの大群。その足音でした……」。
隣の人が死ぬと、真先にシラミが大移動する。シラミの動きで人の死を知る毎日だった。
奥地から次々と引揚者がたどり着く。いっぱいのはずの収容所は、いくらでも新しい避難民を受け入れられた。死者がどんどん出たからだ。
飢餓や病気で死ぬ人々。防空壕を利用していた墓地はたちまちいっぱいになった。凍結した地面は固くて掘れない、野積みするしかなかった。しかも、衣類に不自由していたから一夜で亡骸は裸にされ、別の誰かを温めた。地面が解ける早春を待って、腐敗直前に瀋陽の南湖(旧長沼)公園に埋められた人々は、3万人近くにおよんだ。くる日もくる日も、遺体を乗せた荷車が列を作った。
「ようやく日本に着いたら、真先にあの白い粉ですわ」
長崎・門司・下関・舞鶴など引揚港で「白い粉」DDTが散布された。
終戦から60年後の2005年4月、訪れた瀋陽の南湖公園はようやく春を迎えていた。桃の花が香り、芽吹きはじめた柳がゆれていた。三木さんのお母さんを含めて3万人に近い人々はどこに眠っているのか、それを示すものはない。歴史のキャタビラに押しつぶされた人々への限りない哀惜がこみあげてくる。
「人はいつから衣類を着たか」、謎をといたのは最先端の遺伝子研究だった。
レーウェンフックが200倍の顕微鏡ではじめてシラミの拡大図を描いたのは、17世紀直前だった。発疹チフスに有効な抗生物質が発見されたのは、20世紀半ば、戦後のことである。
今、人類は遺伝子組替に成功し、羊のドーリーを産み、さまざまの生命操作をはじめた。発達した科学をいかに使うかは、論議のあるところだ。
参考文献
・『歴史を変えた病』フレデリック・F.カートライト著 倉俣トーマス旭/小林武夫訳 法政大学出版
・『ペスト大流行−ヨーロッパ中世の崩壊−』村上陽一郎著 岩波新書
・『封印された満州』2003年〜2005年 京都新聞連載
・『世界大百科辞典(24)』平凡社
・『近代日本総合年表(第2版)』岩波書店
・『世界全史』講談社
|
|
|
◆「お幸せに」のことば (「ふきのとう通信」・65 新春号)
 京都八坂神社の初詣は通称オケラ参りと呼ばれている。 京都八坂神社の初詣は通称オケラ参りと呼ばれている。
大晦日の深夜から新年の早朝のころに、この神社にお参りし、新年の火種をいただく。火種を付けるのが、植物のオケラの繊維で、一メートルばかりの縄になっている。
オケラとは万葉集にも歌われた、古来からの菊科の野草で、春の若芽は食用に、花は茶花に、根は薬剤になる。正月を祝うトソの材料でもある。
八坂神社の奥のかがり火からオケラ縄にいただいた火種は、燃えすぎないように、消えないように上手に持って帰らねばならない。火が消えそうになると、縄を振り回す。風があたって、火はいこる。その風景は八坂神社の初詣につきものの風物詩でもある。
その火種を元に、雑煮を煮たり茶を沸かしたりする。
新年初の茶は「大福茶」と呼ぶ。この茶を沸かすと子どもの頃の茶の間を思い出す。四国山地の私の生家でも、元日の茶の風景があった。
祖母は言葉をあらためて祖父に茶をささげる。
「大福をいただいてつかされ」
「大福をいただきましょ」
祖父が答える。
いろりには大晦日に用意した「福くんぜ」とよぶ、大きな樫の丸太が燃えていた。「くんぜ」とは薪のことだ。生木の樫は、燻されながら少しずつ燃えていく。幹の中の方が窪んで燃えるので、それを臼に見立てる。深く大きな臼になると「今年は世がよさそうだ」などと、その年の五穀豊穣を願い、占った。
農家だったから、二日には「蒔き初め」として、畑の一角で種蒔きの儀式があった。家族全員がそろってする儀式だった。形ばかりに、父が鍬で耕し母が大豆を蒔くと、みなで「お弁当」に見立てた干し柿を食べて終了した。
祖父、祖母、父、母、それに兄弟姉妹がいるという、サザエさんやちびまるこちゃんの家と同じく平均的な日本家庭の一情景で、私の家はただ農村にあったにすぎない。
今、単身生活者の私には家庭がない。それでも、正月には大阪にいる兄夫婦一家を訪ねて、幸せのおすそ分けを貰っている。
「幸せ」、それを強く感じたのは、一昨年の正月だった。
「今年はどこに初詣に行こうか」と話題になり、応神天皇を祀った地元の誉田八幡さんに出掛けた。鳥居の前で、兄夫婦と、その娘や夫たち、孫らと一緒に新年の記念撮影をすることになった。一枚目のシャッターを兄が、二枚目を私が押すことにしていた。
兄がカメラを構えたときだった。一人の見知らぬ老人が近づいてきた。
「そら、あかん。おじいちゃんが入らへんやないか。私が撮ってあげよう」
私たちは、その好意に甘えて全員で記念写真におさまった。
ほんとうに優しい心づかいの方がいるものだと、振り返ると、去りゆく後ろ姿はただ一人だった。たった一人で初詣に来た老人が、私たち家族の情景に目をとめ、親切な申し出をしてくださった……そんなことを思って見送っていた。そこへ、カメラを受け取った兄が戻って来た。
「あのおじいちゃんな、『お幸せに』って言ったんや。普通お正月やったら『よいお年
を』っていうわな」
数日後、兄から写真が届いた。
冷蔵庫のドアに貼ると、見るたびに幸せをくれた老人の後姿が浮かんでくるのだった。
暮れに、映画『三丁目の夕日』を見た。西岸良平の同名のコミックの映画化である。集団就職で、東北からやってきた六ちゃんが住み込む東京の下町で、貧しく、けなげで、哀しく、愛しい人々のエピソードが紡がれる。シャッターを押してくださった老人は、昭和33年、あの映画にいた働きざかりの人々の延長線にオーバーラップする。
そうだ、私たちはあそこから、現代の日本に来た。まだやさしさは取り戻せる。 |
|
|
◆墓標なき慰霊の旅路 (高知新聞 所感雑感 2005/6/10)
 写真:松花江のほとりで(2005年4月16日) 写真:松花江のほとりで(2005年4月16日)
北国特有のニレの木立が、ようやく芽ぶこうとする季節だった。「京都・平安郷開拓団調査会」の一員として、はじめて旧満州を訪ねた。
調査会の中心メンバーは、少年少女時代、開拓団の家族として渡満し、敗戦後幾多の苦難を越えて帰国した人々だった。
誰もが引き揚げ途上に家族の多くを失っている。瀋陽(旧奉天)・長春(旧新京)・ハルビン・開拓地の舒楽村、それぞれの地に関係者の誰かが眠っていた。
花束や日本の煙草やお菓子を手向けて黙祷する、巡礼の旅だった。どこにも墓標もそれらしき痕跡もない。収容所跡は近代化による建設ラッシュで取り壊され、ゴミと瓦礫の更地だった。数万人が埋葬されたという南湖(旧長沼)公園も、春を告げる桃の花が咲き、芽吹き始めた柳の枝が揺れているだけだ。
それでも、現地に立つと新たな記憶が呼び覚まされる。みながいろんなことを語り始めた。
三木建一さん(京都)は「収容所では、毎日、何人も何人も亡くなりました。ある夜、耳がザワザワ鳴って目がさめた。『ああ、とうとう耳鳴りまで…』と思って頭をあげたら、真っ白なシラミの大群、その足音でした」。隣の人が死ぬとシラミが大移動する。着の身着のまま、不潔な環境で大量発生したコロモジラミは発疹チフスを媒介した。またたく間に多くが命を落とした。十三歳の三木さんは飢餓でお母さんを失い、現地召集されたお父さんはシベリアに抑留され、ついに帰らなかった。
過酷な運命に翻弄されながら、自力で道を切り開き帰国した女性もいる。佐野陽子さん(静岡)は日本人によって中国人に売られた。「五百ルーブルで買ったんだ」と、八歳の少女はムチやこん棒で叩かれ、こき使われた。しかし、やさしい中国人もいた。逃亡した陽子さんは、革命後の女性公安員の助言で裁判に勝利し、自由の身になった。裁判中、無償で保護してくれたのも中国人の一家だった。
村田省一さん(京都)は終始、列車の窓から地平線に遠い視線をおくっていた。そのころ十三歳だったが、引き揚げ列車の中で九ヵ月の弟を亡くした。母乳がかれての餓死だった。線路ぎわの草むらに小さいおくるみ姿のまま置き去るしかなった。その母もようやくたどりついた収容所で力尽きた。収容所の腐ったコウリャンがゆは、いくらお腹が空いていても喉を通らない不味さだったという。もう一度食べてみましょうかと、注文した。「美味しいなあ。こんなに美味しかったらあれほど死ななんだのに…」村田さんがつぶやいた。
慰霊の旅は続いた。だが誰も泣かなかった。それが六十年の歳月のむごさだ。死が日常だった当時、肉親の死にさえ涙は奪われていたのかもしれない。
開拓団は本土空襲となってなお、まるで棄民のように送り続けられた。同行した平安郷開拓団の人々は大阪大空襲を耳に出発している。百三十七人中九十二名が亡くなった。
関係者の一人は今、高知県にご健在である。彼女は十七歳で、亡くなった兄夫婦の幼い子ども三人を託された。自分の病気のためやむなく孤児施設にあずけた子どもたちは、行方不明のままだという。
高知県からの渡満は西土佐村や十和村などから、一万四百八十二名。二千六十四人が亡くなったといわれる。開拓団の派遣数では全国一位が長野県、高知県は十位で四国で最も多い。この数字は何を物語っているのか。開拓団とは何だったのか。
|
|
|
◆観て楽しむ嵯峨野 二つの風−
「愛宕念仏寺」と「人形工房&カフェテラス アイトワ」
写真:豆塚猛
野は 嵯峨野、さらなり。印南野。交野。狛野……」清少納言が『枕草子』に、「野といえば嵯峨野はいうまでもない」と筆頭にあげているが、今も風情のある土地柄である。
コミュニティ嵯峨野の周辺を散歩してみると、映画やマンガ『陰陽師』でおなじみの安倍晴明のお墓や、江戸時代、嵐山を流れる大堰川の改修や、京都の市街地の高瀬川を開いた角倉了以を祀る神社などにも行き当たる。歴史が静かに眠っている町だ。
『源氏物語』にでてくる斎宮ゆかりの野宮神社も近い。紫式部は、見渡すかぎりの野辺は「ものあわれ」だと、当時の風景を描いている。野宮神社への竹林の道は、人影が少い時には、今にも光源氏の牛車が現れても不思議でないような趣がある。
そんな嵯峨野で、ろうあ者が一番楽しめそうなところはどこか。カメラマンの豆塚猛さんと二人で散策した。
〔おたぎ念仏寺〕
嵯峨野には有名な二つの念仏寺がある。「あだしの(化野)念仏寺」と「おたぎ(愛宕)念仏寺」である。「化野は昔の人のお墓をいっぱい集めて供養した所でしょう。お墓より、羅漢さんを観ませんか。なんだか極楽みたいですよ」豆塚さんに誘われて、おたぎ念仏寺に向かった。
観光客で賑わう嵐山の天龍寺門前の通りを、清滝方面に奥深く入ってゆく。里の風景がとぎれ、道の両側に山が迫ってくる所。行く手に見えるトンネルの手前、山はだに這い登るように建っているのが、おたぎ念仏寺である。
ここは誰でも自由に拝観できる開かれた寺である。建物の下のトンネル状の通路を抜けると、右手におだやかなお顔の石仏群が「いらっしゃい」と声をかけるように迎えてくれる。そこから、羅漢さんたちの世界である。
 
思い想いの表情、さまざまの形。
風雨にさらされ、苔むした姿は、完成からわずか20年ばかりとは思えないほど古色をおびて、静寂の山の景色に溶け込んでいる。
この羅漢さんたちは、20世紀のごく普通の人々が、仏像彫刻家で住職の西村公朝さんの呼びかけで、いろいろな祈りや願いを込めて彫ったものである。それぞれが、自由にノミをふるい、心の羅漢さんを表した。
上段の本堂に向かって「く」の字の坂道がある。その道のそばにも羅漢さんが微笑んでいる。「お参りですか」とささやいてくれるようだ。
本堂に登りつくと、山を背に雛段状に、これまた羅漢さんがずらりと並んでいる。総数は1200体だという。
ギターを弾いている羅漢さん、カメラを構えたの、「まあまあ、一杯やろうや」とお酒を酌み交わすの、子どもを抱いたの、抱きあったの、ねこを万歳させたもの、そして合掌し瞑想する姿……。ここには20世紀末に生きた人々の祈りや願いが刻まれている。彫った人々には、戦争を体験した人、幼子や家族、恋人を亡くした人もあったろう。 遠くから泊まりがけで彫りに来た人々もいたという。
『仏像の声』(新潮文庫)という西村さんの著作には、こんなエピソードが紹介されている。
それぞれ完成した仏像について、いろいろ批評はしなかった。その人がなぜそれを彫るのかも尋ねなかった。
ところが、ある一人が、自分の羅漢さんをどう思うかと感想を求めた。像の下部には「心」という文字が刻まれ、僧が瞑想している姿。専門家から見ればいろいろ指摘するところはある。しかし、素人としてはいい出来だった。「手の形はうまく彫れていますが、ちょっと左によりすぎましたね。真ん中にあった方が瞑想している形になったのに」と答えた。その人は「これはこれでいいんです」と怒ったのだそうだ。「この手の形は、手話では万国共通の言葉で、ハート、心ということなんです」その人は言った。
それが、どの羅漢さんなのか。それぞれの背には彫った人の名前も刻んである。手話の「心」の羅漢さんを探したり、その名を見つけるのも楽しみになる。
西村さんは、この本のなかに、仏像の手の位置や指の形には、誰にも分かりやすいように、決まったメッセージがあって、それは手話のようなものだとしばしば書かれている。
サインを読み取るのに敏感な手話の人々こそ、ここで1200の羅漢さんたちの声を、より深く聴くことができる。ひたむきな祈りの姿には、、厳しいの、哀しいの、やさしいの、かわいいの、楽しいの、表情もさまざま。
帰ろうかと、下の段におりて「さようなら。また来ます」と振り向いて、もう一度羅漢さんたちを一巡した時だった。私たちに「見つけて欲しかったの」とでもいうような一体の像があった。身体いっぱいに、粘土に手のひらを押しつけたような、手、手、手、まるで手模様の袈裟だ。「ねっ、手話の仏さんと呼ぼうか」。豆塚さんはうなづいてもうシャッターの音を響かせていた。
〔人形工房&カフェテラス 「アイトワ」〕
畑の向こうに落柿舎を見ながら、常寂光寺に突き当たり、左に曲がると間もなく竹林に入る。このあたりは観光客もまばらな静寂の世界だった。秋風の音が遠くから聞こえ、間をおいて竹林がざわめく。故郷で聞いた竹藪の秋から冬の音だった。
静寂を余儀なくされたろうあ者の人々は、風にゆれる竹にどんな想いをオーバーラップさせるのだろうか。
左の竹林の根元には大ぶりの水瓶が上向きに、下向きに、中には割れた底から竹が伸びているのもある。これも一つの嵯峨野風景だ。まっすぐ行くと小倉池になるが、ふと右側に目をやった。木の枝に小さなブランコがかかって、お人形が遊んでいる。その下の木の又にも、ちょっと茶目っ気なもう一人の子がいる。
森の詩を読んでいるような、お人形の世界だった。
秋の夕日に照らされたカエデやモミジの枝が、赤や黄やうす緑の淡いレース模様になって子どもたちの遠景を彩っていた。
 
その子どもたちの帽子や衣服がとても気になった。「すごいのを着ている」と思った。
不思議な子どもたちに誘われるように門口に行ってみた。お人形の写真が3枚、そのそばに「ほうき草が色づきました」のメッセージ、ケーキと飲み物の案内。秋の冷気を感じる午後、ちょっと休憩もしたい。中庭に入ると、荷車にいっぱいの花々。見上げると建物2階の窓辺からも、お人形が外を眺めている。「こっち、来ない?」と誘っているようにも見える。観せてもらえるのかな。とにかくお茶をいただこう。
店の前には2鉢のすっかり紅葉したほうき草。
中に入るとバターの甘い香りがした。もてなしてくれるのは、白い清楚なエプロン姿の上品な女性。お茶を待つ間に、脇のおみやげ コーナーをのぞく。お人形の絵はがきや写真集、作者のエッセー集の本などがある。人形作家の森小夜子さんのものだ。絵はがきを3枚買うと、展示室が観られる仕組みになっていた。
紅茶が冷めないよう、ティーポットに厚手のカバーをかけて出してくれる。ひと口含んだケーキが温かい。旅人をそれとなく癒す、ねぎらいのやさしさ。
「コミュニティ嵯峨野」が「全国手話研修センター」になったので、と説明すると「ありがとうってこうでしたかね」と手話、むかし少し習ったことがあるとのことだった。
別の棟の展示場に案内していただく。一階は工房で、求めた本『人形にいのちを込めて』(大和書房)にサインをお願いした。こころよく受け取ってくださる小夜子さんの指には白い粘土がついていた。製作の最中にお邪魔したのだ。
 
2階の展示室のガラスケースのなかには、ユーラシアの民族衣装を着せてもらったいっぱいのお人形がいた。帽子、首飾り、上着、ズボンやスカート、靴など心を込めて手作りして身に着けさせたものだ。髪の毛や皮膚の色、しぐさもさまざまな恰好をしている。とした表情は、少数民族の誇りに満ちている。
小夜子さんが、こうした世界を表現しはじめたのは、NHKの番組「シルクロード」がきっかけだそうで、「ローラン」など地名の名前をもらった子どもたちが多い。
「彼らは日本人が失ってしまった民族の誇り、生活の知恵や技術を大事にしているに違いないと興味を抱いたのです」と語る。
着せている服はそうした土地の古布や、独自に染めた物、日にあてて色落ちさせたり工夫している。それらは野良仕事など庶民の働く衣服を着せているのだという。
しかし、あくまで小夜子さんのイメージによるもので、忠実な再現ではない。それゆえ、芸術の香り高い、・かな想いの世界にひたされる人形たちだ。
撮影する豆塚さんが「先生、この子は男の子ですか」と尋ねた。「いいえ、女の子ですが、私のはどっちかというと、男の子みたいな女の子なんです」。
「『みみ』に写真で登場していただけますか」、お願いした。「いいですよ。じゃあアフガンの子どもにしましょう」。抱いたのは、イスラムのスカーフを被った少女だった。
展示場の子どもたちは、お喋りはできないけれど、ユーラシアのさまざまな民族のメッセージを聞かせてくれる。
「おたぎ念仏寺」と「アイトワ」、二つの嵯峨野風景は、声なく語りあえる場所だった。癒されながら、製作者たちの心を読み取る世界である。ろうあ者も健聴者も同じだ。 |
|
|
◆女の碑−京都嵯峨野 常寂光寺
 「野は嵯峨野、さらなり。印南野。交野。狛野……」清少納言が『枕草子』に「野といえば嵯峨野はいうまでもない」といちばんにあげている。 「野は嵯峨野、さらなり。印南野。交野。狛野……」清少納言が『枕草子』に「野といえば嵯峨野はいうまでもない」といちばんにあげている。
『源氏物語』には斎宮ゆかりの野宮(ののみや)神社が登場する。
ここ嵯峨野は遠く京に都が開かれて以来、春秋をとわず人々をひきつけてきた名所だ。
この秋は、カメラマンの豆塚猛さんとレンタサイクルに乗って、何度も取材に走りまわった。京都人の私たちの目でとっておきの嵯峨野案内を出そうという目論見からだ。
俳人の向井去来の住まいした落柿舎を畑の向こうに眺めながら、まっすぐ進むと正面に常寂光寺が見える。人どおりの多い天竜寺界隈と比べて、ひなびたかつての嵯峨野風景が残るのが、このあたりである。その景観とお寺の名前にひかれてまずは立ち寄ってみた。
常寂光寺への入り口には大きな掲示板がある。そこには「憲法第九条」の冒頭「永久に戦争を放棄すること」「武力を保持しない」ことが、墨筆あざやかに掲げられていた。アメリカのイラク攻撃に対しても「ストップ」の、そして「わたしたちは平和憲法の改悪に反対します」の小さなチラシも張ってある。どんなご住職のお寺なのかと気がかりな誘(いざな)いを感じていた。
たどりつく仁王門、茅葺きの簡素な屋根が美しい。左右に立つ仁王さんは、鎌倉期の仏師運慶作と伝えられ、腕や胸の筋肉はいうまでもなく、踏ん張った足の指先にまで力強さがみなぎっている。
仁王門からの険しい石段を登ると本堂である。さらにその上に優美な多宝塔が建っている。そのあたりから・に煙るように、京都の市街地が北から南まで、一望できる。
「小倉百人一首」を選んだ藤原定家の時雨邸跡の一つにも上げられ、(時雨邸跡は三ケ所伝えられている)背景は小倉山なのである。定家が、はるかに都を眺望する所に山荘を営み、百人一首を選んでいたのかもしれないと想像をたくましくさせる
本堂に下りて、ふと気になる標示板に気づいた。矢印が「女の碑」と示している。なんだろうかと標(しるべ)をたどると坂道を下る。あたりの樹木の間に抱かれるように碑(いしぶみ)はあった。そこに
女ひとり
生き
ここに
平和を
希う
美しくやさしい文字が白く刻まれている。参議院議員だった市川房枝さんの揮毫であった。そばに由緒を刻んだ石碑が添えられている。
第二次世界大戦で200 万人に及ぶ若者が戦場に消えた。
その影で、そうした若者と結ばれるはずだった女性たちが、独身のまま自立の道を歩むことになった。その数およそ五十万人。
困難な時代に立ち向かって彼女たちは生きた。その「あかし」として、この碑を刻み、二度と戦争を繰り返さない戒めと、後の世に一人生きる女性たちへの語りかけを期待するとしている。
建立したのは「独身婦人連盟」の人々で、「一九七九年十二月 女の碑の会」とある。
平安時代の藤原定家、鎌倉時代の運慶とならんで、20世紀の女性運動家の市川房枝さん揮毫の碑、お寺が歴史を刻んでいる。その信仰は仏教でもあるが、ここは平和信仰の地でもあるような気がした。ひっそり佇む碑は、観光という癒しを越えて、わたしたちの目を歴史や現実に引き戻してくれる。
ご住職の長尾憲彰さんに、その不思議な巡り合わせを電話でお尋ねしてみた。
「ああ、女坂の碑ですね」と言う。お寺の本堂に向かう急な石段を登れない人のための坂道を「女坂」と呼ぶのだそうだ。
青春時代を戦争のただ中ですごした長尾さんは、戦後、大学を卒業し大阪市立大学に務められた。その時、同僚に心理学の助手をしていた谷嘉代子さん(後花園大学教授)がいた。彼女が活動していたのが「独身婦人連盟」だった。住職でもあった長尾さんに「女の碑」の希望があり、建立に至ったのだという。
戦争を経て、荒れ放題だったお寺は、長尾さんの熱い平和への願いの中で、少しずつ復興し、今日の美しいたたずまいをとりもどした。
長尾さんは、読経しながら、いつも戦禍に散った人々の菩提を弔っているのだと語る。
21世紀、まだ飢餓や戦火のニュースが絶えない。そして、憲法第九条は今危機にある。
|
|
|
◆ブルー・ジーンズ (『ひとはなにを着てきたか』所収)
 初めてコカコーラを飲んだのは高校生の時だった。 初めてコカコーラを飲んだのは高校生の時だった。
スーパーマーケットの試飲で、 一人に一本ずつ配るという大盤振る舞いだった。 はじめて口にする、 木の根っこを煎じたような奇妙な味にみんな首を傾げたが、
たちまちアメリカ映画の主人公になったような 「かっこいい飲み物」 として広がっていった。 それは東京オリンピック前だった。
ジーンズを見かけるようになったのもその頃からである。 フォークソングとともに町に広がった。
60年安保のデモ行進をしたのは、 黒い詰め襟の学生たちだったが、 ベトナム反戦のデモ行進する学生たちの多くはジーンズスタイルだった。
今ではおしゃれな街着としても愛用されるブルー・ジーンズは、 最初は 「ジーパン」 と呼ばれて、 時代に敏感な若者たちのファッションとして登場した。
ジーンズの日本最初の上陸は1950年、 東京のアメ横でアメリカの古着のジーンズが売られたことに始まる。 日本で発売されるのは1962年である。
今日では大学生の通学服にもなっているが、 教室でのジーンズ姿が物議をかもした時代もあった。 77年、 大阪大学でアメリカ人男性講師がジーンズ姿の女子学生に教室からの退出を命じたことが新聞各紙に報道された。
服装が 「……らしさ」 を現すシンボルだった時代の壁を打ち破ったのは、 まさにジーンズの登場からだといえる。 フォークソングが若者の心を自由に表現したように、
ジーンズは時代の枠を打ち破る、 もう一つの表現のシンボルでもあった。
女子学生たちは 「ジーパンは家庭にしばりつけられた女性を解放した服装だ」 と主張した。 事実彼女たちはどんどん社会進出し、 結婚後、 出産後も働き続けるようになっていった。
さて、 そのジーンズについて面白い本がある。 出石尚三さんの 『完本 ブルー・ジーンズ』 である。 出石さんによれば、 その名前の由来はジーンという生地で仕立てられたパンツという意味で、
本国のアメリカではメーカーの名前から 「リーヴァイス」 と呼ばれていた。
ジーンズはリーヴァイス社によって発売されるのだが、 このズボンを最初に作ったのはヤコブ・ディビスという一人の仕立て職人だった。 木樵きこり用の丈夫なズボンをと依頼を受け、
幌馬車のキャンバス生地で仕立て、 ほつれやすいポケットなどのポイントに鋲びょうを打ちつけてみた。 この堅牢な鋲打ちズボンが好評を得て少しずつ注文が増え、
わずか1年ばかりで200本も売れるようになった。 彼は特許を思いたちリーヴァイス・ストラウス社に提携を申し入れた。 特許は1873年に認可、
量産され、 今日まで130年もの歴史をもっているのだ。
しかし、 長いあいだそれはカリフォルニア地方の労働着で、 現代のファッションとして登場するのは1930年代になってからのことである。 農村の労働着が都市に登場したのは、
休暇で観光牧場を訪れた人々が、 カウボーイ姿に変身するために着たものを持ちかえり、 日常着として愛用したのがきっかけだった。 こうして都市に登場したジーンズは次第に人々の日常着として浸透していった。
生地は藍染のデニムで仕立てられていた。 タテ糸に藍染が、 綾織りのヨコ糸に白が使われ、 裏側は白い。 新品はかなり固いので、 最初から着やすいように、
ワン・ウオッシュで、 つまり軽く洗って売り出された。 また、 わざわざ漂白したり、 シェイヴィング加工して履きこんだ風合いを出したものもある。
丈夫な生地は洗濯を重ねて、 着こむほど心地よく身体に馴染んでくれる。
ほつれたり、 膝に穴があいたものに、 ファッション性さえ認めて愛されるのは、 数ある衣服の中でもジーンズだけだろう。
出石さんは 「すべての服は消耗することを前提に生まれる。 しかしジーンズだけは違う。 消耗ではなく年齢を刻むことが、 カンロクを加えることが可能な服なのである」
とその魅力を書いている。
かつて背広はホワイトカラーと呼ばれる人々の象徴だった。 今、 ジーンズはあらゆる階層に性差を超えて破れるまで履きこまれ、 服装からステータスシンボルを取り上げるまでになった。
木樵の服だったジーンズこそ、 服装から階級や階層を取り除くことを先駆けた、 革命の戦士だったのだ。
|
|
|
◆ためさんの藤布 (『ひとはなにを着てきたか』所収)
 藤布のふるさと 藤布のふるさと
丹後半島の上世屋集落
「花より雪が消えたいうことで、 春が来たなと思います。 花はただきれいだな、 と思って見るだけですわな。 雪が消えるのが一番嬉うれしいですわ」
京都市内の病院で療養中の光野ためさんは、 長年暮らした村を思いだすようにぽつりと言った。 天橋立のある宮津から車で40分ほど。 日本海に突き出した丹後半島の内陸部、
上世屋が、 ためさんが80歳まで藤織りを続けた村である。
そこは雪の深いところで、 12月の初雪とともに長い冬がやってくる。 軒下まで降り積んだ雪は年によっては3月の半ばにならないと解けない。
その長い冬を、 この村の女性たちは藤布織りをしてすごしてきた。
藤布は丈夫で、 夏の山仕事に汗をかいても着心地のいい衣類だったという。 自分たちの衣類だけではない。 海草とりの袋、 畳の縁 (へり) や、
ふとんを包む大ぶろしき、 蒸し器の敷布など、 日用品としても重宝で、 炭焼きとともに、 この村の大切な現金収入となるのであった。
1914年生まれのためさんは、 小学校の3年ころから、 お母さんのかたわらで、 機の経(たて)糸の糊のりつけを手伝ったり、 糸をつなぐ藤績うみをした。
女の子は、 機に足が届くようになるのが、 織りはじめという村の暮らしだった。
それにしても、 藤づるは見るからに頑丈である。 粗いつるから、 どのように繊維をとるのだろう。
初夏の山を美しく彩る藤は、 その前後から収穫期である。 山野に自生している藤を探して森に入る。
この村で藤布が盛んだった時代はそれは男衆の仕事で、 よその山まで出掛けた。 ふつう山の植物は所有者以外は採れないが、 藤だけは他の木に絡まって成長をさまたげるので、
採集が自由だったのだという。
藤づるから皮をはぎ取るのは、 力がいる。 つるを槌で叩いて皮をはぐ。 表皮の固い鬼皮を取り除き、 繊維部分の中皮だけにして、 乾燥させて冬まで保存しておく。
秋の収穫期がすぎ、 水もいっそう冷たくなるころから、 本格的な藤の作業が始まる。
まず、 中皮を灰汁(あく)で煮て、 谷川にさらし、 V字型のこきばしで何度もしごいて純粋の繊維だけにする。 それを米糠を溶いた湯に浸し、 再び乾燥させる。
糠の油がしみて糸の滑りがよくなるのだ。 寒い季節の水仕事はつらい。 藤は雪解け水など、 冷たいほどよく晒されて白くなるのだという。
「さぶうて、 冷てゃし、 手ですることだで手間かかるで。 指の皮が薄うなって、 血がでることもあるわな」
ためさんは言う。
その繊維を、 指で細かく割いて、 つないでいく。 藤績みだ。 1日しても績めるのはわずか。 一反分績むには40日もかかるという。
そして糸車にかける。 「ひい、 ふう、 みい、 よう、 いつつ」 と撚りをかけ、 今度は糸車を反対に回して巻き取る。 「こんなふうに」 と、
ためさんは目の前で指を泳がせた。 そこを藤糸がつたっているように、 指はリズミカルに空を紡いでいた。
こうして、 ようやく機織りの用意が整う。 藤布は手間のかかる仕事だ。
「これが、 母の織ったものです」。 ご子息の保さんがさしだした。 それは、 あの硬い藤のつるから採れたものとは思えない、 優しい肌触りだった。
色はごく薄い茶褐色。 ためさんの手が藤の妖精をよびだしたような風合いだ。
藤布の故郷が見たい。 新緑の頃ころ、 上世屋村を訪れた。 下世屋の集落がきれて、 まだ人里があるかと思うほど山道をたどると、 ぽっかりと村が現れた。
美しい棚田が、 絹糸のような雨に煙っていた。 万葉以来の藤布は、 この里で最後はためさん一人に守られて生きてきたのだ。
|
|
|
◆凪ぐ海のように (季刊『MIMI』2002年秋号No.97
掲載 全日本ろうあ連盟発行)
 漁師の朝は早い。 漁師の朝は早い。
ようやく、空が白みはじめると、志田喜代松さんは船のエンジンをかける。
志田さんは二級小型船舶操縦士の資格をもつ、漁師だ。この免許は5年ごとに更新を受けなければならない。普通は講習会にでて更新手続きをするが、ろう者の志田さんは、特例で海運局の職員に同乗してもらい実地のチェックを受け、ずっと更新し続けてきた。
志田さんがお父さんについて漁師になったのは18歳の時だった。まだ手こぎの船をあやつる時代のことだった。
「ギイッ、ギイッ」と櫓が軋む音が聞こえる。志田さんの手こぎの手話は力強い。
その日から、75歳の今日まで、ずっと漁師一筋の人生だった。
それを支えて、連れ添ってきたのは、やはりろう者の妻、こずゑさん86歳である。
数年前までこずゑさんも、共に船に乗るおしどり漁師だったが、病気がちなのと高齢のため、最近は乗ってない。
恋女房である。つい先頃もこずゑさんは入院生活をしていた。ようやく退院できた日、玄関に出迎えた志田さんは、うっすらと目に涙をためて妻を迎えた。
「ずっと二人で生きていきたい」、こずゑさんを見初めた時から、いちずに愛し続けてきた。
こずゑさんは「あの人、この人、誰々さんは? 聞こえない女の人、いっぱいいるよ」と訪ねた。
「いや、おまえが一番いい」そういって、熱心にプロポーズした。
朝から船に乗る、夕方5時には、取れた魚を土産に持って、こずゑさんの家の前に立った。そして日が暮れて、家の灯がつくまで、ずっと外で待っていた。
1927年生まれの志田さんは、ろう学校に行けなかった。淡路島にろう学校ができるのは、1948年のことである。
志田さんの住む北淡町からこずゑさんの実家のある三原町には、バスを何度を乗換えなければならない。バスの行き先の文字も読めないし、人に訪ねようにも、耳は聞こえない。
それでも、志田さんは間違うことなく、こずゑさんの家の前に立っていた。
ようやく二人が結婚したのは、志田さん30歳の時だった。
二人で漁に出た。こずゑさんはヒラメ釣りが上手で、魚が餌をつつく当たりと引きのタイミングが抜群で、これだけは、志田さんはかなわないという。ヒラメは高級魚で価格もうんといいのだ。
志田さんはどうやって魚のいるポイントを決めているのだろう。
それだけは秘密で、他の漁師仲間に聞かれても教えない。みんなが漁をしている所に向かって、一緒に走るふりをして、途中から、自分のポイントに行く。
志田さんはぬめりがあって扱いにくいアナゴをさばくのが、とても上手い。アナゴがたくさん獲れた日は、きれいにさばいて漁協に納めると、いい値段がついた。
「こうやるのだ」志田さんは、アナゴをさばく手話する。「骨に身が残らないように」と、志田さんの手元は何匹も何匹もアナゴをさばいて見せてくれる。
学校に行けなかったけれども、魚の名前はみんなカタカナで覚えた。計算も覚えた。カワハギ、アジ、ベラ、ハマチ、スズキ、サバ、タコ、イカ、アナゴ、ヒラメ、そしてウナギも獲る。
今日も、早朝6時、志田さんの船は浅野湊をでる。瀬戸の海はおだやかに凪いでいた。そのつり船は、もう40年以上も走ったとは思えないほどきれいだ。掃除もていねいに行き届いている。自分でペンキを塗って手入れしているのだという。
30分ほど沖合にでると、志田さんは仕掛けを下ろしはじめた。自分で作ったというピンクの毛針だ。ビニールが虫の羽のように光って見える。40〜50の毛針を下ろすと、等間隔に小指ほどの錘のついた綱になる。それを手で引いたり、緩めたりして加減する。そして、顔をほころばせて、船のヘリをコツコツと叩いて「つついてる。つついてる」と教えてくれた。
「これが、つついている当たりだ」と、代わる代わる綱を持たせてくれるが、波なのか引きなのか、誰にも感覚がつかめない。しばらく様子をみて、引き上げるとタチウオが銀の体をうねらせて上がってきた。
船を走らせながら、志田さんは、この船も手放そうかと思っているという。こずゑさんが「二人で老人ホームに行こう」というのだ。「80歳まではやれると思う」「だが、やはり二人で暮らし続けたい」。志田さんの心はこずゑさんの方に傾いている。
淡路島北淡路町は、阪神大震災の震源地だった。
志田さんの家も全壊した。こずゑさんと二人、怪我もなく無事だった。この町はどの家も真新しい。それが、地震のひどさを物語っている。志田さん夫婦は、今、町営住宅に住んでいる。
こずゑさんは、ちょっと広めの、住宅の出窓に座って、双眼鏡で海をみる。夫が一人で漁に出るようになってから、ずっとそうしている。夫の船が見えるわけではない。ただそうして海を見ていたいのだ。
やがて、漁を終えた夫は、原動機付きの三輪車で坂道を登ってくる。双眼鏡はその姿もとらえる。
志田さんは、こずゑさんを指さして、両手を大きく拡げて、やさしく抱くようなしぐさをした。どんな言葉にもおきかえられない、深い愛を表す手話だった。ずっとずっと、二人で寄り添って生きたいと思っている。
|
|
|
◆子山羊
 きのう、つばめを見た」「きょう、虎杖(いたどり)の芽を見つけた」。 きのう、つばめを見た」「きょう、虎杖(いたどり)の芽を見つけた」。
こうして四国山脈の山間(やまあい)の村にも春が訪れる。
進級して、新学期が始まる頃、先生の声は、きまって私の耳に届かなかった。
そわそわして、窓から外をチラチラながめて、「早く、家に帰りたい!」そればかり考えていた。
春は命の誕生の季節である。子猫、子山羊、鶏のひな、子牛、あらゆる家畜の赤ちゃんが私を待っていた。
とりわけその年、気もそぞろだったのは、子山羊のことがあったからだ。
お産の時、子山羊の足にからまって母山羊の子宮も一緒に出てしまった。獣医を呼んで手当てをしたが、母山羊は三日三晩、悲鳴をあげて鳴き続けた。
そんなわけで、子山羊の乳も足りなかった。父が町から一缶の粉ミルクを買ってきた。子山羊のために粉ミルクを買うことは当時の農家では異例のことであった。そもそも、山羊は乳を搾(と)るために飼っていたのだから。
いつしか子山羊の世話は私の役目になっていた。ある日、私は父に「ミルクが足りない」と言った。父は「粉ミルクは高いから、これで終わりにしよう」。子山羊はみるまにやせた。母山羊はどうにか元気になったが、乳の出が足りないのだ。
私は若草を摘んできては細かく刻み、青汁に絞って飲ませ、少し食べられるようになると、ハコベなど柔らかな草を摘んで世話をしていた。そうしたことから、早く家に帰って、子山羊と遊びたい。そればかり考えていた。
ところが、ある日、家に帰ると、子山羊は隣家に貰われていた。
「私の子山羊が隣の小屋にいる!」
私はわんわん泣きながら飛んでいって、小屋の閂(かんぬき)をあけ、子山羊を抱いて連れ戻った。
父は私の頭をなでながら言った。
「みっこのおかげで、子山羊も大きくなった。もう一人で葉っぱが食べられる。家に2匹も山羊はいらんろう。貰(もろ)うてくれる人がいたら、飼(こ)うてもらわにゃいかん。冬になったらどうする。干し草がいっぱい要るろう。いつまでも家にはおけんから……」
私は悔しくて泣いた。
「わかったか。わかったら、自分で戻してき」
そうして、私は泣きながら子山羊を隣家の小屋に抱いていった。
今も、運よく取材先で子山羊に出会うことがある。いつも抱き方が上手いと褒められる。私は、そんな時、あの少女の日に帰る。
|
|
|
◆ベトちゃんドクちゃんだけでなく
 20世紀は戦争の世紀ともいわれた。科学技術は進歩したが、それだけ戦争の惨禍もひどかった。30年に渡る戦いの末、ベトナムがアメリカに勝利したのは
1975年のことだった。しかし、今もベトナムでは戦争の傷が癒えない。大量に散布された枯葉剤が原因で、奇形や障害をもった子どもが誕生し、まだそれが続いている。 20世紀は戦争の世紀ともいわれた。科学技術は進歩したが、それだけ戦争の惨禍もひどかった。30年に渡る戦いの末、ベトナムがアメリカに勝利したのは
1975年のことだった。しかし、今もベトナムでは戦争の傷が癒えない。大量に散布された枯葉剤が原因で、奇形や障害をもった子どもが誕生し、まだそれが続いている。
藤本文朗滋賀大学名誉教授は「ベトちゃんドクちゃんの発達を願う会」をたちあげ、長年に渡って交流をしてこられた。この会は二人への支援だけでなく、ベトナムの障害児の実態調査や、障害児師範学校の設立などの支援を続けてきた。
11年間の日越交流レポートを発行した時のことだった。「タイトルをどうしようか」という時、ある女性会員が「私ね、『ベトちゃんドクちゃんだけでなく』って、いつも思うの」と発言した。そのままタイトルにいただいた。表紙には、小さな男の子が木製の車椅子で微笑んでいる写真を選んだ。お父さんがその子の体型にあわせて、手作りしたと思われる、粗末だが、愛のこもった車椅子だった。
以来、私のなかで、もっとベトナムへの支援をという想いがふくらんでいた。
昨年末、教授からお誘いがあって、はじめて訪越した。
ベトナムで、すでに青年に達したドクくんに会った。午前中3時間コンピュータ製作の仕事に出て、日本語教室にも通っていると語り、松葉杖で活発に動く輝く彼を見たとき、私の脳裏には、ガラスを隔てた手術室から、フォン博士が「今、二人の身体が離れた」と手でサインした日のテレビ報道が浮かんだ。
私は今、京都府丹後の「与謝の海養護学校」の写真集を編集している。重い障害を越えて生きる、命の力と笑顔を見ていると「こんな保障をベトナムにも……」と思う。
ベトナムでは、まだ「社会福祉」が根づいていない。
(写真は、筆者とドクちゃん。2000年12月、ホーチミン障害児師範学校に講師として訪問した際)
|
|
|
◆どんな出版社か
出版社をはじめたばかりの頃、「お宅はどんなカラーの出版社ですか」と聞かれるのが一番こまった。出版社は、発行している本からその傾向を見ていただく。それが点数が少ないのだ。
「じゃー、どんな本を作っていきたいの」と聞かれて、得々と説明した。
「うん、なかなか面白い。けど、あなたの本は表紙は出来てるけど、まだページが真っ白だ」。
そんなときから、25年が過ぎた。もう誰も「どんなカラーの出版社ですか」とは尋ねない。370冊以上の本が語ってくれるからだ。
そしたら「出版社は一つ当てたら大きいからな。当たるまでの辛抱だよ」と励ましてくれる。私は「とんでもない。当たったら倒産します」と怖がっている。意外な売れ足がついて、書店から注文が殺到すると、次々増刷する。
ところが、本は読者が買わない限り、売れたことにはならない。書店からの返品が在庫になって倉庫を食う。やがて断裁処分ともなって、制作費だけが借金になる。こんな怖いことはないから、「売らんかな」はしない。
うちのような小さい出版社は、世の中の小さな声を本の形にしたり、そう大量には売れないが、誠実な学術書で研究者と共に夢を育てるような仕事なのだ。
映画『釣りバカ日記』で浜ちゃんが言う。“お魚が鯛やマグロばっかりじゃ、つまんないじゃないの。いろいろな魚がいるから面白いんだよ”。
良書を安価で大量に提供してくれる大出版も、学術研究の地味な成果や、地域や運動の小さな声を届ける、うちような小さな出版社も必要なのだ。 |
|
|
◆『かけがえのない命よ』
文理閣のシリーズに『はたらく人々のいのちと健康』というのがある。3冊出て、4冊目「VDT労働」は滋賀医大西山勝夫教授が執筆中、続編の企画も進めている。編集会議で研究者の意見を聞き、「現代労働負担研究会」や「労災職業病一泊学校」などの研究会に、本の売り込みを兼ねて出席することもある。
そこで、さまざまの現場からの報告を聞いて驚く。新機種の発売が、2週間後だと新聞報道された時に、工場では、まだ最後の試行錯誤が行われている。最後に製品検査をするエンジニアは、ユーザー用のマニュアルを片手にサンプルを徹夜で検査し、結果を翌朝に現場に戻す。夕方には指摘箇所を修正した製品が届く。再び徹夜検査を行う。一刻、一秒を争って新製品を発売日に間に合わせる。限界状況で働く労働者は「いつ欠陥自動車や欠陥器具が出ても、現場から見れば、全く不思議ではない」と指摘する。
あるカーナビセットの製品テスト現場では、1人で2台のCD検査を同時に行う。右目・右耳は右のCD、左目・左耳は左のCDをチェック。右手でボタン操作とCDのセット、目は高速で走る数字を確認し、耳は音飛びが無いかを聞いている。1日500台から700台だ。世界の先端を誇る製品が、いつ病気になってもおかしくない加重労働から生産されているのだ。
最近、古代エジプトのピラミッドを作った労働者の墓が発掘された。当時の石灰岩の出勤台帳には、欠勤の日付と理由が記されている。自分の誕生日に休み、息子の墓参りに休み、中には二日酔いというのもある。もちろん病気の届けが最も多い。
しかし、今、日本の働く人々は病気でさえも休めない。
シリーズの3冊目が細川汀氏の『かけがえのない生命よ』だった。タイトルは氏が付けた。働く人々の現場報告を聞いていると、40年間職業病検査で全国縦断した細川氏が、働き傷んだ人々を検診しながら、胸を痛めたつぶやき「かけがえのない生命よ」がよくわかる。 |
|
|
◆スモンから甦る
加藤直樹立命館大学教授から滋賀の障害者施設「ひかり福祉会の20年の足跡」をまとめる仕事を手伝ってもらえないかという話から、足掛け4年滋賀通いをしたことがある。本作りは初めてという編集スタッフと、集めた原稿すべてを音読し、問題点や書換えを討論するという会議をねばりづよく4年間続けて、1998
年に『明日をつくる仲間たち』が出版となった。
私の一番印象に残っている原稿は、せつせつと綴られた一人のお母さんの手記だった。
そのお母さんは薬害のスモン病で入院生活を余儀なくされていた。喉の自由がきかず声が出せない、手足も動かず、食事も自分で摂れない寝たきり。病院のベッドで胸を痛めていたのは知的障害を持つわが子のことばかりだった。介助なしに生きられない身で夫に退院を求めた。教師の夫は一人で障害を持つ息子の世話をし、妻を病院に見舞い、勤務していた。妻の介護が加わる困難を承知で退院させた。
お母さんは必死になって、手のリハビリをした。この情景を見ていた知的障害の息子が、食事の介助をするようになった。しかし、毎朝作業所行きをぐずった。学校勤務のあるお父さんの苦闘が続く。何とか自分で作業所に連れていけないか、リハビリに励み、自動車運転免許取得に挑戦した。下半身も不自由で車椅子である。3年も続く編集の過程で、この家族の話題はさらに発展した。口のきけない車椅子のお母さんと、障害を持つ息子が、二人だけで新幹線に乗りディズニーランドに行ったのである。
本書の出版記念会は、全く経験したことのないものだった。ひかり園の20年の総括、施設の将来が語られ、熱心な実践発表が行われた。ビールもジュースもない出版記念会。障害者も大勢スピーチした。さらに驚くことがあった。そのお母さんが車椅子からスピーチしたのだ。発病から30年、声を取り戻したのだった。
ひかり園は今も発展を続けている。親の亡き後、障害者が輝いて生きられるように、グループホームもたちあげた。その発展をまた本にしたい。 |
|
|
◆カメラマン
カメラマンの豆塚猛さんとは長いつきあいである。
最近の本は写真やカットをいれて、ゆったりした大きめの活字にしないと、売れにくい。本を選ぶ読者の姿を見ていると、ペラペラめくって、ぎっしり活字が詰まっていると買わない傾向がある。
学術専門書は別として、表紙のカラー写真や、カット代わりに写真を入れることも多くなって、いつも豆塚さんにお願いしている。
しばしば撮影に同行して、注文をつけることもある。
そして、同時に人物を撮る時のレフ(反射板)持ちの助手もさせられる。
そんな時、私は彼のカメラアングルを覗いたりはしないが、被写体を見て、シャッターの音を聞いているだけで、上がりの見当がつく。「いけてる」と思うと必ずいいのが上がってくる。
彼には『ドンが聞こえなかった人々』という写真集があって、それは私がやらせてもらった仕事でもある。
長崎の原爆を見た聞こえない人々の記録で、彼は四年をかけて自費で長崎に通い続けた。仕上がった数百枚の写真を見た。聞こえない人々の清々しい笑顔、睦み合う夫婦、さりげない暮らしのなかに見せる表情はほんとうに美しかった。
「黒川さん。この彼女の手話わかりますか。彼女は『私、ブラジャーをしているのよ』って言っているんです」
そう説明された彼女は乳房の下で、大事なものを支えるように、両手を広げている。
「彼女のブラジャーには意味があるんです」と教えてくれた。
彼女は長い間聞こえない世界にいて、ろう者や手話通訳の人々と触れ合う機会がなかった。建築工事や土木現場で働くだけの暮らしだった。長崎の手話仲間が、ろうあ者の原爆体験を聞き取りをするという出会いから、様々の知識をえるようになった。社会への窓が開かれ、女性らしいお洒落の楽しみも知った。
そして、豆塚さんのカメラの前で、嬉しそうに「私、今日、ブラジャーしてるの」をしたのであった。
その豆塚さんが、「嫁はんが入院した」と電話をかけてきたのは、昨年の11月のことだった。手術を受け、抗ガン剤治療をしたが、病には勝てなかった。
「ごめんな。ごめんな」と言いながら力尽きたと聞いた。
豆塚さんの家族はしばしばモデルにもなってくれて、私の手掛ける本の世界をふっくらと豊かなものにもしてくれた。捕虫網を持って野原を駆けていたり、おばあちゃんと畑を耕したりする子どもたちはとてもかわいい。
そんな子どもを残して逝った奥さんの無念を思う。
彼女はいつもてきぱきしていた。豆塚さんが不在でも、撮影の依頼や日程で不自由することはなかった。大切な助手であり、コーディネーターで、彼女らしい心配りが見える写真もあった。
悲しみのまだ癒えない彼と、岡山で開かれた手話の集会で出会った。彼は三キロのカメラを片手に撮影に余念がなかった。手話仲間やろう者の中で、活き活きと見えた。
後日、一緒にお酒を飲んだ。
今、毎日がたまらないと言う。
「黒川さん、手話に『仕方がない』という表現があるの知ってる?。こうやって」
左の肩から右の脇の下に、袈裟がけに切る仕種をする。
「岡山で大勢のろうあ者が僕をなぐさめてくれたんです。僕は『仕方がない』という手話をしながらわかったんです。ろうあ者の『仕方がない』は、あの人たちが、正に『身を切られる』という思いでしてきた手話だった」
人生の辛さ、悲しさ、痛み……。しかし、それを「どうすることもできない」という意味を込めて「仕方がない」と表すのだと言う。
「僕は自分の痛みのなかでそれに……」。
私には彼を慰める言葉がない。
深い悲しみを越えるには、失った者と語り合い、労い、なお愛する、長い時間とエネルギーがいる。
それは、その人自身にしかできないことなのだ。 |
|
|
◆遠い声
(『遠い声近い声』はしがきより)
「嫁を見よー」
「婿を見よー」
夕闇の山にこだまして聞こえるのは嫁入行列の呼び声である。
星と月だけが美しい静寂の村で、その声は、幼い私の胸をときめかせた。
高知県の山間(やまあい)の嫁入行列は、とりたてて珍しいこともない寂しい農村に、一時の華やぎをもたらすものだった。
「嫁を見よー」「婿を見よー」
ぞうりをひっかけて、あわてて表に飛び出すと、黒い山影に、提灯の灯りが点々と道の形になって動くのが見えた。「お嫁さんだ、お嫁さんだ」と遠いその灯りが、村の家に消えていくまで、あきることなく見ていた。
いろりの火はちろちろと燃えて、ときおり薪の爆(は)ぜる音がぱちぱちと鳴る。
黒く煤けた薬罐からは、しゅんしゅんと湯気がたち、炉端で、家族が「手わざ」と呼んで夜なべにかみそ(和紙の原料梶)をへぐる(削る)音も、シュルシュルとよっぴて続いていた。
百姓の朝は早い。
祖父は寝床で「一番鶏が鳴いた」「二番鶏が鳴いた」と数えて、まだ暗いうちから起きだし、牛の世話をはじめるのだった。
冬の朝は、どの家も夕べ、へぐったかみそを干す。ようやく山の端から出た朝日は、霜柱をとかして、虹のような煙になって立ちのぼる。その中でかみそを干す腰のかがんだ祖母の姿が、影絵のように動いていた。
百姓たちの声は大きい。朝の挨拶や噂話をかわしながら、カミソ干しが一息つくと、それぞれが鎌や鍬を手に山に登る。一直線に生きる人たち。 山には山の呼び声があった。お昼のご飯の支度ができると、母は幼い私を連れて父を呼びに行った。「ホーオイ」「ホーオイ」と特別の裏声で呼びかけると、仕事をしていた遠い山の父がふりむいて「聞こえた」の合図をする。風の強い日もその声は届く。
山の暮らしには山の「声」があり、自然には季節ごとの「音」があった。
夏にはさわさわと青葉をかけぬける、風の音がした。
山が時化ると、狭い谷間を「竿かつぎ」と呼ぶ縞模様の雨が、川下から川上にぐんぐん登っていった。雨は風にあおられて、無数の「竿かつぎ」の遠征となって、いつ果てるともなく続いた。山の雨を集めた谷はすざましい轟きをあげて、濁流となってかけくだっていた。そんな時、谷は叫ぶ。
「あんたのふるさとに行くと、谷の瀬音が聞こえていたね」と大学時代の友人に言われた。私の生まれた村は折り重なる山襞の中にある。生家からは、眼下の土居川がほとんど真上からのぞいているような角度で見える。
晴天が続くと、水は翡翠(ひすい)のように透明な青さだった。その流れはせせらぎというようなおだやかなものではなく、勢いよく岩を削って仁淀川を目指して流れ下っている。夜の静寂の中でも、谷の音だけは聞こえていたから、京都から来た友人には、眠れぬほど異郷の音だったに違いない。
遠く聞こえる谷の瀬音は私のゆりかごの音だった。 けれども、その谷の音は、いつの頃からか私には「遠い声」になってしまった。ストマイや中耳炎で「耳」が傷つき、やや難聴になってしまったからである。
難聴になってからいっそう耳をすますようになった。
「音」はそれぞれの風景や情景のなかにうもれていて、普段はとりたてて気づかない。
けれども、私たちは「音」をともなってこそ、深くイメージできる世界をたくさん持っている。
山の風景にホルンが似合うように。
ふるさとの風景も、季節季節の彩りと共に小鳥の声、風の音、谷の瀬音をともなって、私の胸によみがえってくるのだ。
さまざまな「音」の世界への紀行をはじめる。
|
|
|
◆
弔いの風景
願わくわ花の下にて春死なんこの如月の望月の頃 (西行)
歴史家の赤松啓介さんの葬儀の帰り、花の道を歩きながらこの和歌(うた)を思いだした。
赤松さんは小学校を卒業後、行商など下積みの仕事を転々としながら、苦学して歴史学や民族学で独自の世界を展開された孤高の学者である。
そして、私の親友啓子さんのお父さまである。
訃報はわが家の留守番電話に、「今朝父がなくなりました。明日朝九時からお葬式です。お知らせだけ」と悲しみにあふれた声でメッセージされていた。
享年91歳の天寿を全うされた「大往生」である。
それでも「百歳まで生きると言っていたのに……」と啓子さんは絶句した。
啓子さんとは家族ぐるみのお付き合いをしていたので、赤松さんとも嵐山の料亭で食事をご一緒したことがある。
赤松さんは小さい頃の中耳炎がもとで難聴となり、当時はずいぶんご不自由になっておられた。私は聞こえない大学者を前に、食事の味もわからないほど応対に窮したが、赤松さんは淡々と箸をすすめられた。
「静かに本が読めていい」と語り、研究一筋に歩まれた人生だった。
葬儀の日、各紙の夕刊にその訃報が報じられた。写真には補聴器のコードも写っている。その補聴器で耳を傾けながら、神戸の五色塚古墳の復元事業など、市の嘱託として現場監督や文化財調査をされた。
妻の入院中も高齢にもかかわらず自活し、書斎を離れようとはしなかった。
つい最近、ようやく阪神大震災から難を逃れた蔵書や発掘品の行き先を定めて、娘の啓子さんの所に身を寄せたのだった。
力尽きるまで、強靱な精神で独自の学問を打ち立てた方であった。
朝日の夕刊亡者記事は「庶民の性風俗や民間信仰の研究でユニークな成果をあげた在野の民俗学者」と伝えている。
赤松さんは、難聴を越えて膨大な聞き書きによる庶民生活史を研究しておられる。彼は最低辺の人々を「非常民」と呼んで、その生活と文化研究から、民俗学に新しい切り口を啓(ひら)いた。
戦中、治安維持法で投獄された時も、非転向で刑期をおえた不屈の人でもあった。
その人の亡骸と私は最後の対面をした。まさに「翁」の風貌で安らかな眠りについておられた。
「野」に在った人は野に還っていくのだ、と思った。
近親者だけにかこまれたつつましい葬儀だった。
柩の蓋が閉じられようとしたとき、その生涯を支えた奥さんの澤枝さんは「ちょっと…」と制して「おじいちゃん、おじいちゃん」と頬をなでて名残を惜しんだ。妻、娘、孫、家族の別れはそれぞれに厳粛で哀惜に満ち、私の涙をさそった。
同じ光景をどこかで見た。
写真家ユージン・スミスの「スペインの村」の中の一枚である。
ベッドには昇天した老人が横たわっている。それを取り囲む数人の人々。一枚の写真に絵画のように、老人と死を悼む人々が焼き付けられている。その一人ひとりの表情に、命の終末を見つめる悲しみと、死者との距離が凝縮されている。一瞬のシャッターに込めた、スミスのメッセージが、息がつまるほどに迫ってくる。
老いた人を見送る沈黙の光景は、悲しいほど、美しいものだ。
音のない世界にも、濃密な時間が流れている。
そして、音は感情の波動でもある。 |
|
|
◆星星花の少女たち−中国竹林寺で−
 高知市五台山の牧野植物園には、高校時代にしばしば行った。 高知市五台山の牧野植物園には、高校時代にしばしば行った。
この五台山が中国の仏教聖地五台山に由来する事を知るのはずっと後のことである。さらに竹林寺が本家本元の中国の五台山に有ることを知ったのは、この夏の中国旅行を計画中のことだった。
五台山に行くなら、ぜひ竹林寺も訪問したいと思っていた。夢がかなった。
山西省・五台山は北京から西南に約300キロに位置する。
竹林寺は古刹の立ち並ぶ台懐鎮の町から、山の中腹にうねうねとカーブを描いた道を登った所にある。私たちのバスは大車溝村を過ぎ、小車溝村に着く。
「溝」とは、このあたりの季節川のことで、雨の降らない時期はすっかり干上がってしまう川である。そして、そのほとりにそって車が通れる、つまり「大車溝」は大きな車が「小車溝」は小さな車が通れる村の意味である。竹林寺のある小車溝はそれだけ小さな村である。
バスが着くと、どこから見ていたのか10人ぐらいの子どもたちが駆け降りて来て、一列にならんで出迎えてくれた。私たちはこんな時のために用意しているお土産をだした。鉛筆である。鉛筆を配っていると、あっちこっちから子どもが集まって来る。
子どもたちは私たちを囲んで、前になり、後ろになりながら一緒に竹林寺への坂道を登る。誰かが配った色紙を持っている子もいて、折り鶴を折っていると、「教えて、教えて」と取り囲まれる。
そんな時だった。一人の少女が道端の草むらに入って、野の花をいっぱい摘んで私にプレゼントしてくれた。草むらにはエーデルワイスやマツムシ草、千鳥草や野菊、ワレモコウなどの花々が咲き乱れ、一面お花畑である。楽しいひとときの中で、「私も何かしてあげたい!」少女はそう思って私には花を摘んでくれたのだ。
名前のわからない高山植物も多かった。中でも一番小さな花、わすれな草ほどの花びらを摘んで、私は少女に聞いた。「この花の名は?」。「チンチンファー」。手帳を出すと「星星花」と書く。目の前の少女のように可憐な花だ。
星の形をした淡いブルーの花びら。その花びらが五台山の夜空いっぱいに咲くのだ。こんな小さな花にも名前をつけて、標高2000メートルの厳しい自然とともに生きてきた人たちの長い長いつましい暮らしの歴史を思った。
少女たちは、花を摘んでは名前を書く。
「鴨子花」「灯籠花」「蚊子花」……。
私の手帳には、ていねいで可愛い中国語の花の文字が並んだ。
五台山は洛陽の白馬寺についで、中国で二番目に築営された仏教の聖地で、五つの山は文殊菩薩が住まいする所だという。
竹林寺は唐代の高僧法照が創建した寺である。日本の天台宗慈覚大師がこの地で先ず参詣したのがこの寺で、当時六つの院があり、40人ほどの僧侶がいたという。竹林寺は中国に二つしかない公式の受戒の寺でもあった。今は再建された本堂中央に釈迦像、その左右に若き阿難と老いた迦葉が、壁面に羅漢像が復元されている。文化大革命の惨禍をあびたためである。その下の優美な白亜の塔のみが、かつての竹林寺の面影を留めている。明代に建てられたもので、五層八角、それぞれの角の軒に風鐸がかけられ、風のある日には四周に響くという。晴天無風のこの日はその音色を楽しむことはできなかった。
竹林寺から遠望する山々のたおやかな緑の稜線が美しい。
山肌に拓かれた畑には、燕麦、粟、蕎麦などが作られているが、けっして豊かな土地ではない。
少女たちは本殿の羅漢像に中国式に額づいて祈りを捧げていた。
シルクロードの敦煌、大同の雲崗、洛陽の龍門、重慶の大足と様々な仏教遺跡を訪ねたが、そこにはすでに信仰はなかった。
しかし、この五台山は今も数千の僧侶が住む、生きた信仰の地である。その中に身を置くとき、厳粛な空気を感じて私も喜捨箱にささやかな元を入れて、手を合わせた。
少女たちは帰り道も私たちから離れなかった。バスは村のずっと下で待っているので、「もうお家に帰りなさい。再見」と言うのだが、とうとうバスまで見送ってくれた。
アーイー(おばちゃん)今度いつ来る」と聞く。
少女の摘んでくれた花を、ホテルの新聞紙に挟んで押し花にした。残った花をペットボトルにさして、バスの窓に結わえた。花はそれから三日間山西省を発つまで、昼間はバスの窓に、夜は私のベッドのそばで咲き続けた。小さな蕾も花開いていった。
蕾のような少女たちが、私の旅を一際思い出深いものにしてくれた。子どもは世界のどの土地でも心やすらぐ、天使だ。
|
|
|
「わたし」という人生
(2009年6月12日 高知新聞朝刊「所感雑感」掲載)
「わたし」の人生はなにだったか。
高齢社会、多くの人々がふとそんなことを考える。勲章をもらったわけではない、たいした肩書があったわけでもない、でも「わたしは生きてきた」と。
ときどき、そういった方から本を作りたいと相談がある。昨年は、八十歳になる女性の自分史を『島根 益田川の夢』として全国発売にした。島根の農家に生まれて結婚し、やがて京都で出稼ぎした。修学旅行旅館の「女中」さんから始まり、その後、今は世界に有名なゲームメーカーとなっている企業で、黙々と百人一首のカルタを張り続けた。戦中・戦後の益田の風景や暮らし模様は貴重な記録で、難聴をかかえながら、子どものために働き続けた、慎ましく美しい人生が綴られていた。
「わたし」をふりかえるとき、何かの形で本にまとめてみたいと思う人はほかにもいる。ある日、「写真集を出したいのですが…」と一本の電話があった。まもなく、分厚いアルバムが4冊届いた。川村邦博さんという方で、かつて私の兄が編集した『追憶の碑−大西・その村と学校−』を入手していて、自分の写真集を作りたいと思ったのだという。聞くと、私と同じ赤藪という村のご出身だった。添えられた手紙には、「あなたのお姉さんと、ままごとをした門口の八手の木は今もありますか」と尋ねてあった。
川村さんは、昭和27年に中学校を卒業して、愛媛県別子にある鉱山に就職し、その鉱山の播磨事業所などで43年間働き、現在は加古川市に住んでおられる。写真集のご希望は六部だった。あとがきに、「ぜひ、あなたの文章を」と希望された。
アルバムをめくった。ルーツになる人々の写真は『追憶の碑』の、家族に関係する卒業写真や、村の行事などがついていた。やがて、彼は青年になり美しい女性と出会った。ういういしいデートの写真。どんな言葉でプロポーズしたのだろう。仕事の写真や会社の慰安旅行もある。真面目で、誠実な社員の表情。家族との食事風景や妻との温泉旅行。幸せの主人公は、誇らしく盃を持っている。温泉街を夫婦仲良く散歩する下駄の音まで聞こえてきそうだ。孫たちにも恵まれた。
「苦労は写真に写りませんが、言えんばあ、しました。山に生まれた者はどんなことでも頑張れます。転居や入院も何回も。共働きでようやくここまできました…」。人生の役目を終え、あらためてふり返るアルバムの軌跡。
私は、表紙に花環に囲まれてほほえむご夫婦とふるさとの村の全景を、裏表紙に向いの大渡山の写真を選んだ。
あとがきには「川村様や、私の父祖たちはこの大渡山に出る朝日を拝み、畑仕事、山仕事に明け暮れて、私たちの命を育ててくれました」と記した。六部の写真集は、こうした小部数も手掛ける仕事仲間が引き受けてくれた。
今年の大相撲夏場所優勝を決めた、日馬富士関の一言。「僕を生んでくれた父と母にありがとうと言いたい」。「わたし」とはなにか。人はときどきそう思う。アフリカのサバンナを二本足で歩いた遠い祖先から、現代までつながった命の、「わたし」という偶然を一生懸命生きる。
それが「わたし」だ。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|