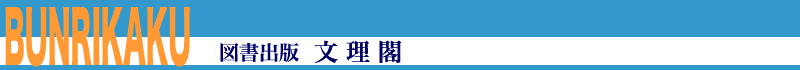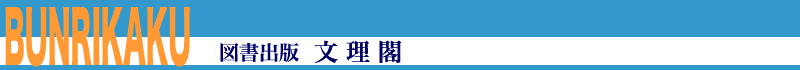| |
|
|
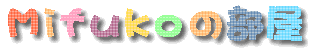
おんなと男上方流|現代のことば|MIFUKOのぷちシネマ|私の京都新聞評|Mifukoの筆箱 |
|
| |
|
現代のことば |
|
2006年8月より、京都新聞夕刊で担当した「現代のことば」を転載しています。
|
|
| ◆手が語るヒロシマ (2006/8/01)
「出版屋さんですか。一つ当たると大きいからなあ」、ときおりそう言われる。私は、当たる本というのは、大手・中堅出版が、当てることを目指した、企画と作戦で成功しているのではないかと、長年の経験で考える。
こんな本こそと、熱い思いで出版しても当たったことがない。そればかりか、ときには採算的に難しい本も手がけてきた。それでも、こうして続いているのは、書き手と読者が応援してくれるからだ。
こんな本がある。
長崎のろう者たちの聞き書き『原爆を見た聞こえない人々』と、豆塚猛氏の写真集『ドンが聞こえなかった人々』である。
長崎のろうあ者の聞きとりがはじまったのは、被爆後四十五年後のことだった。彼らは誰にも、その体験を聞かれたことがなかった。四十五年間、心に封印されていた記憶は鮮明だった。「手よ語れ、もっと語れ」の、熱いサインに応えて、手話が、全身の身振りが、原爆を再現した。聞き手たちは「まるで疑似体験しているようだった」と語る。
長崎の記録を出版して十五年がたつ。ずっと、気がかりだったのは、ヒロシマのろうあ者の体験が出版できてないことだった。さきごろ、ヒロシマから連絡がきた。
今、手もとに聞きとり原稿と、同時進行で撮影した写真が届いて、編集作業に入っている。
語り手の多くが、当時、ろう学校小学部の子どもだった。すでに七十歳前後になっている。その人々の記憶もまた鮮烈だ。
一九四五年八月六日。
朝食のちゃぶ台を囲む家族、犬とたわむれる少年、柱にもたれて一人留守番する少女。
戦時下とはいえ、それぞれの市民の朝があった。
「駄菓子屋のシロ(犬)と遊んでいた」。そこまで話した高夫勝巳さんは、突然、駐輪場の壁に跳びつき、顔を押しつけて、しばらく動かなかった。音もなく、光もなく、一瞬に十メートルも吹き飛ばされた模様を、全身で表現したのだ。
真っ暗な中で、われに帰ったとき、身体はまだ張りつけ状態のままだった。
そして、黒い雨が降った……。
音はなくても、あの惨状は伝えられる。正に沈黙のヒロシマだ。
森岡正勝さんは、爆心地から二・五キロメートルほど離れた自宅で被爆した。「一瞬光った。闇になった。屋根瓦が落ち、土煙でなにも見えん。落ちてきた瓦が熱いっ」。どうしたのかと見上げた空に、一筋の雲が…。右に、左にこぶをつくりながら高く昇り、巨大なきのこ雲になるのを目撃した。
その光景が十八枚の連続写真となって、まるでアニメーションのコマ送りのように、克明に再現されている。一枚として、同じ手話(身振りも)はなく、同じ表情はない。恐怖と驚きの顔。両手でかばうように目をおおい、うずくまる姿。
語り手たちが、手話であるゆえ、写真は見事に原爆を見せている。
彼らは、今も、一つの位牌を大切に守っている。そこには、被爆死したろうあ仲間、十六人の名前が記されている。この位牌を抱いて、毎年、平和記念式典に参加してきた。
まもなく六十一回目の八月六日がくる。人類は、まだ「核」のない平和にたどりつけない。
|
|
| |
|
|
◆外国人犯罪と通訳問題 (2006/9/29 夕刊)
中国語をかじったころ、品物を「東西(ドンシ)」と呼ぶと知って、なるほどと思った。広大な、かの国の人々が、品物は東や西からやって来ると表現したのかと、大いなるロマンさえ感じた。私たち日本人は「薬を飲む」といい、中国では「薬を食べる」という。
さすが医食同源の国と納得する。
このように小さな言葉一つとっても、そこには言語を育てた民族の生活習慣や歴史が詰まっている。
最近、どきっとしたのは、広島女児殺人事件の報道で、ヤギ容疑者が「悪魔が入って動かした」と弁解しているとの記事を見たときだった。メディアは一斉に自分の犯罪を悪魔のしわざにするとは、と非難した。幼い少女が犠牲になったことを思うと、犯人への怒りを感じ、家族はどんなに悔しいだろうと胸が痛む。
しかし、「悪魔が動かした」を、その言葉どおりに解釈していいものかとの疑問は残った。やがて、第一審がおわって無期懲役の判決がおりたが、そのときの報道にも、この言葉が出てきたから、法廷審理をとおして、この言葉は生きていたのだろう。
日本語には「魔が差した」という言葉がある。日本国語大辞典によると「心の中に悪魔がはいったように、ふと悪念を起こす。思いもよらない出来心をおこす」とある。仮に日本人が海外で犯罪をおかし、この言葉を使ったらどのように訳され、解釈されるだろうか。
今年亡くなった、著名なロシア語通訳者で作家の米原万理さんも、その著『不実な美女か貞淑な醜女(ブス)か』に通訳の難しさを書いている。
「異なる言語間のコードの転換ともなると、一対一の対応ではとうていとらえきれない。言語は、その担い手である民族の文化とか、歴史とか、風習などを背景にした独特の世界観や思考法とかを内包しているものだ。そういった言語の間でのコード転換は、非常に複雑であると同時に、曖昧模糊(あいまいもこ)とした面が多々あって、なかなか一筋縄ではいかないのである」。
神戸女学院大学助教授の長尾ひろみさんは、『社会福祉と通訳論』という本のなかで、法廷通訳には慎重さと、かつ十分な法廷用語の知識がなければならないと指摘する。長尾さんは長年にわたる法廷通訳人の経験から、法廷での通訳者には検定制度の導入が必要だと訴えている。
現在の法廷通訳人は裁判官の面接に受かれば登録され、必要に応じて呼び出される。語学力や専門知識の厳密な試験はないという。しかし、法律知識や法廷用語に精通した通訳がされないために、判決に影響を与える場合もおこる。たとえば私たちが何気なく使っている「みだりに」という言葉も、法廷では「法の除外事由がないままに」を意味する。
法律用語を的確に通訳できる法廷通訳者の必要性は、日本に滞在する外国人犯罪のみの問題ではない。
もう人々の記憶に遠いが、一九九二年、オーストラリアでおきたメルボルン事件では、トランクの二重蓋内にヘロインを隠し持ちこんだとして、日本人が有罪となり服役させられた。彼らは今も冤罪だと訴えているが、犯罪者の汚名から解放されていない。幸いにも、取り調べ模様のテープが存在し、長尾さんたちは弁護団の依頼で通訳と被疑者の日本語テープを起こした。そこには、適切な通訳が行われなかったばかりに、日本人が冤罪に巻きこまれたことを証明するに十分な内容があった。
最近、外国人のかかわる事件が増加している。法廷通訳者の養成と検定制度の導入は、急がれる課題だろう。言語の壁を越えた裁判が行われることで、冤罪が防がれ、私たちも事件に対する正確な情報をえられる。 |
|
|
◆二人の障害児を育てたお母さん (2006/11/27)
東京タワー、新幹線、アポロ宇宙飛行士の月面到着、明日にはまた新しいなにかがあるかもしれない、そんな期待に満ちた時代のことだ。
一九七〇年の大阪万博。
そのお祭り広場に、一つの幸せな家族がいた。元気に太った男の赤ちゃんを囲む二人のおじいちゃんと、若い夫婦。
しかし、その後、赤ちゃんはポリオワクチンを飲んで感染し、「もう一人を」と望んだ二番目の女の子は脳性マヒだった。
障害児ということばさえ知らなかった川瀬とし江さんは、信明と愛子、二人の重い障害児の母となった。病院まわり、宗教入信、離婚の危機、あらゆる体験をした。「このハンドルを切ったら…」、夫はカーブにさしかかる度に口にした。外出しても、うつむいて小さくなっていた。
そんなとし江さんが変わるのは、整肢園で「早く普通の保育園に」と言われたときだった。早速一人で役場に出かけた。
「障害児はリハビリさえしてたらいい。ほんまは家でひっそり育てるもんやっ」。窓口に行く度に、叱られているような言葉が降ってきた。
けれども、もうどんな拒絶にもひるまなかった。
ようやく入った保育園で、歩けない娘が、一人ですべり台にひざで這い登り、向きをかえ、うつ伏せなってすべり降りる情景を見た。地面には、娘の得意気な笑顔があった。
とし江さんの子育て期は、障害児が就学免除から義務教育制に移行した時代だった。
二人の子どもは、教育事情に合わせて、どちらかが施設にいた。会いに行くたびに、別れが辛かった。いつか必ず引き取って、家族みんなで暮らしたいと思っていた。
子どもたちが養護学校を卒業すると、それからはもう通うところがない。在宅では、せっかく身につけた成長の道が閉ざされる。お母さん仲間や施設の人々と、障害者が通う作業所や施設を立ち上げた。資金を補うために、資源回収やパン配達をはじめた。
ようやく、作業所の見通しがたって、十七歳の息子を施設から引き取ることができた。やがてそれぞれが成人式を迎える。
「ああ、この子たちも、二十歳になれた。新成人にこんな重症者もいることも知ってほしい」、そんな思いで式に出た。晴れ着を汚さないように、夫婦は娘のよだれを拭き続けた。記念撮影のとき、「お願いできませんか」と、隣の席の娘さんにタオルを頼んだ。娘さんは、しきりに口もとをぬぐってくれた。
数年後、作業所で若い職員に出会った。「私は信明くんと同じ成人式でした。重い障害者をはじめて見て、それで福祉の仕事を選んだのです」。二人の子どものリハビリのため長浜赤十字病院に行ったとき、「私、愛子ちゃんと同じ成人式やったんよ。それで、なにかできることないかとリハビリを勉強したんです」と声をかけられた。
さきごろ、このお母さんのたくましい子育てを描いた本が完成し、出版記念会が開かれた。自宅には百人近い人々が集まった。本にもたくさんの人々が登場する。編集するとき、どこまで名前を残すか迷ったが、全員フルネームで載せた。一人ぼっちで障害者の介護はできない。地域や仲間たちに見守られ、福祉サービス支援があって、家族は守られる。
いま、とし江さんたちの前に、四月から施行の障害者自立支援法が立ちはだかる。
福祉サービスに利用者負担がかかるのだ。お金がないため、再び、障害者が家庭に閉じ込められてはならない。 |
|
|
◆美しい国の面影 (2007/01/31)
 毎朝、数匹のねこが通ってくる。
毎朝、数匹のねこが通ってくる。
こっそり飼っていたが、近頃は食べ物を届けてくれる人がいたり、出張などで留守のときは、ご近所が面倒を見てくれる。
迷彩柄のをピカソ呼んでいる。鉄工所の屋根裏に住まわせてもらい、イビキをかいて眠るそうだ。彼女は鼻炎を患っている。
うちの野良たちではあるが、地域のねこでもあって、「姿が見えない」と心配してくれたり、どこそこで見かけたと教えてくれる。
私が住んでいるのは、京都駅からそう遠くない鴨川ぞいの町である。
商店街ではないが、酒屋、畳屋、豆腐屋、八百屋、魚屋、鉄工所、営繕屋に雑貨屋、それに町医者も自動車整備工場もあるから、まるで、映画「三丁目の夕日」を少し現代風にしたような町だ。
二十年ほど前、引っ越したばかりの頃、畳屋の奥さんに「仕事をもろてるさかい、なるだけお得意先で買い物するんよ」と聞かされた。
住宅地にばかり住んできた私は、お互いの商売を消費し合って生きるという町の営みをはじめて知った。
三世代が暮らす家も多く、お地蔵さんには、しばしば真新しいよだれかけが掛かった。誕生した赤ちゃんの無事な成長を願ったものだ。
お年寄りは家族に看取られて旅立った。
私が、その町にとけこめるようになったのは、順番で回ってきた地域の世話役をしたときだった。会費を集めたり、広報を配ったりするうち、町の人々と親しくなった。
最近、材木店が引っ越したあと、地響きをたてて取り壊しがあったかと思うと、マンション建設の掲示が出た。京都市の窓口で「建築紛争の予防と解決に向けて」という冊子を貰って配り、地元説明会を前に、住民のアンケートを取った。「ワンルームマンションの住民は、収集日でなくてもゴミを出すからこまる」「賃貸だからどんな人が来るか不安」「住民が増えると町が活気づく」「建物が新しくなると景観もよくなる」、いろいろな意見が出た。やがて、それらを取り入れた協定書が交わされた。
マンション建設を阻止することは難しいのだから、町の声を反映した計画であってほしい。新しい住民と、どう交流できるか、建設後の地元の課題になるだろう。ぜひ町内会に入ってほしいという声もある。
町の姿は少しずつ変わっていく。
「この張り替えが、わしのできる最後やろな。次のときはもう…」と言っていた畳屋さんが店をたたんだ。機械を取り壊すからと、労いの御神酒をかけていた。「長い間、家族や職人さんを養のうてくれた機械やったね」と言うと、畳屋さんの顔はたちまち少年の日に戻り、当時の界隈の様や、二代に渡る家業のことを懐かしそうに語ってくれた。
暮れには、豆腐屋さんが店じまいの札をさげた。「あそこの豆腐は美味かった。外ばかりやのうて、中までツルンとしてた。なんとか頑張ってほしかったなあ」、配達に来た酒屋の息子さんが残念がる。
渡辺京二著「逝きし世の面影」には江戸末期から明治中期の外国人の見た日本の情景がある。箱庭のように美しい農村の姿、人々の闊達とした笑い声。街路には子どもがはしゃぎ、犬が寝そべり、ねこが走る。
あるフランス人が、小さな石を寝そべった犬のそばに投げた。そのとき、微動だにしない犬の姿に、彼はこの国では犬がいじめられることもないのだと感動している。
逝きし世の面影が、この町には残る。美しい日本の面影だ。。 |
|
|
◆菜の花で走るバス (2007/04/03)
 中国南部、貴州省、そこは見渡す限り、菜の花の海だった。遠く、薄曇りの空に溶けるまで、平地も段々畑も菜の花におおわれていた。ここは菜種油の大生産地である。 中国南部、貴州省、そこは見渡す限り、菜の花の海だった。遠く、薄曇りの空に溶けるまで、平地も段々畑も菜の花におおわれていた。ここは菜種油の大生産地である。
菜種が日本に伝わったのは弥生時代だという。在来種のアブラナで、野菜としても食べられてきた。その油は、とくに中世末から、食用、灯火、燃料として活用された。今も花の蕾が、私たちの食卓にのる。
今井敬潤さんの「くだもの・やさいの文化誌」によれば、江戸期の秋田地方では飢餓対策の糧(かて)として記録されている。寒さに強く、油として商品性が高い上に、主食の不足分を補う大切な野菜でもあった。
菜の花といえば、唱歌の「朧月夜」だ。ビルの間から仰ぎ見るおぼろ月、頬をなでる微風、香る緑、その空気を浴びると、たちまち菜の花の原風景のまぼろしが見える。
「朧月夜」に歌われた菜の花は、明治時代に欧米から伝わった西洋アブラナで、戦後、安価な外国産の大量輸入で衰退するまで、長く日本の春を彩ってきた。
今、私たちの台所に、純粋の菜種油はないが、豆腐屋さんは油揚用に使う。コーン、ひまわり、オリーブ、綿の実、菜種…、私たちは世界中から届く油を食べている。
ところが、最近、「菜の花エコプロジェクト」と呼んで菜種栽培を復活させていると聞き、その活動センターの「あいとうエコプラザ菜の花館」を滋賀県東近江市に訪ねた。
それは、一人の役場職員の発案から始まった。現在、市の愛東支所に勤める奥村清和さんが、町の環境担当だったころ、琵琶湖の水質汚染が問題になり、県は条例で洗剤のリンを規制した。奥村さんは環境担当としてゴミ問題を考えるうちに、消費者グループが展開していた、廃油の石鹸作りに着目する。一九八六年のことだった。
町が設けた廃油回収ポストには、住民の協力でたくさん台所油が集まるようになった。
石鹸作りだけでなく、処理した廃油で役場のトラックなど、ディーゼルエンジンも動きはじめた。現在、東近江市所有のトラックや、路線バス二台もこの油で走っている。
そういう活動の中で、思いついたのが菜種の復活だった。減反政策の転作作物として、かつて、稲の裏作だった菜種を提案したのだ。一九九八年のことである。麦など他の奨励作物と比べて補助金が少ない上に、手間のかかる作物だが、応えてくれた農民たちがいた
。コンバインや搾油機を導入し菜種油が復活した。
こうした取り組みへの、政府の補助金は、期待したほど出なかったが、粘りづよく続けて行くうち、注目を浴び、今は「菜の花エコプロジェクト」として、国にも評価され、全国に波及しつつある。
「仮に全国の田畑に菜種を植えても、今のエネルギー問題は解決できません。けれども環境問題を考えると、大切です」、奥村さんは語る。
見学の途中、ちょうどトラックが入ってきた。廃気ガスからは焦げた天ぷらの匂いがした。このガスは石油のように黒い煙を吐かない。
三月、伊吹山系はまだ雪で白い。
その北風のなか。キャベツの苗のような菜種が、子どもが両の手のひらを広げたほどに成長していた。この花は、歌のとおり晩春のおぼろ月の頃に咲き、やがて食卓にのぼり、廃油となってトラックを走らせる。
小さな試みが、世界有数のエネルギー消費国の人々に、環境問題を考えさせる種を蒔いている。
人間の知恵と感性はすごい。
夜空におぼろ月を見て、地上に菜の花の車を走らせる。
|
|
|
◆五十人の墓碑名 (2007/06/11)
 あはれいまひとたび あはれいまひとたび
わがいとけなき日の名を
よびてたまわれ
風のふく日のとほくより
わが名をよびてたまわれ…
展示場の壁に、三好達治の詩がある。その隣に、氏名、年齢、職業を記した一覧表。50人の名前。年齢は25、41、 35歳…。
職業も各種製造会社職員、銀行員、公務員、医師、判事などさまざま。年齢は享年を示している。
一覧表は墓碑銘である。
今年四月、京都市下京区のひと・まち交流館の小さな一室。過労・うつ病自殺をテーマにした展示会があった。NPO法人「働く者のメンタルヘルス相談室」(大阪市北区)が行った。
歩を進めると、今年二月労災認定された東京都の小児科医師、中原利郎さんはじめ、幾多の人々の写真や手記がある。どの写真も家族や友人、仲間との楽しいひとときの中にいて、屈託のない笑顔だ。
その笑顔が、なぜ消され、自ら命を絶つに至ったのか。残された家族は自らを責め、無念の思いにうちひしがれてきた。
そんな一人、伏見区に住む寺西笑子さんは、夫の彰さんを49歳で失った。笑子んもまた、「なぜ、助けられなかったか」と苦しみ抜いた。働きざかりの夫婦には、大学生と中学生の息子たちがいた。
「自分との戦いでした。ようやく壁を乗り越えたとき、夫は会社に追い詰められたのだと判断し、行動を起こすことができました」と語る。
過労死110番に電話し、労災申請準備の一歩を踏み出した。昨年、笑子さんは地裁から高裁と長い損害賠償裁判を経て、会社と和解にこぎつけた。労災申請準備から全面解決まで10年余りの道のりだ。
夫の彰さんは、東山区三条にあったそば屋の店長だった。中学卒業後、大手電気メーカーで、毎日が機械の部品づくり。一生続けたくない、将来は自分の店を持ちたいと調理師の資格をとり、料理人となった。たちまち腕を上げ厨房のチーフに抜擢され、生き生きと働いていた。
歯車が狂ったのは店長に指名されてからだ。宴会場もある大店舗。売り上げノルマが厳しく「右肩上がりに伸びてない」と叱責される。労働時間も長く、帰宅はいつも深夜。
何度も血尿をだしたが、そのたび、内科から精神科にまわされている。
食事の箸もすすまない。おしゃれだったのに着替えもしない、風呂にも入らなくなっていた。
その日は、バレンタインデーだった。ハート型のチョコレートに女子学生のようなメッセージを添えるのが常だったが、「まごころをこめて」とだけ記して渡した。いつもは即
座に反応するのに、黙ったまま出勤した。その夜は帰宅せず、未明、一人で旅だってしまった。
裁判では、追い込まれていく職場での様子が証言されていく。それを知るのが一番辛かった。「一生懸命働いてきたのに、勝たなかったら、夫の無念は晴らせない」と耐えた。
この5月17日の京都新聞は「過労自殺、最多の六六人」と一面トップで報道した。厚生労働省の集計で、昨年度は前年より六割近く増加した。厚労省はノルマ達成など過大な仕事量、職場のサポートも不十分で過労自殺すると指摘している。
一方、経済界は、本人の自己管理の問題だと、「労働時間の規制除外制度の導入」を政府に迫っている。
展示会で見た、50人の墓碑銘を思う。背後に労災申請までたどりつけない、幾多の家族のすそ野が広がっている。命は一つだ。 |
|
|
◆自費出版の時代 (2007/08/09)
 「私の本 書店にない」 「私の本 書店にない」
「自費本著者が版元提訴」
七月五日付けの京都新聞朝刊にこんな見出しの記事が載った。訴えの内容は、「書籍は全国各地の書店で販売する体制」と広告され、それを信じて版元に印刷・宣伝費用を支払った。
しかし、版元は書籍の紹介文を書店に送付するだけで、もし注文がなければ一冊も店頭にでない可能性があるという内容である。
最近、「本の原稿がある人チャンス」「原稿を編集企画のプロが読んで感想を送る」といった新聞広告が目立つ。出版社を経営する私から見ると、誤解を招きやすい内容だ。
完成した本が最初に書店に出回るのが新刊配本である。まず、出版社が見本と配本希望部数を取次店に送る。取次店は現物を審査し、配本部数を決定し出版社に返事する。
こちらの提示した部数より多いこともあるが、少ないことも多い。私どもの専門書の場合はわずか数百部の単位である。
全国の書店は大小合わせると一万七千店舗に近い。そのなかの比較的大型の数百店舗に一冊か数冊ずつ入荷するのが実情だ。それでも、新刊配本すると、本は生き物のように活動を始める。書店が追加したり、読者が注文してくれるからだ。動きを見ながら私達も営業努力をする。
一方、大型書店はいうに及ばず、ターミナルの小中規模書店の平台に山積みされている本は、読者層の広い、いわばベストセラー候補といえるような本である。
書くことを職業としない、ごく普通の市民が、自費出版で本を作って、書店に並び、売れることを期待しても現実はとてもきびしい。
私も、しばしば自費出版の相談を受ける。市民が本を書きたい、出したいと思うのはいいことだ。内容を検討して、次のようにアドバイスする。「市場にだすことは費用の点でもお勧めできない。ご自分が本を買うときはどうやって選ばれますか」。ほとんどの方は納得される。
市場に出さなくても、その人にとっては大切な原稿だから、お手伝いもさせていただく。出版社の名前の入らない、いわゆる「私家版」の本として。
はじめから私家版として相談にくる人もいる。「成人式の振り袖の代わりに、詩集を出したい」という女性や、何冊か句集や歌集を出した人もいる。遺稿集も多い。
そんな中で忘れられない本がある。もう、二十年も前、涙をいっぱいためた若い御夫婦が見えた。生後三ヵ月の赤ちゃんを亡くされたばかりだった。話すたびにお母さんの目から涙がこぼれた。
赤ちゃんの胎動から、元気な産声の感動。幸せの絶頂から、ガンであることを告げられ、短い命を閉じるまで、詩で綴られていた。
すこやかに 育ってね
おかあさん あなたを 必ず しあわせにする
どうぞ ヨロシク!
私のあかちゃん……
お腹に宿ったときから書きためた詩は『あなたがはたちになるときに』という本になって、抱かれて帰っていった。部数二百五十冊。
つい、先頃、このお母さんが見えた。「あの本を増刷したいのです」。タイトルのとおり、今年はそのお子さんが二十歳を迎える年だった。その後、男の子と女の子に恵まれ、青年期を迎えているという。
詩集になった赤ちゃんは、今も家族の中で生きつづけ、成人式を増刷で祝ってもらった。
増刷のあとがきには、詩集を通して出会った人達に支えられ、今があると書かれている。
※写真は『 あなたがはたちになるときに』
|
|
|
◆限界集落 (2007/10/10)

※写真は、杉に浸食される集落 高知県池川町(現仁淀川町)
「限界集落」という言葉をよく耳にするようになった。
過疎地域で、行政の文書配達や道の整備、葬祭などの社会的な共同生活が営めない状況の集落を言う。
今、全国でこうした集落はどのくらいあるのだろう。
昨年の国土交通省が行った、過疎地域のアンケート調査によると、六十五歳以上が半数を占める集落は七八七三カ所。
機能維持が困難となっている集落が二九一七。
十年以内に消滅する可能性の集落と、いずれ消滅す可能性の集落は二六四一で、一九九九年の調査より二八四増加した。
今後なんの行政的手だてもなければ「限界集落」の課題は数十年に渡って続く問題になろうとしている。
私の生まれた集落も、今わずか三戸しかなく消滅寸前である。
高知県の池川町(現仁淀川町)。
ここは一九六〇年代の高度経済成長の進行とともに過疎化が進んだ。
農村地帯としては、けっして恵まれた地域ではない。険しい地形で棚田は少なく、山畑の雑穀と焼き畑、養蚕と林業の里だった。
日雇いや出稼ぎに出る家も多く、見切りをつけての離村も早かった。
一九五〇年代の木材景気のころ、父は「銀行の利子より木のふとるのが早いぞ」と、いろりばたで杉の石高を計算して喜んでいた。国や県も植林を推奨していたから、離村する農家も田や畑、所かまわず植林した。農民は、年老いるころ成長した杉がいくらかの退職金になると信じていた。
しかし、植林は残る農家に打撃だった。杉の成長が隣接農地の日照を奪う。一方、期待した植林は、やがて輸入木材の増加とともに価格が暴落。経済価値を失って手入れもなく放置された。
この地域に、30年あまり通い続けた高知大学名誉教授の大野晃さんは、綿密な聞き取りと調査で、つぶさに農村の変貌を見つづけた。その著『山村環境社会学序説』(農文協)は、現代の農山村問題の現実と、日本の環境問題への深刻な影響を報告している。
大野さんは高知県下の山村の実態を、もはや「過疎」とは呼ばない、「杉に食いつぶされる」状態だと指摘している。
箒(ほうき)を振り上げて赤トンボを追っていた子供たちの完成も今はない。
小鳥の声も消えた、「沈黙の林」に取り囲まれた集落。そこに、年額三十数万円の年金で、農作物を自給してお年寄りが暮らしている。通院には片道二、三千円もかかるタクシーしかない。葬祭や道の整備などの社会的共同生活も出来ない状態で、これを「限界集落」と呼んだ。
もう一つ驚く変化が報告されている。沢の水涸れである。谷水が涸れて、家庭の水道や頼みの棚田の水に影響する。水がなぜ涸れるのか。
近年、仁淀川大渡ダムの水位低下や、吉野川の早明浦(さめうら)ダムの渇水が報道されている。原因は降雨量の問題だけでなく、人工林の荒廃にあると指摘する。
間伐や枝打ちの手入れがない植林には下草が育たず、土地がやせ、大雨が鉄砲水となって川床を洗う。微生物も育たず、カニやエビ、魚も住めなくなる。この連鎖は海の漁場に影響する。渇水は都市の水不足ともなる。
この状況は高知県下を問わない。
昨年十二月、綾部市は「水源の里条例」を公布し、水源地域は「水源のかん養、国土、自然環境の保全、心をいやす安らぎの空間等として重要な役割をになっている…」と謳って、地域の振興と住民福祉に一歩を踏み出した。
高度経済成長政策で農民を切り捨ててきた国は、いまだになにもしていない。 |
|
|
◆食の職人ー錦 (2007/11/30)
 包丁の柄が朽ちてしまった。 包丁の柄が朽ちてしまった。
最近、町の荒物屋がなくなって修理のできる店がない。錦の有次さんに「お宅でいただいたのではないのですが…」とお願いすると、快く直してくれた。仕上がった包丁がすごい。柄は朴(ほお)の木、京都の職人さんが鬘(かつら)と呼ぶ箍(たが)の部分が水牛の角、愛用の出刃が少し恥じらうような見事な仕上がり。
塩干物を看板にする山市さんで、ふと目にとまったフグのヒレ。包装しながら、「両面炙ってくださいや。熱めに燗をして、蓋をする。いただくときに上げてね、入れとくと生臭うなります」。このお店には、ついこの前まで、かつぎ屋さんが、国鉄一番列車で若狭から干物を運んできたのだそうだ。二条駅で下りたかつぎ屋さんは錦に干物を卸し、帰途に京都の物産を仕入れる。ちょっとした立ち話で聞く、お店の歴史や食べ物の知恵。
錦には、お客さんと対話する商いの姿が今も生きている。たまごを一個から買える店、野菜や魚、肉などパックされたものは少なく、欲しいい部分を必要なだけ。品物によっては包装に新聞紙を使う店もある。
そんな、錦が少し様変わりしてきた。
観光客の増加と、それを目当てに違和感のある店も現れて、虫食い状態で景観を損ねはじめている。
錦市場商店街振興組合理事長で漬物の桝イ吾社長の宇津克美さんはバブルの崩壊からの変化だという。
錦は茶道や華道の家元、寺の本山、京呉服などを背景に、もてなしの料理としての京の食文化を支えてきた。表には一般客用の品を、もう一つ、「奥の間の商売」と呼んで、仕出し屋、料亭などを対象に、プロ好みの一流の食材調達と、だし巻や佃煮などみがかれた加工品を提供し、流通のプロ、目利きたちが技を誇ってきた「食の職人」の町である。
しかし、バブルの崩壊による衰退や後継者問題などで、空き店舗がでるようになった。そこに、登場したのが、異業種の店舗だった。「錦らしさ」に危機感を抱いた組合は、空き区画のオーナーとテナントを結ぶシステムを立ち上げ、奮闘してきた。組合が仲立ちし、既存の店舗と競合せず、かつ錦に相応しい新規店舗に参入してもらう努力だ。
宇津さんは、観光客に対する位置づけも、一見さんでなく「将来のリピーターになって貰えるように、独自の味と顔を持った、錦ブランドの品質を守ること」と力説する。
古くは「宇治拾遺物語」にも登場する錦は、江戸幕府公認の魚市場となり、四百年の伝統を培い、幾度もの危機を乗り越えた歴史を持つ。
最初の危機は明治維新の問屋の特権の廃止。自由営業による競争で、古くからの店舗がわずか七軒に衰退した。次の危機は、一九二八(昭和三)年、日本初の京都中央卸売市場の誕生だった。錦の卸業者の半分が中央卸売り市場に移り、空店舗ばかりとなる。三度目の危機は戦後の「京都市水産物販売許可規則」で、魚屋は町内二、三軒と指定された。
危機の度、商店街は結束して知恵を絞り、「京の台所」としての技をみがき、繁栄を守ってきた。四度目の危機は大手スーパーダイエーの進出騒動だった。「阻止」を決めた組合は、電光石火わずか十数時間で予定地のど真ん中を買収、阻止した。
今、新たな危機に直面する。四百年も続いた商店街は、活動する文化遺産である。宇津さんは「京都は職人の町、量より質を重んじる」と語る。
職人の伝統は食に限らない。いま、日本中が職人を見直す時代だ。
※写真は、夕方の錦市場
|
|
|
◆昭和の記憶 (2008/2/01)
出版屋をしていると、ときおり、自費出版の相談を受ける。そんな中で、時として、プロの書き手とは一味ちがった、魅力的な原稿に出会うことがある。
手元の原稿は、島根県の石見銀山遺跡に近い、益田地方の農家で育ち、今は京都に住む中村文子さんという、今年八十歳を迎える女性の自分史である。
中村さんは三十五歳ころまで島根で農家の嫁として働き、やがて家計を支えるために京都に出稼ぎに出た。大勢の修学旅行生が泊る旅館の「女中さん」から、料理屋のお運びさん、仲居さんなどさまざまな仕事につき、後には、今は有名な玩具メーカーで、百人一首のカルタ張りをしてきた。
収入の多くは故郷で育つ子どもたちに送金し、間借りの住まいで、つつましく生きてきた。
原稿には、昭和三十(一九五五)年ころまでの益田地方の地理的景観、自然の描写、農作業の一つひとつがつぶさに描かれ、日々の暮らしに織りまぜて、随所に土地の言葉がリアルに再現されている。
産湯を使う場面では、「ほんにこの子は無患(むくろ)のような目じゃこといのう」、という産婆さんの言葉。「ほんとに、この子は、羽根つき羽根の黒い実のような目をしていることよのう」という意味だろう。
当時の益田地方の農業は、稲作以外に、裏作の麦や豆類、畳表となる藺(い)草の植え付けから収穫、麻糸をとるための麻(お)の種まき、収穫、加工などで、その様がくわしく描写されている。
蒔いた麻の実は、発芽前後は雀に狙われる。子どもたちは交代で鳥追いをしなければならない。ちょうど桜の季節、節句のお弁当をつくってもらって、遊びたいさかりの少女は、一日じゅう鳴子を引っ張る鳥追いをさせられる。こうして育てた麻は皮を剥ぎ、縒りをかけて糸積(う)みする。収穫した藺草は石灰液に浸して干し、紡いだ麻糸を縦糸に、お母さんが茣蓙機(ござばた)で畳表に織って、町の業者に売りに行く。
子どもも幼いころから大切な働き手であった時代、その体験があればこそ再現できる、高度経済成長期以前の農作業と、暮らしの記録となっている。
益田川流域の恵まれた農地と、祭りや行事の御馳走など、地域独特の物語と、山陰地方の豊かな文化もかいま見える。
結婚適齢期を迎えた中村さんは意に沿わぬ縁談を、強引に父親に押し切られ、益田からほど遠い山間(あい)の農家に嫁ぎ、山村農業のきびしさと嫁の難儀を味わった。
この原稿は、自ら「昭和の時代を生きて」と題して書きためてきたものである。それは農村に生まれ生きた、多くの女性たちに共通する、昭和の記憶であり、一つの女性史ともいえる。
今年も成人式のもようが報道された。美しく着飾った新成人の女性たちは、どんな人生を歩むのだろう。
厚生労働省の人口動態統計の推計によると、二〇〇七年の婚姻数は、七十一万四千組で、前年より一万七千組減少した。
昨年の離婚数推計は二十五万五千組で、わずか二千組の減少である。
また、近年、初婚女性の年齢は二十歳代が低下傾向で、三十歳代が上昇傾向だか、上昇幅は小さい。
結婚、非婚、離婚、それぞれにドラマを持っているだろう。
高齢社会、無数の昭和の記憶が刻まれている。その原風景の総体の上に、今の日本がある。 |
|
|
◆浦じまい (2008/04/04)

自衛隊イージス艦の漁船衝突事故から、一ヵ月余がすぎた。
「浦じまいが一つの区切りとなり、音も笑いもなく謹慎していた川津に、少しずつ生活がもどりました。いま、金目鯛があがっています。清徳丸の舟神様が、三月三日、船体からお寺に戻って、住職がお経を上げました」。
「浦じまい」について調べるうちたどりついた、川津、日蓮宗津慶寺裡、宇野あや子さんの手紙の一節。
「音も笑いもなく謹慎…」。
港のおよそ三百戸の家々は、事故以来、歌舞音曲といった華やかな行為をつつしみ、ひたすら二人の漁師の安否を気づかってきた。
事故翌日から、仲間の船は毎日、吉清(きっせい)さん親子の捜索に出た。一日十万円余の船の燃料費も自前、操業をやめて、寒風の海に二人の姿を探しつづけた。出航を見送る親族が、祈るように、手をあわせていた姿が今も思い出される。
一週間後、仲間による捜索の打ち切り、「浦じまい」が行われた。
「お父さんと食べろやー」、港総出で果物や供え物を海に投げて、声を限りに呼びかける。かたわらで、前かけ姿の婦人たちが団扇(うちわ)太鼓を打ち、僧侶が読経していた。
初めて知る儀式だった。こんな伝統があったのかと、丹後の伊根や高知県須崎の漁港に問いあわせてみたが、ないとのこと。
川津とはどのような所だろう。
太平洋を望む勝浦市は、古くは縄文遺跡、律令制以前からの歴史をもっている。
「海人が子」と自称した日蓮聖人が誕生したのは、現在の鴨川市天津小湊で、川津漁港からも遠くない。
豊浜、川津、勝浦、松部、興津、浜行川(はまなめかわ)、大沢などの一帯は今も漁業が盛んである。江戸期には、いわしのほか、特にあわび漁が盛んだった。
その熨斗鮑(のしあわび)は特産品で、武蔵岩槻藩から幕府に献上されていた。
あわび捕りは海中深く潜らねばならない。男衆による海士(あま)の仕事で、時として、浮かび上がれないこともあった。
こうした場合を地元では「行きっぱなし」と呼んで、港をあげて結束捜索した。
生還も果たせず、遺体が見つからないおり、身内にも、港の仲間にも、ひとつの区切りが余儀なくされる。そうしたときは七日間をめどに、また遺体があがった時点、「浦じまい」の儀式が行われてきた。
人々が日常をとりもどすための節目の儀礼であるとともに、捜索活動で海を騒がせ、荒したことを海神に詫びる儀式だという。
「海の恵みをいただいて生きているのですから、海の神様にも祈るのです」、あや子さんは語る。
川津の港を守護する八大龍王
護水(ごすい)の善神(ぜんじん)
清徳丸勧請の舟神(せんじん)…
この法華経の声を灯として
吉清治夫氏 哲大(てつひろ)氏
一刻も早く皆の待つこの川津港に帰還させ給え…
港に響いた祈りの詞(ことば)も哀しく、二人を見つけられないまま、海上保安庁の捜索も打ちきられた。
一連の、川津漁港の姿をとおして感じたのは、外記栄太郎組合長を先頭とする漁師たちの、毅然とした姿勢だった。
自ら事故をおこしながら、繕い続けようとした自衛隊や政府関係者の軽挙な発言や行動にも、抑制された対応。おりおり下す冷静な決断。
その背景に、浦じまいに象徴される、強固なコミュニティの伝統と、海に生きる人々の人生観が見えた。
それは、都会に暮らす私たちが失ってしまった感性かもしれない。
|
|
|
◆春蚕(はるこ)の季節 (2008/06/06)
 六月上旬は、春の蚕が繭になる季節だ。
六月上旬は、春の蚕が繭になる季節だ。
東山に椎の花咲く五月半ば、福知山(京都府下)の農家を訪ねたとき、蚕は一回目の脱皮を終え二齢に達したばかりだった。
蚕は孵化(ふか)から二十二日ほどで繭(まゆ)になる。今ごろ、あの蚕たちも、吊り橋のような足場をはり、おぼろな楕円形の繭を作りはじめているだろう。
案内してくれたのは、織道楽塩野屋社長の服部芳和さん(五十八歳)である。二百五十年、十四代にわたって「御召」こと柳条縮緬を織ってきた。武家の女性や女学生に愛用された矢羽根絣も御召で、今では婦人雑誌のグラビアを飾る華の織物だ。
服部さんによれば、日本の養蚕は今や絶滅寸前の危機。京都府下では福知山、綾部のわずか三戸だけ。それも、孵化から繭まで、蚕の一生を桑ばかりで育てた繭が、極めて少なくなっているという。
今日の養蚕事情では、二、三齢まで固形の配合飼料で飼い、そののち農家に引きとられて桑で育てられることがほとんど。全国一の養蚕県群馬でも、そうした飼育が九十五パーセントをしめている。
絶滅寸前という、日本の養蚕事情はどうなのか。
政府統計によると、昨年の全国養蚕農家数は、千百六十四戸で、一昨年から百七十二戸の減となっている。
明治、大正、昭和の時代、日本は絹の国であった。
主要な輸出品目に数えられた時代、一九三二(昭和七)年には五十八万俵を記録したが、戦中の食料増産で桑畑が減り、戦後の回復でも一〇万俵を越すことはなかった。高度経済成長による過疎化で激減を続け七四(昭和四九)年輸出ゼロとなった。
養蚕農家戸数も、史上最多は二九(昭四)年の二百二十一万戸。八五(昭六〇)年に十万戸を切り、今日の減少にいたった。
背景には外国産の安価な生糸輸入があるが、国の農政もまた、養蚕を見捨ててきた。政府は九七年に養蚕農家への補助金をカットし、〇一年には、全国各地の県の養蚕担当課や試験場などが廃止された。
服部さんは、京都の農家三戸が生産する繭を、農協価格よりも高く買い取って、国産の絹糸を守っているが、その量は着物五十反に満たない。
蚕は農薬に弱い。桑畑の周辺に散布されるだけで使えなくなる。安全な場所を探し、桑の木を植えるなどの努力で増産を願っているが、農家の高齢化も心配される。
源氏物語の絹ずれの音、能や歌舞伎の華麗な衣装…。
絹織物はその技を磨き抜いて、日本の重厚な文化を彩ってきた。
「お蚕さん」と呼ばれて農村を支え、「お絹」と呼んで京の職人たちに慈しまれた、日本の蚕と絹織物。その美しい世界が、いま風前の灯火。
日本の伝統工芸や産業もまた、世代を継いで続けられなければ、保存不可能の危機にある。
※写真は、春蚕飼育の様子(2002年高知県大豊町の農家にて)
|
|
|
|
|
|
|
|